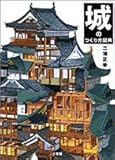他県から出張したり、引っ越してきた人が言うセリフ。
「名古屋って暑いですよね・・・」
正しくは『蒸し暑い』で、不快指数が高いんです
前回 観音寺城②はコチラ
本丸の下にある平井丸には埋門が残ってます。
本に載ってる写真はかなり立派なものだったんですが、倒木により崩れていました
埋門の先の門跡(平井丸内) 平井丸内から埋門で外へ出る城ガール隊員

wikiペディアに掲載されている写真(2008)
たった4年でカナリ崩落しちゃってますね {修復してくれないのかな
{修復してくれないのかな
立派過ぎる~~![]()
石垣構えという点では、『石階段どーん』の本丸より高級ですね!
しかも
ここで問題です
「“算木積み”の“算木”とは何でしょう。」
①考案者の名前
②そろばんの別名
③計算用の木材
④建築の角材
(参考:日本城郭検定 の模擬試験)
ちなみに私この模擬試験中級は5/7でした。
万年方向音痴なkaiさんに「文部科学省」て言われてもどこかサッパリですがな
話を観音寺城に戻しまーす。
曲輪内にも石垣がありました。
その先は一段高くなっていたので、門跡でしょうね。
平井丸奥(北)の石垣
観音寺城が現代見られるような大規模な城になったのは1532年ですが、
鉄砲の伝来(1543年)により、弘治年間(1555~1557年)に改修されたようです。
ところが佐々木六角氏が没落するのが1568年で、このとき廃城。
安土城完成が1576年ですので六角氏の築城技術の高さが窺えます。
算木積は天正年間(1573~1592年)に登場し、確立するのは1600年以降で、
最初は意図してなかったとのことです。
もしかしたら六角氏が起源かもしれませんね
ここまで順調に観音寺城攻めをしてきた城ガール隊ですが、
池田屋敷へ向かう道に“積み石”が・・・(遺構じゃないよ)
霊的なものらしく、それぞれ一礼して通らせていただきました。
その池田屋敷、低いながらも全体を石垣で固めてあり、櫓台らしき張り出した石垣や、
本丸にあった溜枡も2~3個見られました。
そしてなんと言っても広い!おそらく本丸より広いです。
「池田さん家広ーい」
「落合さん家と比べたら何倍?やるなぁ、池田さん」
などとワイワイ話しながら池田さん家訪問  ≡
≡
池田さん家もとい、池田屋敷の2段下にある曲輪にも埋門があるようなのですが、
だいぶ時間を押していましたので、今回は断念し、
観音寺城の支城である和田山城に向かいました
算木積みの問題の答えは③の計算用の木材です。
参考文献:
- ¥2,940
- Amazon.co.jp