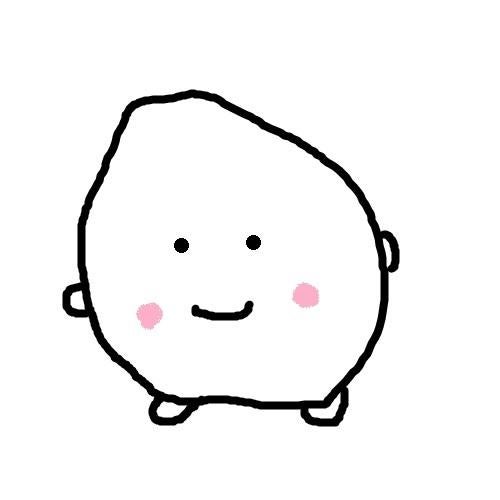27巻P122
・恵という形相の目的は「理性的被造物が神と合一すること」
キリストの恵みは増大することが出来ない。何故ならペルソナに於いて神と合一した以上それ以上大きな恵は無いから
・懐胎の瞬間から完全な仕方で神を見ていた
27巻P117
ディオニシウスによる天使の階級論
燭天使、知天使、座天使、主権、勢力、権威、支配、大天使、天使
27巻 P 135
「賜」=選ばれた人々に聖霊によって注がれる特別の神の恵。
次の七つがあげられる。
「知恵」 sapientia、「悟り」 intellectus'「知識」 scientia
「思慮」consilium、「剛毅」fortitudo、「敬虔」pietas、「畏敬」timor
この賜を受けた人の魂は、霊感に対して特別に敏感になるとともに、聖霊のすすめに速やかに対応して行動するように態勢づけられる。 『イザヤ書」第一章(二ー三節)
27巻 P196
そもそも個物が知られえないといわれ るのは、それが現存しないからではなくて、たとえ現存し感覚されたとしても、表象の段階で抽象されるからではないか。抽 象されるのは、事物の普遍的側面だけで、個物は個物である限り、能動知性の光のもとに照らし出されることは決してなく、したがって経験知の中には含まれない。その点においては、過去の個物も未来の個物も、また現存する個物も全く同じである。 もっとも個物についても、知られないのは「本質」であって、『存在」に関していえば、たしかに知られている。トマスはここでは、「存在」についての知は、考慮の外に置いているように思われる。 賦与知によっては(神の本質を知ることはできないが)、天使の本質と個物の本質を知ることができる。普通の人間はこの世の生においては、獲得知に限られているが(超自然的恵を受ける場合は別として)、キリストはこの世の生において、旅人であるとともに把握者でもあるから、能動知性の光のもとに知られうる「すべて」を完全に知るとともに、その光の及ばな い領域の「すべて」を、この世において既に、その賦与知によって、完全に知るのである。
27巻P205
トマスにおいて、「経験」とは何 を意味するか。それは、感覚経験を通して得られた 「表象」 phantasmata に関わる点では、先人の「経験」と同じであるが、 それから後がちがう。すなわち、先人によれば、経験とは、この表象に、アプリオリな賦与知を「適用する」 convertere こ とであった。トマスの場合も、同じ convertere という語が用いられるが、その意味はそれとは別となり、能動知性が表象に「向い」 convertere、これをその光によって「照らし」 ligibilisを、現実態たらしめること、すなわち表象から可知的形象を「抽象する」ことになっている。それゆえ、経験における表象は同じであるが、 先人がこれに適用する賦与知は、アプリオリにキリストの魂のうちに内在するのに対し、トマスの場合は表象のうちに可能的に含まれている「可知的形象」species intel- の場合 は、形象の源泉は表象にあり、更にその源泉は、質料的世界にあり、質料的世界こそ経験知を完成する形象の宝庫であることになる。そしてこの経験知の源泉たる質料的世界から、感覚を通し能動知性による抽象作用をへて獲得された知が経験知である。このように、同じ「経験」といっても、先人においては、いわばカント的にいえば、賦与知によって構成された 「経験」であったのに対し、トマスにおける「経験」とは、質料的世界から感覚を通して抽象された「経験」、すなわち「獲得知」となる。もっともトマスに於いて「賦与知」の存在が、否定されたわけではなく、キリストの魂における、賦与知の存在はそれとしてみとめながら、経験知は、それとは本質的に異なる「知の次元」として措定されるのである。この ことは、別の観点からいえば、アリストテレス的認識論の、トマスにおける徹底化であったともいえよう。しかしながらトマ ス自身は、このような「経験知」の、独立した次元への措定の理由を、アリストテレス説の徹底化の結果であるとはいわず、 あくまでもキリストに即して、キリストの人性が完全であるために、そのような知の領域の措定に到るのは必然であると考え ている。すなわち、キリストが人間である以上、そこには、知性の自然本性的作用があった筈であり、能動知性も、抽象作用 もあった筈である。もし賦与知がそれに代ってキリストにおいてはたらいたとすれば、能動知性はキリストにおいて不必要と なった筈である。それでは、キリストは「真の人間」でないことになる。キリストが「真の人間」である以上、キリストの内 に在る能動知性も、その作用としての抽象も、キリストのうちに存在理由を有した筈であり、したがって、それに相応する経 験知がなければならなかった、とトマスはいう。すなわち、キリストが「真の人間」であった以上、経験にもとづく経験知が あり、その知の次元において、「進歩」があったことをみとめざるをえないと主張するのである。
27巻 P 221
人間キリストが他の人々から教えられることがあり得たかという問題についてはキリストが完成した年齢に達するまでの期間において獲得知に関してはあり得た
27巻P224
人間キリストは、真の人間として、普通の人間と同様に魂と肉体とから成り、身体的感覚を通して物質的世界から経験知を受けるとともに、知性によって上から賦与知を受けた。しかし人間として最高度に完成されていたから、その知の受け方も、最高度に完全であり、その点において、普通の人間と異なっていた。
(一)経験知についていえば、普通の人間の経験は有限であり、未知なるものを残したが、キリストの経験知は「完全な能動知性の光のもとに、経験知の及ぶ限りのすべての知を有していた。
(二)賦与知についていえば、キリストの魂は、言に直接に合一し、そこからすべての知を受けていたから、人間として、賦与知によって知られうるすべてのことを知っていた。それゆえ知の不完全性をおぎなうために、天使から教えられる 必要性は、経験知においても、賦与知においても、全然なかった。だからキリストは、天使たちから知を受け取ることはなかった
27巻 P229
人間の認識能力には
・創造された初めの状態
・堕罪以後の状態
・恵によって回復される状態
・栄光において完成される状態。
という変化と上昇の過程がある。
27巻P236
「本性」としての「人間」は、個々に存在しているすべての人間に共 「通する、何らかの普遍性である。これに対して、エッセは、人間本性の普遍性が、それによって、個々の人間と成り、この現実の世界に「この人間」として、他の人間から区別されて、現実存在(エクシステレ)するように成っ たものである。人間の本性は、それ自体としては、普遍性であって、そのうちに、すべての可能的な在り方を含み ながら、それ自体として単独には、現実世界のどこにも存在していない。
27巻P238
トマスによれば 、個的人間が自然界において成立するのは、「知性的根原」が質料の領域に浸透し、質料の或る部分を自分の所有となすことによってである。このようにして、知性的根原に所有された質料は、その人間の「身体」と成る。それに対し、知性的根原は、身体に生命を与える形相となる。身体との結合によって、その全部分にわたって浸透し、これを生命づけるに到った知性的根原は、「魂」といわれる。
かくて、知性的根原を頂点となし、身体を基体となし、その中間を生命づけ結合する魂を有する、知性、魂、 身体の三層から成る具体的個的人間、すなわち、「真の人間」が現成する(第一部七六問一項参照)。
この説明の中に、エッセは表面に現われないが、形相的根原である知性と、質料的根原である身体とが、魂によって結合し、その完成した時が、その人間にエッセの与えられた時と考えられるであろう。
27巻P239
トマス固有の存在論においては、質料もエッセに関わるものとなり、単なる生成の前提ではなく、 生成の前面に現われる。すなわちそれは、まだ現実的にはいかなるものとしても存在しないが、形相を取れば、そ 『の形相のものに成りうる可能性を有して「在る」ものとして、すなわち、形相に対する可能態に「在る」ものとし 「て、エッセに関わる。このような可能態に「在る」ものも、一つの「在り方」としてエッセの及ぶ領域に含まれる。 かくて、エッセの及ぶ範囲は、現実態の領域にとどまることなく、可能態の領域にまで、拡大深化される。
27巻P246
トマスは、このような「ロゴスの世界」の創造を認めない。なぜならば、トマスによれば、創造はあくま でも、個物の創造であって、普遍性の創造は、ありえないからである。 それゆえ個物の世界の根原となる普遍の世界は、それ自体一つの被造物として、神の外に在るのではなくて、神 の内に在るもの、すなわち、神の知性のうちに思惟されて在るもの、神の思惟内容でなければならない。 この世界のうちに、いつか創造されるに到る筈のイデアは、根原的に「個物のイデア」 ideae singularium であり、種や類に関わる普遍性のイデアは、この「個物のイデア」の構成要素として、「個物のイデア」のうちに含ま れている。それゆえ、神の言のうちには、「普遍性」としての「人間」のイデアがあるだけではなく、創造によっ て、いつかこの世界に個物として現われる筈の、「この人間」に対応するイデアがあることになる。しかし、いず れのイデアも、神がそれにエッセを与えて、普遍性の次元から個物の次元に生み出すまでは、神の言のうちにイデアとして、普遍性の境地にとどまるのである。
28巻P27
それぞれのものは自分が可能的に所有している形相を、現実的に所有している他者によって現実化される。そのものは現実化する他者を能動因とし、それの結果として自分の形相を実現する。
28巻P27
自然本性的秩序、超自然的秩序、創造の秩序
人間に把握できる因果関係、人間に把握できない因果関係、因果関係なしの奇跡の連続
28巻P38
人間には3つの状態がある 「無垢の状態、罪の状態、栄光の状態」
28巻P39
能力を実行する場合、主体となるのは単なる魂ではなくて身体と結合した具体的人間であるが、能力の根源は人間の形相たる魂であり、魂を根源とする能力によってその身体も動かされる。
28巻P41
キリストが自然本性に伴う肉の苦しみに耐えたのは、それが神の善き御旨に適うことだったからである
28巻P42
キリストはその懐胎の始めから恵によって全ての罪を免かれていた。すなわち無垢の状態にあった。
それにもかかわらず本性的にアダムの子孫である限りにおいて、その罪の結果としての罰を受け取らねばならない状態にあった。
28巻P43
キリストはアダムよりも、より完全な人間本性を有していた。しかるに、アダムの身体は、無垢の状態においては、魂に全く服していた。それゆえキリストの本性は、それにも増して身体に対する魂の支配力を有していた。すなわち、その魂は自分の身体に対して全能を有していた(異論)。
これに対する答は要約されているが、これを補って答えるとす れば、次のようになるであろう。
(一)フダムが、無垢の状態において、魂が身体を支配していたというが、これはアダムの 人間本性に、それだけの力があったからではなくて、原初の義の状況においてその力を神から恵として受けて、その恵によっ て、その状態に保たれていたからである。
(二)しかしその状態においても、アダムは自分の身体を、いずれの形相にも変え ることのできる力を、受けていたわけではない。ただその状態を損うことなしに保有することができる(もし欲するならば) 力を含んでいただけである。キリストも、もし欲すればそれだけの力を受けていたであろう。
(三)だから、この点だけで、 アダムとキリストを比較して、キリストは、自分の身体を意のままに変える全能を有していたと結論することはできない。 (以上で、一応の答はできているが、それに加えて)
(四)アダムは、始めは、原初の義によって、上記の状態にあったが、 後に、罪を犯すことによって、この義を失い、その結果、罰として死に服することになった。
(五)これに対し、キリストの 本性は、(1)合一の恵によって、その知は、栄光の状態に上り、(2)また、すべての罪を免れて、無垢の状態に在るととも に、(3)アダムの子孫として、その罰を受け取り、その結果、その身体は、死に服することになった。この罰の状態におけ る限り、キリストは、身体に対して、全能を有するどころか、自然の必然性に従って、死を免れない者となった。キリストの 魂の状態は、同時に、上記の (1) (2) (3)を前提とし、異論のように、これを単純に、原初の状態におけるアダムと比較す ることはできない(以上、第二異論答)。
28巻P54
キリストの人間としての意志は、神の意志に対して独立であり人間キリストはたとえ自分の意志に反したことであっても、それが神の意思だと分かった時には潔く初めの意志を捨てて神の意志に従う。そこに人間キリストの真の意志がある。是非にとあらず思召しのままになしたまえ、この間の事情を無視して単純に神とキリストの意志はひとつだと主張する点に単一論者の誤りがある。
28巻P65
キリストって身体的欠陥あったの?
「ない方が良いと思う理由3つ」
・舐められる
・昔の預言者達も身体的欠陥を心配してたんじゃないの?
・悪魔が強いので弱いと勝てない
「あるべき理由」
・人類の罪に対して十分な償いを果たすため
・受肉の信仰を確かなものにするため。欠陥のない人間は真の人間ではない。
・忍耐の模範を我々に示すため
28巻P71
復活したキリストにはもはや痛みも苦しみもない。しかし身体は有している。その身体には生前に受けた苦しみを示す傷跡が残っている。その傷跡は今は痛みを感じないにしても生前のイエスが感じた痛みを証明する。
28巻P73
カリタスとは神から受ける恵みの愛であり、人間の自然本性的な愛ではない。 もしも恵の愛から発するのでなければ、その行為はその効果を生じないであろう。
28巻P74
「キリストはこの世において既に神をみる至福に預かっているが、キリストは特別だから、その栄光は身体には及ばない」
キリストの身体は魂の栄光の溢れを受けて完全無欠となり、従っていかなる苦痛も感受するはずはなかったのであるが、キリストの場合は特別。 自然本性的秩序を超えて神の意志が働き、魂の栄光の身体への溢れが、いわばその流れをせき止められて、身体に及ばないようにされ、そのため人間キリストはその魂の奥底においては至福の栄光を享受しながらその身体にはその栄光の力が及ばず普通の人間の身体と同様に苦しみを受ける者として放置され、事実存分に苦しみを受けなければならなかった。
28巻P86
神は意志してキリストの十字架上の苦しみを肯定した。神はしぶしぶ認める存在ではなく必然によってそれを意志する存在だからである。
キリストは人間としての自然本性に備わる自然本性的意志から言えば身体の死と苦痛とを忌避し、生と快楽とを求めるのは必然だった。なので意志の自然本性的な動きに関して言えば欠陥の必然性はキリストのうちに存在した。
しかし意志は理性の指示に従う。神の意志に従って人類救済のための償いの業として甘受すべきものと考え、強制の暴力として受け取っていた外力を神の恵みとして受け取り、自ら進んでその試練に耐えることになる。 意志の方向を転ずるか否かは彼の意志の自由決定による。そのようにして決定された意志こそはキリストに固有な意志、熟慮された意志であり、この意志に従う限り肉の欠陥は彼にとって必然的なものでなくなる。
「ゲッセマニの祈り」
最初は父よできればこの盃を私から取り去ってくださいと血の汗を出して祈った時、自然本性的意志の必然性の支配下にあったと言えるが、次第に変わっていき、思召しのままになしたまえと神の意志に身を委ねた時その意志は強制の必然から脱した。
28巻P97
マリアは人祖から伝えられてきた原罪とその罰としての死と肉体的欠陥とを継承した。すなわち無限罪ではなかった。
人間キリストはマリアから生まれて人間本性を母たるマリアから引き取ったが、それに付随する原罪は受け取らなかった。罪に関しては完全に無垢であった。にもかかわらず自ら罪を引き受けたのである。
28巻P100
人間の体が自然法則に従って死と欠陥を受けることは事実である。しかしこの法則は楽園においては神の恵みによって抑えられていた。しかし人祖は罪によってこの恵みを失い、その結果、人間は死と欠陥を受けることになった。
「俺」
キリストは自らの意志によって罪を引き受けたというが、神によるセッティングではないのか?そこはダブルの効果か?
罪を引き受けたとしても、至福の境地にあるものは現実においても栄光に預かることができる。 聖人も原罪を負った存在としてこの世に生を受けるが、神の恵みによってある程度はこの現実で栄光に預かることができる。 キリストの場合は最強だから現実においても至福の境地にあれる。 罪を引き受けたのはキリストの意志だが、せき止めは神によって行われた。ただそれもキリストは熟慮された意志によって自ら進んで選びとったということだろうか。
28巻P107
・キリストは贖罪のために必要とする恵と知の完全性に反する欠陥、例えば無知や悪への傾向は持っていない。
・共通的でなく個別的な病気や欠陥は持っていない。
・人類が共通的に引き受けた原罪による欠陥は自らの意志で引き受けた。
死、飢え、乾きなど。 そこから人類を救い出すためにキリストはやってきて、その約束を果たした。
だが依然として人類は苦しんでいるではないか?しかし死んだ後に永遠の生命が待っているという信仰を、復活で示した。
28巻P120
キリストが人間本性の欠陥を受け取ったのは 1人間の犯した罪の償いを十分に果たすため 2キリストの人間本性が真実のものであることを証明するため 3人々にとって徳の模範となる為である
28巻P129
「受肉」とは神のうちにあるロゴスが乙女マリアの腹に宿り人間キリストができること。
28巻P131
アダムの生涯は3つの時期に区別される
1 神によって創造され楽園に置かれて1人で過ごした時期
2 神によって男と女との両性に分かたれ、二人で楽園に無垢のままに過ごした時期
3 罪を犯し楽園を追放され地上を放浪するに至った時期
28巻P133
キリストの人間本性はただその身体の側面において他の人間と共通するだけで能動性としての理性的魂はアダムに由来せず従ってアダムの罪をも継承しない。だからアダムを祖とする全ての人間が共通に有する原罪をただ人間キリストのみは共有しない。すなわち罪を有しない。
28巻P135
肉欲も自然の欲望である限り悪いものではない。従って自然的に欲求することも罪ではない。それが罪となるのは秩序を外れて理性に反して欲求される場合である。 罪はこれを秩序を外れて欲する意志の側にある。このように罪の根源は意志に求められる。
28巻P136
彼自身のうちには魂の上位の部分理性に対する下位の部分肉のいかなる反乱もなかった。 悪魔の誘惑を受けても、キリストの心は肉の誘惑に動ずることがなかった。
28巻P144
最初の人間は、「恵において」創造された。この恵を、「原初の恵」 gratia originalis という。この恵のおかげで、魂と身体、その諸能力は調和を保ち、理性によって統一され、その理性は神の意志に従い、神の前に義とされていた。
この恵によっ て与えられた人間の義を 「原初の義」 iustitia originalis という。神の意志に従って生きる限り、この恵と義とは保たれ、人 間は苦しむことも死ぬこともなく、楽園において、永遠の幸福を享受する筈であった。
しかし人間は神の意志に背くことによ って、原初の恵と義とを失い、苦痛と死の支配する現世に落ちた。この最初の人間の神からの離反を「原罪」peccatum originale という。
最初の人間の子孫であるすべての人間は、本性的にこの原罪を継承している。たとえこの世に生まれて、まだ現実の罪を犯さない赤子であっても、この原罪のゆえに、罪への本性的な傾向性をまぬかれることができない。この罪への傾向性を「罪の火種 」という。この意味で、すべての人間が身に帯びる「身体の受苦性と死性」と「罪の火種」とは、原初の義「喪失」という、 同じ根原から出てくる。
28巻P147
【理性的部分の欲求=意志、非理性的部分=感覚=感覚的欲求=感性】
魂の能力は【理性的部分】と【非理性的部分】に分かたれるが、感覚的部分は、非理性的部分に属する。これらの能力にはそれぞれに対応する欲求能力がある。
感覚的部分に属する欲求、すなわち、感覚的欲求を【感性】sensualitas という。
これ対し、理性的部分に属する欲求、すなわち、理性的欲求を【意志】voluntasという。
意志の対象が普遍的善であるのに対し、感性の対象は個別的善である。この二つの欲求は、それぞれ固有の対象を志向するが、その志向の方向が一致しており、感覚的欲求が理性的欲求に従い、意志の対象が神に向かい、その方向が神を目的として一直線になるならば、その時、人間の魂は正しい方向にあると言える。
原初の人間においては、堕罪以前には、そのような正しい状態に在った。原罪の結果その方向に 狂いが生じた。そのため、感性の欲求は、必ずしも理性の欲求に従わなくなった。それゆえ人間は、正しく生きるために、その欲求を理性に従わしめるために、努力してその行動をその方向に規制し、それを習性づける必要が生じた。
そのために形成される習性が【倫理的徳】virtus moralis といわれる。
28巻P148
【感性2つ、欲性と怒性、欲性に基づく情念を欲情、怒性に基づく情念を怒情、
感性は、感覚の対象を欲求する魂の能力であるが、それはまた二つの部分に分かたれる。一つは、個々の欲求対象に対して、それが自分にとって善いものと思えばこれを欲求し、悪いものと思えばこれを忌避するはたらきのもとになる能力である。 これを【欲性】vis concupiscibilis という。
一つは、善悪の対象に対して、直接に反応するのでなく、自分にとって悪とみ られる対象に対し、逃避せず、抵抗し、克服しようとする欲求能力である。これを【怒性】vis irascibilis という。
これらの 「感覚的欲求に対応して、それにもとづく「情念」 passionesがある。欲性にもとづく情念を「欲情」 concupiscentia といい、 怒性にもとづく情念を「怒情」 ira という。これらの情念は、人間が魂と身体との結合体である限り、そこから生じてくる情念であって、それ自体、自然本性的なものであり、倫理的に善でも悪でもない。ただ理性との関係において、それらの情念が理性の命令から外れてはたらく時、倫理的立場から「悪い情念」となる。そこで情念を悪い方向から守り、理性に従ってはたらくように、理性の立場から規制し、正しい方向にはたらくように習慣づける必要が生じる。このように習慣づけられた行為 の蓄積によって、能力のうちに善い習性が生ずる。それを【倫理徳】という(前註)。またそれぞれの情念に関して、それを正しくみちびく具体的な倫理徳が成立する。たとえば、欲情を正しく規制する「節制」temperantia、怒性を正しく現制する mansuetudo の如くである。
28巻P149
(一) キリストは聖霊によって生まれた。聖霊はすべての罪を排除する。ゆえに、キリストのうちに、〈罪の火種〉はありえ ない。
(二)キリストのうちに、すべての徳が、最も完全なあり方で存在する。ゆえに、〈罪の火種〉は消滅している。
(三) キリストの受肉の目的は、人類の罪を 完全に願うことである。この目的に、〈罪の火種〉は反する。ゆえに、それがキ リストのうちに存在することはありえない。
キリストの徳は、他の人間の有する徳に較べて、「一番」ということではない。比較を絶して、絶対に「完全」ということである。それは徳の増加の連続線の「先端」ではなくて、「極限」として指定される「最も」である。それは普通の人間には、絶対に到達不可能 な「完全」である。その完全性の段階において、火種は消滅する。というよりもむしろ、この段階においては、「火種」は始めから「存在しない」。このように考えると、(一)(二)(三)の理由は同じ根原から生じ、同じ根原を別の局面からみること によって成立したものであることが知られる。すなわちその根原は、「受肉した神の子」であり、ただそれのみにこれらの理由は妥当する。
(俺)
火種もMAX化するから、理性もMAXでないと、そもそも抑え込めない。キリスト以外は理性をMAX化できないので、人間の集団もしくは人間の力を越えた悪魔などに唆された場合、抑えることは出来ない。キリストはできる。
人間本性を越えた悪への唆しがあった場合でも、神の恵に守られているから、それを越えると言うことだろう。
28巻P150
魂は、理性的部分と非理性的部分とに分かたれる。非理性的部分は更に、感覚的部分と非感覚的部分とに分かたれる。こ のうち感覚的部分は、それ自身、理性ではないが、理性的部分に近接し、その影響を直接に受けている。そして「本性的に理性に従いうる」naturaliter obedibilis nationiものである。しかしその従順は自然本性的ではあるが、必然的ではない。すなわち、「必ず」従うわけではない。従う方がその本性に適ってはいるが、しかし「従わない」こともできる。その意味で、 魂の感覚的部分は、理性に向う傾向性とともに理性から外れ、あるいは理性に背く傾向性をも有している。この反理性的傾向 性を矯めて、理性への傾向性を強め、その習慣を強化するために「徳」が必要となる。
ここに「身体的諸能力」vires corporales といわれるのは、魂の非理性的部分のうちの感覚的部分から区別された「非感覚的部分」である。具体的にいえば、「体液」 humores corporales の有する力と「植物的魂」 anima vegeta-bilis の有する力である。「体液」とは、この場合は、身体の生命を維持するに必要な体内の液状なもの、すなわち、血液、胆 汁、粘液、等をいう。これらの体液の調和ある配合によって身体の健康は維持され、その調和が崩れると病気になる。「植物 的魂」とは、人間の身体の栄養、生長、生殖、等を支配する体内の力である。これらの諸力は、感覚的部分と区別されて、直接には理性と関係せず、理性による支配を受けず、生理的、物理的、化学的法則によって独自の運動をする。「徳」には関係 「しない。
28巻P151
キリストの魂も他の人間と同じくその非理性的部分は感覚的部分と非感覚的部分とにわかたれる。そのうち感覚的部分は最も完全な徳によって罪の火種は完全に消滅している。 非感覚的部分においては他の人間と同じ欠陥を有し、そのために受苦と死をまぬかれない。しかしこの領域において見出される受苦と死は罪には関係ない。
28巻P151
感覚的部分は理性と直接に関係し、理性の作用を受ける。この部分には理性に服するように傾く傾向性とそれに反する傾向性が存在し、対立している。
【理性に服する傾向性に従って働く場合はその行為は倫理的に善】となり、
【反する行為に従って働く場合はその行為は悪】となる。
【徳】はこの善への傾向性を助長し強化する修正であり、
それに反する傾向の根源となるのが【罪の火種】である。
だから徳の力が強まるほど火種の力は弱まる。
28巻P160
キリストは罪を犯さなかったから経験による罪の知は持たなかった。しかし言と合一している人間キリストは言から直接に受ける光の元にもっと完全に明瞭に罪のなんたるかについての知を得ている。
28巻P174
普通の人間の場合は感覚的欲求のうちに生ずるパッシオは往々にして度を超えて理性の領域を侵害し人間を不道徳たらしめるが、キリストに於いては決してそのようなことは起こらずパッシオは感性の領域に留まり、その限界を超えて過度に流れることなく理性の支配に完全に服していた。 トマスによって示されるキリストは初めから常念が理性の領域を超えることがない点でストア派のチシャの五徳であるがしかし積極的に常念を抑圧することもない。普通の常念もうこれを抑圧し否定することを望まずみむねならば敢えてそれを感受しようとする更に苦痛を感受することが人類の罪の償いとなるという積極的に意味を持って受け取られている
28巻P175
普通の人間の場合は感覚的欲求のうちに生ずるパッシオは往々にして度を超えて理性の領域を侵害し人間を不道徳たらしめるが、キリストに於いては決してそのようなことは起こらずパッシオは感性の領域に留まり、その限界を超えて過度に流れることなく理性の支配に完全に服していた。 トマスによって示されるキリストは初めから情念が理性の領域を超えることがない点でストア派の知者の如くであるが、しかし積極的に情念を抑圧することもない。普通の情念も、これを抑圧し否定することを望まず、御旨ならば敢えてそれを甘受しようとする。更に苦痛を甘受することが人類の罪の償いとなるという積極的に意味を持って受け取られている。
(大食い選手権では大食いすることが善である。大食い選手権を否定する観点からは悪でもあるが。 キリストはゲームキャラのように機械的に必要に応じて動ける)
28巻P183
外部から身体が本当に傷を受け、本人の感覚と意識とか覚めている場合、彼は本当に痛みを感じる。
妄想的損傷ではなく、麻酔を受けているのでもない。
キリストはそう言う存在であった。
28巻P191
殉教者の場合は、観想の喜びは身体に伝えられ彼らの苦痛を和らげたのであるが、キリストの場合は精神の喜びは全く身体に伝えられず、従ってキリストは身に受ける苦痛を精神に由来する喜びによっていささかもやわらげられることなく肉体の苦痛としてもろに受け取らねばならなかった。
28巻P199
苦痛の対象は甘受された障害。対象とそれを甘受する魂とは直接に接触している。 悲しみの対象は心の中で有害な悪いものとして捕らえられたもの本当に有害か悪いものかは問題ではない。感覚のみならず想像力と理性が介入してくる。何らかの距離が認められる。
28巻P201
(一)「自分にあるべき苦難と死とを、心のうちに完全にしていた。そして、このようにして「知られた悪」について真の「悲しみ」を抱いていた。しかし、ただそれだけではない。
(二) 弟子たちが犯すであろうすべての罪についても、 完全に把握していた。そして弟子たちのために、それについて悲しんでいた。それだけではない。
(三) 自分を殺すであろう人たちの罪を完全に把握していた。そして彼らのために悲しんでいた。
要するにキリストは自分について起るべき「悪いことがら」だけではなく、自分をめぐる敵味方を含むすべての人の「悪いことがら」について、心の中で完全に把握して自分のためだけではなく、それらすべての人々のために、悲しんでいた。
このような仕方で、キリストのうちには真の「悲しみ」が存在したのである。
28巻P201
1、対象について。我々のpassioは往々にして不法なものに及ぶ。キリストの悲しみは決してそうならない。
2、発端について。理性によって状態づけられた欲求能力において、 passioが成立した。 だから passio による偏向によって、理性の判断が誤ることはなかった。われわれの場合は、悲しみが理性の判断に先立ち、そのため理性の判断を誤ることがある
3、結果について。われわれの場合はpassioが限度をこえて理性にまで及び、理性を自分の領分に引き寄せることが往々にして起るが、キリストの場合は、passioは感覚能力の領分にとどまり、決して理性の領域に踏みこむことはなかった。
28巻P203
パトスなき状態アパティア
情念を理性が完全に支配する状態エウパティア
28巻P203
全ての情念から解放されて安心の境地に到達しているのが知者である。
貪欲の代わりにただ真のみを求める【意志】
享楽の代わりにただ真の前の認識のみを喜びとする【悦楽】
見える善の喪失と見えない悪の到来を恐れる恐怖の代わりにただ真の善のみを受け入れようとする【慎重】がある
28巻P206
悲しみが感情の度を越えて理性を惑乱するに至ることはなかった。真の人間であるキリストのうちには受難における苦しみも悲しみも最高度に存在したのである。それにも関わらずその感情は惑乱に至ることがなかった。
26巻P207
なすべきことを知りながらなさないのが罪。
したくてもできない状態に束縛されている状態、即ち自由を奪われている状態が罰。
(知るとは何かという問題もある。つくづく知れば為すかもしれないし)
(悲しみにさいなまれている人間がなすべきことをなせないのは罪なのか罰なのか分からない)
28巻P208
人類が犯した神に対する罪に対する罰としての悪であった。その罰の悪をキリストは人類の身代わりとなって引き受けた。すなわち罪の悪を自ら犯すことなしに、その悪に相応する罰の悪を人々の代わりに引き受けたのである。この罰の結果として彼は悲しんだ。
28巻P210
キリストが悲しんだのは、自分の罪のためではなく、人類の罪の償いとして、人類の受けるべき罰の悪を引き受け、そのた めに苦しみ、悲しんだのである。だからその「悲しみ」を病的とか罪深いとかいうのは見当外れである。何故そのような仕事を引き受けたかといえば、それが父なる神の意志であり、その意志をこの世において実現することが、神の子としてのキリス トの目的だったからである。しかしそのために人間と成ったキリストは、人間である限りにおいては、普通の人間と同じように、いやなことはいやであり、人間並みに、できれば避けたかった。しかし神の子として、最後には神の意志に従い、神 の意志を自分の意志とした。その意味で「悲しみ」に対するキリストの意志は、単純でなかった。このことを、キリストのゲ ッセマニにおける祈りが示している。「父よ、できることなら、この杯をわたしから過ぎ去らせてください。しかし、わたしの 願いどおりではなく、御心のままに」(『マタイ伝』第二六章三九節)。(第三異論答)。
(つくづく知れば為すかもしれない。だが有限なる存在の知る力など無限には及ばない。無限なる存在の力を思い知らせると解釈することもできる)
28巻P211
2つの意志の葛藤
この葛藤あるが故にキリストの受難と死とは最大の価値を有する
28巻P217 恐れについて
たとえば、現実に何らかの悪が迫ってきているとしても、それに魂が気が付かず、「迫りつつある」悪として、 把えられない限り、それは、「恐れ」の情念を起さない。逆に、じっさいにはそのような悪は迫っていないにもかかわらず、 魂がそのような悪を想像し、それによって情念を起すとすれば、それは「恐れ」の情念となる。またそれが現在すると想像す る場合には、「悲しみ」の情念となる。
そのことが、未来に起る悪であるとしても、その到来が、絶対に確実だと把えられた場合には、その悪は、じっさいの時間においては、まだ現在的でない未来の悪であっても、絶対確実だと確信したその人にとっては、未来ではなく、現在 て把えられた悪となる。したがってその人にとって、その悪はもはや「恐れ」の対象ではなく、ただ「悲しみ」の対象となる 。 たとえば、或る囚人が死刑を宣告されて、その日の午後に執行されることが確実となった時、その死の時にはまだ間があり、 その意味で未来的な悪であるとしても、確実に死ぬと覚悟をきめたその人にとっては、それは現在的に把えられた悪となり、 一切の希望は消滅し、「恐れ」も消滅し、ただ「悲しみ」の情念だけとなるであろう。
実際に恐れている魂は当然悲しんでもいるのである。トマスはその理由を説明して恐れの対象たる捉えられた未来の悪は、それ自体として悲しみを生ぜしめるものであるからだという。
28巻P218 恐れについて
恐れはキリストも有していた。キリストは真実の人間であるから普通の人間と全く同じ身体を持ち、身体の傷害と死とを自然本性的に恐れたのである。
神の子としてのキリストは神との合一の恵によって地上の存在においても自分とその周辺に起こる救済にかかる出来事を現実に起こる以前に確実に知っていた。
だからそれについて恐れの情念は起こりえなかった。ただ人間としての悲しみの情念のみがあった。その意味に置いてキリストのうちには恐れの情念はなかったと言わなければならない。
にもかかわらず人間キリストは人間らしく人間の本性においては死を恐れた。人間キリストのうちには人間としての自然本能的とも言うべき恐れと神の子としての自覚における恐れなき悲しみとか共存した。両者の共存と壮絶な闘争がゲッセマネの祈りのうちに実現した。
28巻P220
理性による度を越えて、度外れに激しくなった恐れ、キリストはそのような恐れには至らない。
28巻P220
ただキリストだけは、神の子として原罪に服さないから、原罪は彼にとって死の第一原因ではないように、恐れの第一原因でもない。彼は必然によってではなく、自らの意志によって、人間本性を引き受けた。その意味において、死をも自由を以て引き受けた。だから死に対する「恐れ」は、彼の自由との関係においては、普通の人間と同じ意味では存在しない。
28巻P221
受肉以後の場合とに区別して考察する。まず、(一)受肉以前のキリストの立場から考えてみると、それは神性の力によって、未来に起りうるいかなる悪をも避けることができたであろう。したがって、「恐れ」もなしにありえたであろう。それは、異論のいう通りである。しかし彼は、自らの意志によって、肉を取り、人間キリストと成った。そこでこの
(二)受肉以後のキリストについて考えてみると、彼は肉を取った以上、普通の人間の有する肉と全く同じ「肉の弱さ」を負わなければならない。その弱さのゆえに受けるべき悪は、普通の人間にとっては、自分たちの犯した罪に対する悪 として「罪の悪」であり、またその罪に対する当然の罰として「罰の悪」であり、かかる悪の酬いとして不可避なのであるが、人間キリストにとっては、それは自分ではなく他人の犯した罪の悪であり、その罰は、他人の犯した悪に対する身代りの「罰」の悪である。にもかかわらず彼は、それらの悪を引き受けた。引き受けたのは彼の自由意志によるが、引き受けた以上、 それは肉の弱さのゆえに、彼にとって不可避なもの、あるいは容易に避けることのできないものとなった。死に対する「恐れ」もまた不可避なものとなった。
——最後に、何故彼はこのような不可避の悪を受けるべき道を、あえて自由に選んだかと問われるならば、それは人類救済の目的のためであったと答えられるであろう。(第三異論答)。
28巻P224 驚きについて
「恐 れ」と「驚き」との間には、共通点と相違点とがある。まず共通する点についていえば、いずれも、何か異常なことが起って、それによって、心がひどく動揺せしめられた状態だということである。しかし、両者の間には、次のような相違点がみとめら れる。
(一)「恐れ」の対象は未来的であり、それが恐れの対象として把えられ、また間近に迫りつつあると把えられる時に、 魂の感受する情念であり、それが現在的になる時、「悲しみ」の情念に転化する。これに対し、「驚き」の対象の方は、それが現在的と成るまで、全然予知されておら ず、 現在的になった時にはじめて魂の受ける動揺であって、その時始めて、「これは 何だ」という問いが始まる。
(二)「 恐れ」の対象は、それを知る人にとって、始めから 知られる。悪いものとして知られており、できれ ば避けたいと 熱望しながら、それができずに迫るにまかせる間、「恐れ」として続く。「恐れ」が実現されると同時に、それは 止み、「悲しみ」の情念に代る。これに対し、「驚き」の対象は、その対象が実現するまで予知されておらず、その実現ととも に、突然に知られ、対象の善悪も、その実現の後に知られる。
28巻P232
大きなことは実は全て虚仮威しであって驚きに値しない。真に驚くべきことは思いがけない人々のうちに真の信仰を見出すことである。一般の人々には軽んじられ無視されている小さな人々に思いがけず神から注がれてる恵としてのを信仰を見出す時、これこそは人々が真に驚くべきことである。そのことをキリストは身をもって示された。
28巻P233
キリストは驚いたふりをしたのではなく真に驚いたのである。真に驚嘆することによって人々の驚嘆すべき在り方の模範となったのである
28巻 P 234
神のように無から有を創造することはできなかった。すなわち、神のように全能ではなかった。その制限のもとに、キリス トは神の力のもとに、被造界においてなしうる「すべて」をなすことができた。したがって被造界において起りうるいかに偉大なことも、キリストは為しえたのであり、それは「驚き」の対象とはなりえなかった。その意味で、異論のいう通り、キリ ストには、「驚き」は存在しなかった。ただしそれは神から受けた神の力による限り、という観点からいえることである。
しかし、(二)人間性の側面から考えてみるとキリストは真の人間であり、その限りにおいては物質的肉体的制約のもとにあり、経験知によって生活していたから、知における進歩があり、無知もありえた。そこに「驚き」の成立する可能性もありえた。しかしもし欲するならば、この次元においてもキリストは、神の力を発揮して、経験知では理解できない出来事も 為しえたであろう。事実キリストは経験的生活において進歩しながら、時々その生活を超えた業(驚くべき業「ミラクル」) も為したのである。にもかかわらず日常生活においては普通の人間と同様、無知であり「驚き」もした。
なぜこの よう な経験の次元にとどまって「驚き」もしたのかと、その理由を問われるならば、それは真に驚くべきことを知らない人間に人間として真に驚くべきことを自らの模範を示すことによって、人々に教えるためだったと答えられるであろう。 これは既に十分に述べられた如くである(第三異論答)。
28巻 P 241怒りについて
怒りとは自分に危害を加えたそのものに仕返しをすることによってその悲しみを払いのけようとする欲求、つまり恨みを晴らそうとする心として生じてくる。その意味で怒りは加えられた悲しみとそれに対する仕返しの欲望とから複合された情念である。複合されたと言っても怒りの情念がその二要素からなるということではなく、この二つを原因としてそこから結果として生じてくる情念だということである。その意味で怒りは悲しみの結果であると言われる。
28巻 P 241
怒りは道徳的見地から見て善か悪か。
1つは仕返しが理性にかなっているか否かである。理に反している場合は悪徳による怒りと言われる。理性にかなって正義を愛する熱心に基づくものである場合は熱心による怒りと言われる。
もう一つの基準は怒りの度合いによる。善い怒りであっても度を超えて激しくなったり、逆に冷たくなったりする場合は悪い怒りとなる。
28巻 P 244
「怒り」には、「悪徳による怒り」と「熱心による怒り」とがある (グレゴリウス)。前者は精神の目を暗くし後者はそれを動揺させる。しかるにキリストの精神の目は暗くされることなく動揺することもない。ゆえにキリストのうちには怒りはなかった異論
――これに対して、まず、「われわれの場合」と「キリストの場合」 とを区別する。(一) 「われわれ」普通の人間の場合は、魂の諸部分は相互に関係づけられながら統一されている。それゆえ、或る能力のはたらきが異常に強まる と、他方のはたらきはその影響を受けて妨害される。そこで、感覚能力に属する「怒り」の情念が異常に強まると、「理性」 のはたらきである観想がその影響を受けて、多かれ少なかれ動揺することが起る。以上、普通の人間の場合は、異論のいう通 りである。
ところが、(二) 「キリストの場合」は別様である。人間キリストにおいては、「神性」と「人性」とが特別の仕方で結合しているように、その人間としての本性の諸能力、すなわち、理性と感覚能力も、神の力による節度のもとに、緊密に連絡しながら、それぞれ独自のはたらき を、他の部分からの妨害を受けることなしに存分に発揮できるようにされている。それゆえ情念の部分に属する 「怒り」のはたらきがいかに激しく燃えようとも、理性のはたらきである観想には、いささかの動揺も起きない。逆に、その理性の観想のよろこびがいかに大きくても、それによって肉体の苦痛が和らげられることは決してない。それゆえ、キリストにおいては、精神の観想のよろこびに満たされながら、怒りの情念が激しく燃え上ることもありえ たのである。異論は、普通の人間の場合には妥当する魂の諸能力のはたらきの関係を、人間キリストの場合にそのまま適用しようとした点で誤った(第三異論答)。
28巻P253
人間の究極目的である至福は精神が神を見ることにおいて根源的かつ固有的に成立するのであるから、この世に置いて既に神を見ていたキリストはその意味ですでに至福であったと言ってよい。しかし人間キリストは単なる魂ではなく身体でもあるから、その身体に置いても相応する完成に達するのでなければ人間として完全な至福に達したとは言えない。その完全な至福に到達するのは復活においてである。
28巻P254 アリストテレスとトマスの幸福感の違い、幸福と至福
アリストテレスは「幸福」について最高善についての人間の魂の最高部分である「理性」 の最高の活動としての「観想」であるということに帰するであろう。この最高善を「神」、魂の最高部分たる「ヌース」を 「精神」、その活動を「見る」といいかえるならば、「神を見る」を 「至福」とするトマスの思想に通じることは明 らかである。 問題は、この目的のために、根源的ではないが第二次的に、「外的な善」をも必要とするといわれる箇所である(第一巻八 章一〇九九三一以下)。
アリストテレスはここで、「幸福」は根原的に理性の活動において成り立つことを認めながらも、そ の活動が順調に促進されるためには、外的善が「道具として」要求されるといい、その例として友人、財産、政治権力をあげ、個人的には、生まれが良く、容姿が美しく、子宝に恵まれていることが助けとなり、逆に、容姿が醜くく、素性が賤しく、孤 独であることなどは、幸福の完成を妨げるといっている。ここから明らかとなることは、アリストテレスが「真理の観想」こそは幸福だといっても、それは、この世において実現されるべきものであり、そのためにこそ、いわゆる「恵まれた環境」 を前提とし、貧困や卑臓に生まれついた者にとっては全く縁のない、貴族的富裕階級の幸福だということである。
ではトマス自身は、至福と外的な善との関係を、どのように考えているであろうか。彼は、「スンマ」第二ー一部の至福論 において、特に第四間において、「至福のために必要とされることがら」について論じている。そのうち三つの項が、至福と 物体(身体を含む)との関係についての考察にあてられる。その中で、特に只今の問題と関係が深いのは、第七項「至福のためには何らかの外的な善が必要とされるか」である。
そこでトマスは、至補を、不完全なものと完全なものとに区別する。不完全な至福は、この世で得られるものであって、至福というよりは【幸福】felicitas というべきものである。アリストテレスが論じているのはそれである。この幸福に関する限 り、その本質は「真理の観想」だといっても、それが実現されるためには、いろいろな物質的条件が調わなければならない。
その意味で、「幸福の実現のためには(道具として)外的な善を必要とする」。その限りにおいて、まさにアリストテレスのいう通りである。ここまでは、アリストテレスの説は肯定される。 しかしながら、トマスがアリストテレス説を肯定するのは、ここまでである。完全な至福について語るとすれば、話は一変する。
【完全な至福】は、「神を見る」ことのうちに成り立つ。この至福についていえば、「このような外的な善は、全然必要とさ れない」。何故、このような相違が生じるのであろうか。それは、「至福」がそこにおいで成立する「場」の相違にもとづく。アリス トテレスが考えている「真理の観想」は、それ自体は世間を超越する超世間的性格のものであっても、その超世間的超越的観想が実現されるために、多くの物質的条件が、すなわち、能力や財産や余暇や奴隷が土台となって、その成立を支えていなければならない。それらの物質的条件を「道具として」超世間的真理の観想は成立する。トマスのことばによればアリストテレス的幸福は、「動物的生活」を場として初めて成立する。
これに対し【完全な至福】が成立するのは、復活の時である。「神を見る」が本当に実現するのは、この世ではなくて、すべての人間がいったん死んで魂と成り、再び肉を取ってよみがえる時である。その時、魂が再び受け取る身体は、もとの「物質 的身体」ではなく「霊的身体」である。「神を見る」が完全に実現する場は、アリストテレスにおけるような「動物的生活」 の場ではなく、「霊的生活」の場である。そこには、身分も権力も財産もない。この生活に生きるために、いかなる物質的善も必要ない。 だから、聖書の中で、天国においては、楽しい宴会や満ち足りた生活があるように記されているのは、すべて「比喩として 受け取られなければならない」。sunt metaphorice intelligenda ノーマスはいう。霊的なことがらを、物体的形象を用いて表現するのが、聖書の習わしだからである(第七項第一異論答)。
28巻P256
ではトマスにとって、完全な至福に到達した人間にとっては、ただ精神が「神を見る」だけで十分であり、それ以外の物質) 的条件は、一切不要であり、聖書における天国の描写は、善男善女をみちびくための方便としての比喩にすぎず、これを裏面) 目に受け取るのは、馬鹿げているのであろうか。完全な至福の境地においては、ただ精神の「神を見る」はたらきだけが重要 であり、物質的条件は一切消失するのであろうか。 トマスは、第四間七項においては、上述のように、「完全な至福のためには、外的な善は全然必要でない」といって「外的な善」の必要性を全面的に拒否しているが、それに先立つ第六項においては、それとはいくらか異な ことをいっているように思われる。すなわち、この項においては「完全な至福のためには、身体の何らかの完全性が必要であるか」と問うて、「必要である」と答えている。第七項と関係づけると、至福が完成するために は、「自分の外に在るいかなる物質的善 aliqua exteriora bona も必要でない」(七項)が、「人間としての私の一部である私の身体は、私の至福のために完全なものとなっていなければならない」(六項)というのである。それはいかにしてであるか。 第六項においてトマスはいう。復活の時、魂は身体を取ってよみがえるが、魂が最も完全な仕方で神を見ることができるた めに、その魂を受け取る身体は、それに適わしい最善の状態に調えられていなければならない。そのように調えられた身体に おいて、魂は最も完全にそのはたらきを実現できる。他面、そのようにして最高のはたらきに置かれた魂は、神の力を十分に 受け、その力は溢れて身体に及ぶ。かくて、復活した魂と身体とは、二重の関係によって、相互の完成に寄与する。すなわち、 身体は魂の活動に対して、「先行的に」に関係する。復活の時、魂を自分に受け容れる身体は、現在のわれわれ が所有しているような、死と腐敗にさらされた「地上の身体」ではなくて、不滅の「霊的身体」corpus spiritualeであり、栄光に輝く復活した魂を受け容れるのに適わしい。他面、それは「後続的に」 consequenter 関係する。すなわち、復活において神の光を直接に受け取る魂は、神の力と生命に溢れ、それは自分の外に溢れ出して霊的身体に注がれ、その身体を不滅の力 で完成する。このようにして、復活した人間においては、身体は先行的にも後続的にも、精神が「神を見る」はたらきに関わ り、完全に実現される至福の第二次的原因となる。すなわち、復活した人間における「霊的身体」は、精神において根原的に実現される至福に対して、それを完成するための道具 instrumentum の役割を演じながら、その身体を含む全体的人間の至福の完成に寄与する。 このようにして復活するすべての人間の先頭に現われるのは、栄光に輝く人間キリストであるが、その同じ人間キリストが、 現在の世界においては「旅人」として、われわれと苦難をともにして歩きながら、その精神においては既に「把握者」として、 神から直接に受ける「光」を以て、われわれの旅路を照らし、みちびいているのである。それが、「旅人であって把握者」なる人間キリストである。
28巻P257 キリストの魂と聖人の魂の違い
亡くなった聖人たちは、魂と身体とが分離した後、魂は天上に在り、身体は地上の墓に在る。魂は天上で神を見ているか ら「把握者」といわれるが、身体は地上に在るから「旅人」であるとはいわれない。ただ「把握者」といわれるだけである。そのように、人間キリストも、魂は天上の神を見ていたから「把握者」といわれるが、その身体が地上 に在ったからとて「旅人」といわれるべきではなく、ただ「把握者」といわれるべきである。「把握者であると同時に旅人で あった」といわれるのは間違いである(異論)。――これに対して、聖人たちにおける魂と身体との関係は、人間キリストに おける魂と身体との関係とは同じでないから、これを同じ論理(ラチオ)を以て論じるわけにはいかない、と答えられる。両 者の相違は、次の二つである。
第一の相違。——キリストの魂は身体と結合して、 この世 において受苦的passibilis と成った。これに対し、聖人の魂は、 死によって身体と分離すると、受苦性からも分離し、天に上って純粋に神を見る者、すなわち「純粋な把握者」 purus com- prehensor となった。他方、残から分離された身体の方は、純粋な土に戻り、魂とも無関係となり、したがって魂にとっての 受苦性の根原でもなくなった。だから聖人の魂は、ただ「把握者」であって「旅人」とはいわれない。
第二の相違。――キリストの身体は、魂に受苦性を与えたが、その魂は、その受苦性を引き受け、そのために苦しみの生 涯を送ることによって、人類の罪の償いを果し、結果的に、キリストの階罪の務めを果すために役立った。キリストの身体は、 魂にとって単なる重荷ではなく、却ってキリストを栄光の生にみちびくための何らかの務めを果した。その意味で、身体とと もに歩んだキリストの生涯は、栄光の生を目指す「旅人」の道となった。これに対し、魂から離れた聖人の身体は単なる物質 と成り、聖人の魂の栄光に寄与する何のはたらきもしない。だから聖人の魂から離れた身体は、その後の聖人の魂に、「旅人」 としての性格を与えない。その魂は純粋に「把握者」であるだけである(以上、第三異論答)。
25巻 P22
悪霊は、自分たちが人間のように肉体を有する者ではなく、純粋な雪的存在であることを以て、人間に自分たちの優越性を誇示し、人間を自分たちの前に拝させてきたのであるが、神 が肉を取って現われたので、自分たちの霊的存在を誇るべき理由を失った。これに引き続き、アウグスティヌスは「人間が可死であるのに自分たちは不死であることを以て、人間の前に威張っていたが、神の子が死んで可死であることを証明したので、不死を誇る理由も失った」といっている。要するに悪霊どもは、神の子の受肉によって、做慢の鼻をへし折られたのである。
25巻 P29
罪の許しは受肉の結果である。しかし唯一の結果ではない。受肉によって他の多くの結果が生じた。例えば悪霊の力が調伏されたこと、他に我々に知らない多くの結果が生じた。
25巻 P30
存在と本質を分けるのは「関わり≒存在 と そのもの≒本質 の両方を尊ぶ精神から来ている」と見ることもできる。
存在と本質がイコールであるのは神だけである。神には全ての関わりと全ての本質が備わっている。
32巻 P5
(四)についてはこう言うべきである。原罪は、起源 origo を通じて人間本性―――原罪は本来的にそれに関わっている――が伝達・共有されるかぎりにおいて、起源からしてとりついてくるのである。ところで、このことが起るのは母胎にやどった子供に理性的霊魂が注入されるanimatur ときである。したがって、理性的霊魂の注入 animatioの後においては、母胎にやどった子供が聖化されることに何の妨げもない。というのは、その後は母胎のうちに人間本性を受けとるためでなく、すでに受けている人間本性の何らかの完成のためにとどまっているからである。
32巻 P10
(四)についてはこう言うべきである。聖化 聖化 sanctificatio sanctificatio には二つの種類がある。
【その一つ】は、自然本性全体の聖化であり、それはすなわち、人間本性の全体が罪過と罪のすべての腐敗から解き放たれるかぎりにおいてである。そして、このことは復活において起るであろう。
これにたいして【もう一つ】は個人的なpersonalis 聖化である。この聖化は肉の交わりによって生まれる子供には伝わらない。なぜなら、このような聖化は肉に関わらず、精神に関わるものであるからである。したがって、たとえ至福なる乙女の両親が原罪の汚れから潔められていたとしても、それにも拘らず至福なる乙女は原罪の汚れを被ったのである。なぜならば、彼女は肉の欲情にもとづいて、 男と女の交わりからしてはらまれたからである。というのは、アウグスティヌスは「結婚と欲情について」において「肉の交わりから生まれるものはすべて罪の肉である」と述べているからである。