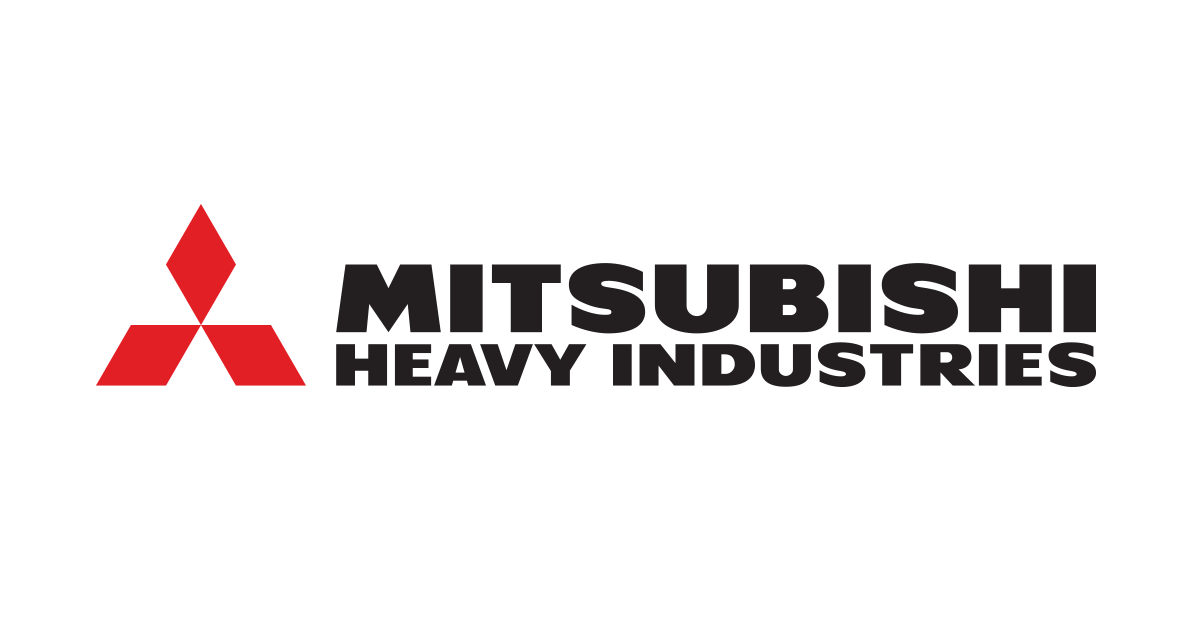脱炭素が叫ばれてるけど、サウジアラビアが水素事業に力を入れるというニュースがあった。
西村康稔経済産業大臣が、昨年12月にサウジアラビアを訪問。
グリーン水素エネルギー「循環型炭素経済」の協力で、輸送技術やCO²の回収などで協力する覚書を交わした。
水素の液化には、以前紹介した磁気冷凍技術による ‐253℃という冷凍技術が必要
スターリングエンジンという熱交換技術で、磁石の移動で熱交換する仕組み
輸送手段においても、川崎重工業が作る二重真空容器による液化水素をマイナス状態で保存する真空加工を施したタンクの輸送船開発を行なってる。
ハッキリ言って、水素輸送船を造るのは、無駄な投資なんだよね。
こちらは、メタン(CH⁴)から熱分離して水素と炭素を分けるという水素製造方法を岐阜大学が完成させてる。
水素を取り出した後のメタンの残留物として、純粋な炭素が残され、色々な用途に使用できる。
要は、石油を燃焼するとCO²が排出され、水素と合成するとメタンが生成できる。
水素は、水素単体では安定せず、液化する場合 -253℃の極低温の温度に冷やす必要性がある。
今は、磁石を使って熱交換の原理で簡単に冷やすことができるので、昔ほどのコストは掛からないが、水素は、金属の分子を通り抜ける性質を持っている。
川崎重工は、メタネーションを得意とし、メタンにして人工液化メタンガス(LNG)を作り、-161℃で液化するメタンの方が、水素を直接冷却して輸送するよりも安定しており、高温の炉で熱分解する事で水素と炭素に分解できる選択肢を考えないのか。
水素を何に活用するのかというのは、トヨタ自動車が開発した MIRAI のような燃料電池車のエネルギーとしてEUで活用するというもの。
メタンであれば、直接メタンを燃やすことで発電エネルギーを作り出せるし、水を電気分解して水素を作り、排ガスと混ぜ合わせると、メタネーションとしてCO²を再利用できる。
排ガスのCO²は、水素細菌と深い地中の圧で圧縮工程を利用して、CO²を餌として食べる水素細菌に食べさせることで、プラスチックの原料を作り出せる。
画像は、PR TIMESから引用
また、水素細菌自体が、人工肉としても食用にすることも可能。
メタネーションとして、石油少量を燃やした排ガスと水素を組み合わせてメタンを造り、安定したメタンを冷却した方が、輸送手段も既に確立されてるLNGタンカーで輸送できる。
コストも何十倍も安く済むし、メタンを熱分解する装置を世界中に輸出できるチャンスが広がる。
メタネーションは、川崎重工業が得意とするメタン製造技術。
つまり、水素輸送船を作るよりも何倍も効率が良い。
三菱重工が既に熱分離する装置へ開発として、米国企業へ投資を始めてる。
岐阜大学とモノリス社のどちらが優秀か?という産業開発競争になってる。
こういう風に考えると、CH⁴(メタン)として保存した方が、輸送手段や輸入先の用途において、火力発電用の燃料としても活用でき、燃料電池の燃料としても活用できるメタンの方が、管理がしやすい事が理解できる。
最終的に、水素細菌を使ったプラスチック原料やバイオ燃料に人工肉など、用途もそれぞれに分かれる
これだけ多くの産業に枝分かれするメタネーションという技術は、今後、日本が世界のイニシアティブをとる為にも、今、最も力を入れる産業分野だということ。