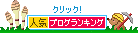1970年代前半のTVドラマには、エンタメとは程遠い、作家性の強い抽象的な作品が多くて、
特に視聴率に縛られる事のないNHKは、既成の価値観に捉われない、自由な発想のドラマを
数多く作っていました。その代表的な演出家が佐々木昭一郎で、「さすらい」「紅い花」
「四季・ユートピアノ」「川の流れはバイオリンの音~イタリア・ポー川」の4作が、
文化庁芸術祭ドラマ部門の大賞を受賞しています。
1976年に放送された「紅い花」は、シュールな画風で知られる、漫画家つげ義春が原作で、
インディーズ系のアングラ漫画雑誌「ガロ」の執筆者として、「フーテン」の永島慎二とともに、
学生運動が盛んな当時の反体制的な若者や、漫画は子供が読むものと馬鹿にしていた
インテリ層に、多大な影響と衝撃を与えました。
「紅い花」
最近、このTVドラマ化された「紅い花」を、YouTubeで偶々見つけて、42年ぶりに観る機会を
得ましたが、かなりの場面が記憶から抜け落ちていただけでなく、挿入歌に使われていた
ドノバンの「リバーソング」を気に入って、何度もリピートしていたはずのに、今聴き直すと、
ザ・ドアーズの「ジ・エンド」に似ていたことが初めて分かり、年齢を重ねることによって、
多種多様な情報が蓄積されることで、曖昧な記憶は再構築されていくものなんだと、
理解したのでした。
つげ義春は、1987年の「別離」を最後に、漫画を描いていませんが、山下裕二等との
共著「つげ義春 夢と旅の世界」(新潮社刊)と一連の作品が評価されて、昨年の日本漫画
協会賞のコミック部門で大賞を受賞して、久々に注目されています。
ただ、ポエトリーな「紅い花」や「古本と少女」とは対照的な、「ねじ式」や「ゲンセンカン主人」の
陰惨な悪夢の世界が、今の若者の感性に訴求できるか(または発信できるか)は甚だ疑問で、
今後も、大衆に嫌悪する似非評論家や文化人等に、芸術の名のもとに、マニアックな枠の中に
閉じ込められて、弄ばれる事になるのでしょう。
「ねじ式」 「ゲンセンカン主人」
 |
つげ義春コレクション 全9巻セット
8,057円
Amazon |