ひさしぶりの時代小説/闇の梯子
闇の梯子
藤沢周平
- 闇の梯子 (文春文庫)/藤沢 周平

- ¥500
- Amazon.co.jp
図書館の放出本で入手。
最近こういう本を読んでなかったのでするすると読めてしまいました。
初期短篇集で、下町の大工が子供を拾って育て始める「父(ちゃん)と呼べ」
独立したばかりの彫職人の妻が病気に。周囲の不穏な人々。そして妻のためにご禁制の品に手を出し始める「闇の階段」
過去に女給として売られた娘。その娘が仕切っている店にあるひ父がやってくるという「入墨」
など5つの短篇。
初期の藤沢周平は暗いと聞いていましたが、暗さよりは、エピローグが見えたところで物語を終わらすような終わり方が印象的でした。
とくに「闇の階段」は、最後の諦念の様子が暗いといえば暗いですが、むしろその覚悟に冬の寒風のような寂しさを感じてしまいます。
こういう味わいは、これはまたこれで貴重です。
しかし江戸時代の人の不幸を慮るというのは、なんというかそれだけ遠回りをしないといけない屈託があるということなんでしょうか。
博愛が人を救う理由/らも 中島らもとの35年
らも 中島らもとの35年
中島美代子
- らも―中島らもとの三十五年/中島 美代子

- ¥1,470
- Amazon.co.jp
中島らも、という人は著作からも分かるように薬もやったりして、当然常識的な素行をするようなかたではありませんが、面白い作家でした。
そんな作家の妻は、作品にも出てきてなかなか変わった人で、興味があって読んでみました。
これが、神戸の土地持ちのお嬢様、ということでかなり自由に育てられて、ある意味中島らもを超えた人物です。
破綻を起こしかねない博愛的な心情(らもがTVスタッフを家に連れてきて、らもが女の子と寝ている間、いっしょにきた男のスタッフがかわいそうになり寝ちゃうとか)は、らもとの相乗効果で中島家に混沌を招き入れるのですが、最初の最初、らもが高校生のころ、この人に惚れたのはやっぱりその博愛にあったんじゃないかと思います。
らもとの初めてのキスシーンからすでに彼女らしい。
突然、ものすごく真剣ならもの顔が近づいてきて、「ブチュッ」地う感じで私の唇はふさがれた。短いキスだった。
「ごめん」
らもは、私の目をのぞき込んだ。少女漫画の登場人物のように目がキラキラして美しかった。
無邪気にも私は、うっかり口をすべらした。
「ううん。そんなことないよ。私、誰とでもキスするから」
私には、中学のときから恋人がいた。キスも、セックスも、私にとっては相手が望めば応えるもの、一つのコミュニケーションのようなもでしかなくて、それほど大きな意味のあるものではなかった。
「悲しいこと言うね」
私の言葉を聞いたらもは、ひどくショックをうけたようだった。たちまち顔が曇る。らもがあまりにも哀しそうで、さびしそうだったから、私は胸を衝かれた。
「あ、ダメだわ。私がちゃんとしないと、らもは、死んでしまうんじゃないか」
私にそう思わせるほどらもの表情は真剣だった。私は真面目に考えないと、らもはきっと絶望してつぶれてしまう。
私は、この瞬間、らもに恋した。そしてそのときから34年間を共に過ごすことになる。
後年成功から分かるように、結局こんなややこしい人とやっていけるのは、こういう人じゃないといけないんでしょうね。選んでではなく、湧き出るような優しさを持っている人。
しかしどんなにらもが売れても、妻にとって一番大事なのは、らもとの愛だったというのは、「バンド・オブ・ザ・ナイト」的なヒッピー的時代を招くほどの無茶無茶な生活を送っておきながらも普通すぎて、そのバランス感覚は常識では図れません。
らもさん大好き、の人から評判の悪い本ですが、むしろこういう人が家庭にいたからこそ、なんとか底のある人生が中島らもも送れたんじゃないかなぁ、と思います。
しかしあらためて、中島らもの混乱した人生はなんだったんでしょうね。
物語のにおい/水辺にて
水辺にて
- 水辺にて―on the water/off the water/梨木 香歩

- ¥1,470
- Amazon.co.jp
筆者の水辺をめぐるエッセイ。
この作家、このエッセイを読む限り、日常生活に常に物語のにおいを感じます。
風景を見て自分の中の物語が動き出し、その物語に深く感応していく様子は、まさにナチュラル・ボーン・作家。
その風景をじっくりと見ていく様子は、他の作家にはない独特の、自分の周りにゆっくりと霧が立ち込めるように、風景が描写されていきます(とはいってもなんか恩田陸の『恐怖の報酬』日記 を思い出しました)。
留学先のイギリス北部の海岸や湿地帯の様子や、たぶん琵琶湖近くの湖のカヌーから見た風景。
そう、この人カヌーに乗っているんです。
カヌーに乗る人のエッセイは野田知佑 以来初めてですね。
しかも決してアウトドア、というわけでもないのに(たぶん)カヌーを愛してしまっているのはいいなぁ、と思っていら猛烈にまたカヌー熱が高まって参りました。
表紙の写真、いいなぁ、と思っていたらやっぱりの
星野道夫 。
ああ、公式サイト もあるんですね。
本の中ででてきた、星野道夫もあこがれていたと
いうドイツ製クレッパー社のカヌー、40万とかする
んですね。
ちなみに梨木氏はボイジャー 。表紙の写真のもの
でしょうか。かっこいいですね。
メーカー希望小売価格:\228,000 (送料別)だそう
です。
まだ高いな、といいエッセイを読んだのに、久しぶり
に物欲にまみれてしまいました。
エッセイの独特のスピード感は最初は読む人を選ぶかもしれませんが、じっくりと腰をすえるとこの人でしか書けない世界が広がっていきます。
ただいくつかは密度が高く、いくつかは低いといった感じで、これはきっともっといいエッセイがあるのではと踏んでいます。
さて次は何を読もう。
読む野球/日本野球25人 私のベストゲーム
日本野球25人 私のベストゲーム
Number
- 日本野球25人私のベストゲーム (25th Anniversary Sports Graphic Number 創刊25周年記念出版)
- ¥1,950
- Amazon.co.jp

- 日本野球25人私のベストゲーム (文春文庫PLUS 70-9)

- ¥650
- Amazon.co.jp
スポーツ雑誌ナンバーの25周年を記念して、1980年以降のベストゲームを著名な野球選手に聞いたものです。
出てくるのは、
長嶋茂雄、王貞治、野村克也、星野仙一、イチロー、清原和博、掛布雅之、原辰徳、ランディー・バース、ラルフ・ブライアント、秋山幸二、落合博満、新庄剛志、古田敦也、松井秀喜、野茂英雄、山田久志、江川卓、斎藤雅樹、阿波野秀幸、桑田真澄、佐々木主浩、工藤公康、松坂大輔、江夏豊、西本幸雄と江川の21球。
となります。
どれもしっかりかかれているんですが、個人的に面白かったのは、バース、秋山、斎藤、松坂、西本、でしょうか。
バースのベストゲームは、1985年、4/17の阪神巨人戦。例のバース・掛布・岡田の3連続ホームランの試合です。
「それがね、あれだけいいストレートを投げていた槙原が、何を思ったのかチェンジアップとスライダーを投げ出したんだ。これが見事に棒球でね(笑)。本人は決めているつもりなんだろうけど、球が高め高めにに浮いてストライクゾーンに入ってくるんだよ。だからカケ(掛布)と『俺にもあの球、投げてくれへんかな』って笑ってたんだ」
決め球が棒球になっていることを、ピッチャーが分からないこともあるんですね。
斎藤は、エピソード的にはたいしたことないんですが、コラムの「スポーツを数字で読む」で見事にこの20年間の先発で1位を獲得しているのに
「僕は現役のとき普段から特に何かをやっていたわけじゃない、コーチのいうように練習していただけで、自分で何かを勉強したりはしない選手だったんです」
という、イチローが聞いたら怒り出すようなことをさらっと言っています。
他にも、秋山の最良のタイミングを図っていたバク中。
実は自分の理想の球が高校時代の球で、プロになってもそれを追い求めていた松坂。
選手采配なんていくら考えてもそのいくつかしか実らない、西本の裏江夏の21球。
どのエピソードも、緊張の大勝負と人間味あふれるエピソードがいっぱいでした。
こういったものをサッカーでもやって欲しいのですが、そういったジャーナリスティックな部分は、野球に一日の長がありますね。
それから関係がありませんが、オリンピックサッカーアルゼンチン代表男子、ブラジルに勝ちましたね。
リケルメを大舞台でみるのもこれで最後になる可能性があると思ってみてましたが、いやぁ、どいつもこいつも日本代表とは同年代がやっているとは思えない差がありましたね。
センタリングのスピードの違いに驚きました。日本人のFKよりスピードが速いんじゃないですかね。
あと安易な場所では絶対にボールを相手に取られる、ということはありませんでしたね。
まだ1試合、見れるのが楽しみです。
歴史は生きている/自壊する帝国
自壊する帝国
佐藤優
- 自壊する帝国/佐藤 優

- ¥1,680
- Amazon.co.jp
怪人、佐藤優のロシアでの新人時代の見聞から、ソ連の崩壊を語る作品です。
もとより国家公務員の枠には入りきらない人物ですが、逆に国家公務員という枠もその大きさと深さは人を魅了するものがあるようです。
もともと東欧のキリスト教の勉強ができるという理由で入省するのですが、あっけなくもくろみは外れて外務省のロシアの公務員として、みっちり教育されていきます。
そんななかでロシアの優秀な人間に出会いながら刺激を受け、勉強をしながら給料をもらっている日本のために働き、我々の知っている佐藤優という人間が形成されていきます。
ロシアで出会った優秀な人間が、大学に残らず「今このときにしかできないこと」として革命を目指し、実際に革命を引き起こしていくのですが、最後には革命から離れていってしまうなど、歴史の激動期に優秀な人間がどう巻き込まれテイクかというのが分かり、なかなかの興奮でした。
個人的に印象深いのは、友人との会話の中で本当の創造とはどういうものなのか、ということについて語ったとき「マルクスのように人の価値観を一変させるようなものを作り出すことで、自分にはそのような能力はない。ただ、そういったものを広めることはできる」というようなことをいっていたところでした。
そうか、革命家は創造的な仕事だったんですね。
自分の能力を、今しかできないできるかもわからない、人々に多くの影響を与えるものに投じる。
ある人々を魅了するのもわかるような気がしました。
結局この人の本が面白いのは、この人の体験でありその信念に基づいた行動です。
思想などには分かりづらいものがありますが、青春書としてある一定の魅力を持っていることは確かです。
ループを越えて/ナンバー9ドリーム
ナンバー9ドリーム
デイヴィッド・ミッシェル
- ナンバー9ドリーム (CREST BOOKS)/デイヴィッド・ミッチェル

- ¥2,940
- Amazon.co.jp
ブッカー賞3連続候補となった作家の作品です。
友人から薦められて(本をもらった)読み始めました。
あらすじは非常に入り組んでいるのですが、屋久島で暮らしていた詠爾(エイジ)が、まだあったことのない父を探すため「トウキョウ」で、弁護士事務所を出発点に様様な冒険・困難に巻き込まれる、という感じです。
最初の章から、弁護士事務所の入っていいるビルの前の喫茶店でどうやって入るかの夢想が3回ループします。
ま、いつもならこの時点で読むのをやめるところですが、なんせ友人に贈られた本なので、なんとか読み進めると、やっとのことでループ」を抜け、物語が進みはじめました。
凶悪組織の争いに巻き込まれたり、双子の妹がいたり、バイトは上野駅の遺失物保管所だったり、神風の潜水艦の話になったり、うなじの素敵な女性と知り合ったりととにかく色々な話がテンコ盛りです。
個人的には、最初の3ループさえ抜け出れば、あとは一気に楽しめました。
胃カメラが喉を通るときに一番しんどいのと同じですね。
久々のSF?だったので読みどころが分からない心配もありましたが杞憂でしたね。
ブッカー賞候補になるぐらいですからストーリーテリングは、SF探偵冒険ギャング恋愛私小説みたいな様々な要素を入れながら、それを咀嚼できるぐらいに読みやすいものに仕上がっています。
村上春樹の影響のことを言われていますが、どうなんでしょう。
大きくいうとそうなんでしょうが、寿司と鋤焼を同じ日本料理といってしまうようなもので、そういうのもどうかと思います。
あと、どーでもいいことなのかもしれませんが、ま、結構都合がいい小説で主人公も小説を通しての成長というのがあまり分かりませんでした。そんなものは気にすることではないかもしれませんが。結構ライトノベルに近いのかもしれません。
ま、でも自分の守備範囲外の本を面白く読めたのでよかったです。
すでに終わった物語/アヒルと鴨のコインロッカー
アヒルと鴨のコインロッカー
伊坂幸太郎
- アヒルと鴨のコインロッカー (創元推理文庫)/伊坂 幸太郎

- ¥680
- Amazon.co.jp
引っ越したアパートの隣人の物語に途中参加させられた主人公と、その隣人の物語のメインだった女性の物語がパラレルに進むミステリライクな小説です。
他の伊坂幸太郎の小説より物語が日常的で(大法螺やSFや超能力がない)でも事件(動物虐待)が起こる、という感じで比較的起伏が少なく「日常的なストーリーでミステリっぽくない今までにないミステリを書く」という命題があって書かれた小説、というような気がしました。
人物的な魅力は、感情がないような外見の肌の白い麗子さん、人のいいドルジ、美貌の男・河崎などいましたが伊坂流の必要以上に人物を書き込まないつくりになっていて、ぐっと引き込まれるまでにはいたりません。
小品佳作、という感じなので、伊坂ファンには楽しく読めますが、それほどファンではない人は読まなくてもいい作品でしょう。
ソフトカバーで読んだんですが、ソフトカバーの本のつくりはなんかよかったです。
ああ、これ映画化しているんですね。
AMAZONみると
>内容紹介
>恵比寿ガーデンシネマ邦画史上最長ロングラン記録達成(19週)
>恵比寿ガーデンシネマ初日興収邦画、歴代1位
>伊坂幸太郎原作「アヒルと鴨のコインロッカー」を、世界観・空気感はもとより、
>映像化困難と呼ばれたトリックを完全映像化!
とのこと。うーん。
- アヒルと鴨のコインロッカー
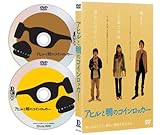
- ¥3,898
- Amazon.co.jp
パンクな仏像/古寺を訪ねて
土門拳
古寺を訪ねて
- 土門拳 古寺を訪ねて―奈良西ノ京から室生へ (小学館文庫)/土門 拳

- ¥880
- Amazon.co.jp
写真家として有名な土門拳。
そのライフワークともいえる、40年にわたって寺と仏像を紹介しつづけてきた「古寺巡礼」を含めた諸作品から、再編集して文庫本にした作品。
このシリーズは何冊出版されていますが、この巻は土門拳がもっとも愛したといわれる室生寺が掲載されています。
今回多分初めて「古寺巡礼」の一部に触れたと思うのですが、いやなんというか、パンクだなぁ、と思ってしまいました。
だって、顔も手もない仏像写真があって「いいなぁ」といっているんですよ。
なんだそりゃ、と思いつつ、でもかっこいいんですね、これが。
「顔がなかろうが,手がなかろうが、いいもんはいい」という感じで、これってパンクですよね(違うか・・・)。
「宗教的な意味合いで言うと・・・」「美術的見地から言うと・・・」といったものは関係なく、写真をみていいな、と思えるものが、結構あったのが驚きです。
精神性というより、その造形美で撮っているように思えました。
我々が衣服や鞄や自転車や車を買うときに、全体のフォルムや細部に注目して「かっこいい」と思う同じ目ですね。
これだけの大写真家も同じ目でみてるんだぁ、と勝手に思ってしまいました。
もちろん、写真として構図やタイミングのすばらしい写真も色々あります。
室行寺には、付近の人々の生活の変化まで分かるぐらい何十年も通いつづけたエピソードなども、写真だけではなくエッセイとしても十分面白く読めました。
機会があればほかもモノも「古寺巡礼」も読んでみたいと思います。
- 土門拳 古寺巡礼/土門 拳
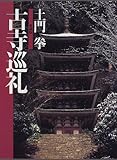
- ¥9,975
- Amazon.co.jp
池上流オーソドックス少年小説/ぼくのキャノン
ぼくのキャノン
池上永一
- ぼくのキャノン (文春文庫)/池上 永一
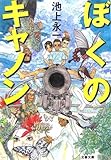
- ¥690
- Amazon.co.jp
エッセイを読んで、そうか根っからの小説家なのね、と気が付いて池上永一の小説が読みたくなったので読んだ作品。
沖縄のある村の物語。
大きな砲台のある村は、表ではノロであるオバァ、マカトが村を取りまとめ、裏では海人、樹王が目を凝らし、砲台を神様として暮らして暮らしてきました。
しかし、マカトの孫である元気イッパイの雄太、頭のいい博士、手癖のわるい美奈は、村の秘密を少しずつ知るようになります。
なぜ、入ってはいけない森があるのか。なぜ「キャノン様」のたたりがあるのか。樹王の陰とマカトの専制。村の潤い。そして村を狙うディベロッパーの存在。怪しい地質学者。
触れてはいけない謎を解いていくうちに、村は転換期を迎え、孫達が青年へと育っていきます。
本人も「自分が得意なのはキャラクター」といっているように、強烈なキャラクターが持ち味の作家ですが、今回はそれは控えめ。「沖縄」と「少年少女」というのを合わせて成長小説を書いてみました、という感じです。
悪くはありません。
愛と美であらゆる男達を意のままに操る村のアイドル「寿組」や、超金持ちで一度使ったのものはその場で何でも捨ててしまうという美女ディベロッパー、などは人間離れしたキャラクターで、なかなか面白いものでした。
今のテンペスト みたいな正統派の練習作品、みたいな気もしますが、それはそれでよし、作家として必要な作品として理解しましょう。
で物足りなさも含めて、やっと「レキオス」「シャングリラ」なんかの異色SF作品にチャレンジする気が湧いてきました。
楽しみです。
- テンペスト 上 若夏の巻/池上 永一
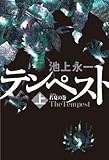
- ¥1,680
- Amazon.co.jp
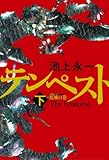
¥1,680
- Amazon.co.jp
レキオス (角川文庫)/池上 永一
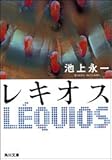
シャングリ・ラ/
池上 永一
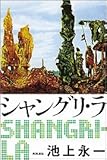
- ¥860
- Amazon.co.jp
- ¥1,995
- Amazon.co.jp
サ・ト・エ・リー/家日和
家日和
奥田英朗
- 家日和/奥田 英朗
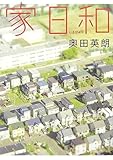
- ¥1,470
- Amazon.co.jp
いまだに録画はVHSしかない我が家ではTVはほとんどオンタイムで見ています。
といっても必ず見るのは朝のNHKのニュースぐらい。
しかし、最近はNHKBSの「週刊ブックレビュー 」を、ミーハー半分、参考半分で見るようにしています。
そうはいっても子供の邪魔が入り見れないことも多いのですが。
で2007年12月23日放送分でサトエリが推薦していた「家日和」
出演していた、桜庭一樹がファンの児玉清 ・ココでしか見ないけどそれもいい中江有里・よく知らない佐藤良明 ・ いくつかの作品が面白い嵐山光三郎 ・ もちろん佐藤江梨子、全員が「イイ」と誉めていたので、読んでみました。
いやぁ、イマイチでしたねぇ。
小説をあまり知らないうちにこんな本読んだら、小説は読まなくなりそうな気がします。
あ、もちろん個人視点ですよ。
なんか目新しいものが何にもないんですね。
以下あらすじネタバレ
●サニーデイ:インターネットオークションの出品にはまる主婦が夫婦喧嘩から夫のモノまで売りそうになって・・・
●ここが青山:主夫に目覚める話「じんかんいたるところにせいざんあり」
●家においでよ:別居した夫が自分の趣味に部屋を変え、なんとなくよりをもどす
●グレープフルーツ・モンスター:内職の管理をする若い社員に妄想を膨らませる主婦。香水が柑橘系なので。
●夫とカーテン:新興高層マンション群の乱立にカーテン・じゅうたん屋を開くため突然会社を辞める夫と家の危機を感じて才能が発揮されるイラストレータの妻
●妻と玄米御飯:N賞をとってベストセラー作家になった夫が急にロハスに目覚めた妻を胡散臭く見ながらそれをユーモア小説にしようか悩む話
ま、最後まで読ませるのは読ませます。あっというまに読めます。ワハハと笑って終わらせればいいのですが。
サトエリー、文化人気取るならもっといい本紹介してくれー、と思ってしまったのはないものねだりというものでしょうか。
サウスバウンド がよかったので、ほかも読んでみようと思ったのですが、判断が甘かったです。