麻雀を覚えたのは、小学3,4年くらいからだったと思います。親父と兄貴がやっていたので、それを見て覚えた感じ。当時(30年前!)はコタツのテーブル裏が緑色の麻雀マットのような生地で出来ており、コタツテーブルをひっくり返して親父と近所のおっちゃん達が集まって麻雀をやっていました。
その当時、同級生の家に遊びに行った時「パーマンドンジャラ」って子供向けの麻雀を模倣したゲームがあり、その山の積み込みが麻雀に比べプラスチック製でめっちゃ軽くてうまく積めず、下手くそーって笑われた記憶があります。(こんな軽いパイで積めるかっ!雀牌やったらお前らより上手く積むのにー、みたいな。)
中学になるまで気付かなかったんですが、4人の面子(メンツ)がいても3人で打つ、いわゆる「三麻(サンマ)」と呼ばれるやり方が親父らの主流だったようで、いつも萬子(マンズ)の二萬~八萬を抜いてやってました。(符計算とかちゃんとした計算が出来なかったので満貫以上が出やすいように3人打ちにしたようです)
そんなヘンテコな覚え方をしたからか、始めは「鳴き専門染め系」みたいな偏りまくった技だけ磨かれて行きましたね。配牌で筒子(ピンズ)か索子(ソウズ)かどっちに染めるかを決めて、後は一気に鳴きまくる素人麻雀です(笑)
中学生になって友達らと初めて4人打ちをやった時、萬子がいっぱいあってドキドキしましたね(笑)最初は4人打ちに慣れず(相変わらず混一色、清一色狙いばっかりだった為)全然勝てないは、対面の人からチーをしてしまい「トイチー!笑」とか大笑いされたり。
でもそのうち名作漫画の「ぎゅわんぶらあ自己中心派」にハマり、鳴き麻雀から「メンタンピン・ドラドラ・裏ドラ」の面前麻雀打ちに打ち方を変えました。特に初めて三色であがった時はめちゃめちゃウレシかったのを覚えています。
そういや、初めて友達の家に泊まりに行ったのって、中学2年の時で「徹夜麻雀(テツマン)」するためだったような。もう今時の子供達はテツマンなんか絶対にやらないだろうなー。その前に、麻雀をやらないか・・・。(PCでオンライン対戦とかやるのかな?)
うーーーん。
久しぶりに「ぎゅわんぶらあ自己中心派」読みたくなってきた(笑)
ぎゅわんぶらあ自己中心派 (1) (講談社漫画文庫)/片山 まさゆき
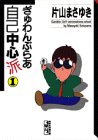
¥525
Amazon.co.jp