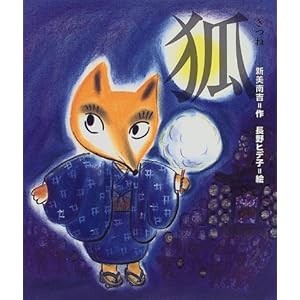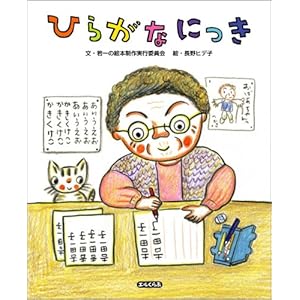☆『狐』 新見南吉作 長野ヒデ子絵 1999年 偕成社
東條:新見南吉の情緒的でどこか幻想的な世界を見事に描かれたこちらの『狐』は、俯瞰の視点でとらえた田舎や祭りの風景が、美しい夜の闇にぽっと浮かびあがります。
ほんのりとした月明かりや露店の灯りがそっと・・・読者をこの時代のこの場所へと誘いますね。
長野さん:ちょうど南吉生誕100年です。
南吉は生前3本の狐のはなしを書いています。有名な『ごんぎつね』、『てぶくろをかいに』、そしてこの『狐』です。
『狐』は全集(※「校定 新美南吉全集」(大日本図書))に収録されていたのを読んで初めて知った作品。
南吉が亡くなる直前の2か月前に書かれたもので、私には南吉18歳~20歳の頃に作った『ごんぎつね』と比較してみると・・・歳を重ね死を目前にした南吉の最後の万感の思いが、相当に込められているように感じられたのね。
それで、この作品について編集の方にお話しして、絵を描きました。
絵本にするには、文章を書く人と絵を描く人が同じ精神状態でないと、作品ができないという考えからです。
同じ場所で、感じてみたかった。

(※文六ちゃんの新しい下駄を買いに入った店で、どこかのお婆さんが「晩げに新しい下駄をおろすと狐がつく」と話しかけます。)
東條:子どもたちの「文六ちゃんは本当に狐にとりつかれたのではないか?」という緊張感が、帰りの夜道の空気を変えていきます。 得体のしれない恐怖感と不安なとまどいが、絵本からじわじわと伝わってきます。

(祭りの帰り道・・・「コン」と咳をした文六ちゃんを不気味に思う子どもたち。いつものように家まで送ってやることをしません。文六ちゃんが狐になったのではなかろうか!怖いから。)
長野さん:子どもたちってのんきに見えるけど、わりと一日に一回はなんとなく仲間はずれみたいなことになっちゃったりしてしょんぼりしたりすること、あるじゃない?
この作品ではそういった「集団の中の子ども」と、中盤から展開する文六ちゃんとお母さんの会話から感じられる「子どもの心情を受け止める理想の母親像」を描いたのね。
2大テーマです。
(家へ帰り布団の中で、「もし僕がほんとに狐になっちゃったらどうする?」と言う文六ちゃんに、お母さんは「父ちゃんと母ちゃんも狐になりますよ」と話します。「猟師の犬にみつかったら?」「母ちゃんは、びっこをひいてゆっくりいくよ。その間に逃げるんだよ。」)
東條:この作品を読んでもらった子どもは、最後やっぱり安心感に包まれた満足の表情をみせますね。
長野さん:子どもにも外でいろんな事がある。丁寧に子どもの話を聞いてあげることの大切さ、ね。
そして子どもをしっかり抱きしめてあげる。このことが不安を拭い去り、元気になって明日が迎えられる。そう思います。
☆『ひらがなにっき』 若一の絵本制作実行委員会文/長野ヒデ子絵 2008年 解放出版社
長野さん:この『ひらがなにっき』は特別なおばあちゃんのお話を描いたわけではないんです。学校へ行くことができない人が大勢いた、そういう時代だったのね。
お話のモデルである吉田一子さんも、そういった人のひとり。
一所懸命に働いて・・・お孫さんが生まれて。そのお孫さんが3歳の時「おばあちゃん、絵本を読んで」と持ってくるのだけれど、字が読めない。だから「目が悪いから読んであげられない」と答えるのね。
そのうちにそのお孫さんも大きくなって、学校に行くようになり本当のことがわかるようになると「おばあちゃんも僕と同じように字を習ったらいいよ」と言ってくれるのですね。
そこから吉田さんと文字との日々が始まるのです。
東條:識字教室で教わった文字を、「こぼれないように」ぎゅっとにぎりしめて家路を急ぐのですよね。
長野:文字を「愛おしい」と思う心、ですね。
東條:だからこそ、さまざまな場所で遭遇する汚い言葉や落書きに心を痛める。
自分は文字や言葉について、ないがしろにしてはいないだろうか…、私も、真摯な気持ちでこの場面を受け止めました。
長野:NHKの番組で吉田さんが取り上げられたときに、
「一番すきな字はなんですか?」というディレクターの質問に、吉田さんは「母」と答えていらっしゃった。
ご自分がまだ物心つかないうちに、お母さんは亡くなられているので、余計に想いがある文字なんだと思います。
その後その記者と私は、吉田さんが体を壊されたのでお見舞いに行ったのです。そのとき
「書きたいのにまだ書けない字、はありますか?」という私たちのの質問に、
「自分の子の名前が難しくて、まだ書けないのがくやしい」とおっしゃっていました。