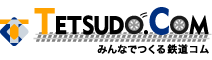かつて計画された貨物新幹線構想
今から20年近く前の2008年ころ、「東海道物流新幹線構想」なるものが計画された時期がありましたが、その計画自体は、車線拡幅の工事が行われていることで事実上計画は頓挫してしまいましたが、改めてこうした高速道路等を活用した貨物路線こそ、直轄高速などで活用させるべきでは無いかと思うわけです。
高速道路に敷設される貨物の新幹線
当時の計画では、在来線と同じゲージで最高速度も100km/h程度で計画されていました。
当時の構想は、下記のような構想でした。
- 新東名、新名神の中央分離帯や既着工の使用未確定車線などを活用する
- 環境にやさしく、大量輸送に適した、貨物専用・軌道系システムを導入する
- 自動運転、無人運転とする
- 複線電化(第三軌条集電方式)
であり、その諸元は
・運行距離 :約 600km(東京~大阪間)
・速度・所要時間:平均時速 90~100km、東京・大阪間 6 時間 30 分
・ターミナル箇所:東京、名古屋、大阪の 3 箇所のほか数箇所
・軌間 :狭軌(JR 等の在来線と同一)
・列車編成 :5 両 1 ユニットを複数連結、1 編成最大 25 両程度で、輸送需要によりフレキシブルに対応
・駆動方式 :動力分散駆動、急勾配区間はリニアモータによる支援システムを採用
となっています。
出典:東海道物流新幹線構想~ハイウェイトレイン~
当時の構想として非常に面白く、現在のトラック輸送による物流問題などを見越した考え方と言えるますが。いくつか技術的な点で困難では無いかと思ったのが下記の点でした。
複線電化(第三軌条集電方式)
ご存じの通り第3軌条方式とは、レールの横にサードレールと呼ばれる、レールを敷設し、サードレールと呼ばれるレールから集電しながら走るとしています。

画像 wikipedia
著作権の表示
Renaik - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0, リンクによる
メリットとデメリット
ここで、改めてメリットとデメリットと言いますか、問題点をいくつか最初に挙げてみたいと思います
まず最初は、サードレールの問題点として、下記の点が挙げられます。
- 第3軌条方式は、高速運転には向かない、けいはんな線では95km/hの最高速度で運転しているが、多くの地下鉄線内などで使用される場合75km/h程度が一般的である
- 表定速度は、85.6km程度は最低限必要 東京~大阪間を6時間30分で結ぶとなれば、かつての在来線特急こだまとほぼ同じであり、表定速度は85.6kmは最低必要になってくるわけで、最高速度が当時は110km/hであったことを考慮すると、全区間でその程度の速度を確保する必要がある
ちなみに表定速度というのは、停止状態から最高速度まで加速して、停止するまでの速度で目的地到着までの総所要時間で除したものであり、運転している時間だけを表したものではありません。
表定速度85.6km/hとなれば平均速度(運転中の速度だけを計算したもの)は停車時間にもよりますが90km/h以上で無いと達成できない数字になります。
あと、もう一点は、無人運転に関する点です。
無人運転による高速運転となるわけですが、障害物の検知などは問題ないのでしょうか。新交通システムなどでは遠隔による自動運転が行われているので、それに準じた考え方で有ったと思われますが、高速かつ重量貨物で有ることから、相当高度なセンサーなどで障害物検知を行うなどの必要があるように思えます。
次にメリットとして考慮される点は以下の通りです。
- 線路幅は狭軌としてあることで、在来線への直通も考慮されている
- 高速道路用地のみ活用部分を活用するので、新たな土地買収の手間が不要
- 動力分散方式による高加速・高減速が可能である
直轄方式の高速道路に貨物専用鉄道を敷設する
結果的には、自動車道の4車線⇒6車線工事が進み、この構想自体は頓挫してしまったわけですが、改めて現在のトラックによる2024年問題と呼ばれる改革により、トラックドライバーの減少は大きな問題となっていきます。
そこで、改めて現在の直轄高速道路区間などを中心に新たな構想で以下のような高速道路に併設される新幹線もしくは高速在来線(所謂スーパー特急方式)で貨物輸送及び旅客輸送が出来ないかと考えてみたわけです。
可能性として高いのは、現在直轄方式で建設されている高速道路などで最初から不採算ありきのため、片側1車線道路なども多く、将来的には2車線とするとしても人口減少などを考慮すれば、仮に2車線化してもそれだけの需要を作れるのかという五問も生じます、更には現在のローカル線問題もあり公共交通の確保も喫緊の課題となってきます。
そこで、未活用の用地を使って高速新線を在来線規格で採用する(新規に建設する路線なので、建築限界を見直して車輌高さの4100mmの制限を撤廃して、4800mm程度まで上げることで、現在の大型トラックの全高が3800mmですので、800mm車輪を採用して、1000mm程度の床面高さとなれば、20tトラックなどの大型車もそのまま輸送することが出来ることとなります。あくまでも仮の話ですが。
画像 wikipedia
Rs1421 - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0, リンクによる
問題は、現在の鉄道の建築限界
もちろん、新幹線の4500mmを更に300mmを越える車両限界というのを狭軌の幅で支えるのは曲線区間でのカント量の問題も考慮すれば問題となりますが、考え方としては面白いかもしれません。
むしろ、こうしたトラック輸送を専門で考える区間にあっては在来線との乗り入れを考慮する必要が無いので、標準軌とすることも可能では無いでしょうか。
こうした区間では、トラックは原則として鉄道輸送に委ねるということで、ドライバーは別に連結する客室で休憩を取るもしくは、別のトラックに乗り換えて戻ることも可能となると言えないでしょうか。
デメリットとしては、鉄道輸送分の上昇コストをどう捉えるか・・・・実際には全ての区間をトラックで走行した場合の燃料費や人件費、等を考慮すればトラックを鉄道輸送させることの対比でメリットがあると判断されれば十分な可能性はあると言えないでしょうか。
更に、この区間に旅客輸送を行うこととして、道の駅などと直結するもしくはSAとしての道の駅を設置して、阪急京都線の西山天王山駅のような、鉄道とバスの相互乗換が出来るような駅とすると言った柔軟な発想も有りではないだろうか。
実現可能性は低いが、このような思い切った発想が今の時代求められているような気がします。
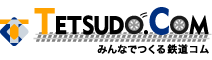

にほんブログ村