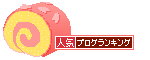母は、我が子を愛おしむ母性本能は働いていたが、もっと自分の思い通りの子が欲しいという気持ちは拭えなかった。
次女は、父に愛されていないことは知っていたが、母にも捨てられるような気がしていた。
母に置いていかれる夢を毎日見ていた。
家にいない母が恋しくて、母の服に残っている母の匂いを嗅いで寂しさを埋めようとしていた。
いつ帰ってくるかと、その音に耳をすませていた。
「匂い」と「口に入れるもの」に度々不快な思いをするようになった。
桃味の歯磨き粉が志村けんの味がするとか、ナポリタンが本の中で人を拘束している木のつるの味がするとか、ママレモンが火垂るの墓のお母さんの死体の臭いがするとか、想像の中で一度連結してしまうと、それが消えるまで数日掛かった。
自分の頭の中の想像が他者には理解されないということが分からず、祖父母に一生懸命説明して困らせていた。