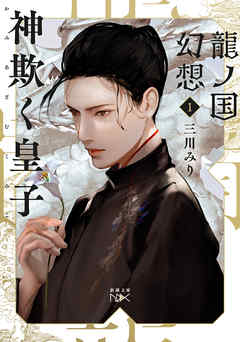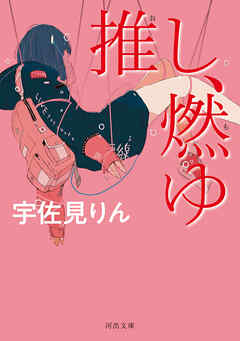この記事に書いた少年国主は懊悩があり、
部外者からは好きなことをして毎日を過ごしている印象になっており、
実態は『それしかできない』状態です。
宇佐見りん先生作「推し、燃ゆ」の主人公も、私は同じ印象を持ちました。
どちらの作品も、母親が日常的にダブルバインドを使っていて、
子供は知らず知らずのうちに「真綿で首を絞められる」ような息苦しさを感じ、それが言語化できるほどのハッキリした形を持たないため誰にも伝えられません。漠然とした苦しさの中で、親の機嫌をさほど損なわずにできることを探した結果、それをして過ごすしかなくなっています。
そうしてカサンドラ症候群のような症状に陥っています。
一方の母親はダブルバインドを使う自覚がなく子供に好きなことを「させてあげている」意識があるので、子供の苦しみや不安やそこはかとないもどかしかに気づかず、子供が親の意向に従わない「子供のわがまま」を言語化して周辺の人々に話します。
ダブルバインドがどのような状態を指すかといえば、
たとえば日頃から子供に刃物の危険性を説き使用を禁じたり制限する中で、親が寝込んだある日に「リンゴを食べたい、リンゴの皮を剥いて欲しい」と子供に伝えたらー
この場合、子供はどちらの要求に従えばよいか戸惑いを覚えるし、リンゴを用意してもしなくても親が叱る条件を満たします。
ところが一般的にありがちな親の対応は、
状況に応じて臨機応変に考えれば、今は病気の人のために刃物を使ってでもリンゴを食べさせてやることが優しさだとわかるであろう。いつもとは違うのだから、もうちょっと優しさを持てばいい。
このような子供の至らなさをあげつらい、子供の戸惑いなど知らずに親のわがままを正当化します。
本来ならば、最初にリンゴを所望した時点で親が丁寧な説明を行い、非日常のことを頭を下げて頼めば万事解決しますけれど、「子供の察しの悪さ」や「空気の読めなさ」を因果にします。そうしたら親はどれほどの月日を経ても、説明する必要を感じる機会はなく、機会がなければ変化もしません。自己都合の悪いことを他人のせいにするなんて、非常に容易なもの。
このような関係から、親がアンビバレントを起こすほどに子供は不安な日常が堆積すると共に、劣等感を埋め込まれ理由の判然としない脅迫観念が芽生えていきます。
アンビバレントとは二律背反や両面等価などに訳されまして、通俗的な表現方法では「いつも自分が正しい」状態を指します。
龍ノ国幻想では、作中に登場する他国の人物が母の不安定な言動を察して、臣下がたくさんいる前で一般的な概念が母にあることの確認を取ったので、少年はもどかしさを形に変えることができ母の実態を知りました。この母は臣下に説く国主崇拝から自分を別枠に置いて、母も臣下のフリをしつつ親の権利を振り回しており悪気はありません。
この話もそうやし、
自分が受けとめ受け入れる精神力がないことを棚上げして、定義や環境を変化させたら「ありのままの自分」で居続けられる前提があるみたい。
かような人は
「困っている人」と「困った人」のどちらのカテゴリーに該当しますか?