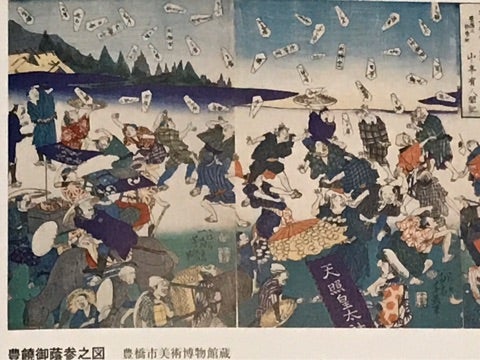石川県の能登半島先端 珠洲市(Suzu city)にて、
現代アートのトリエンナーレ、奥能登国際芸術祭が開幕しました.
1泊2日で巡ってきました.
2017.9.3.
1日目 オープニングツアーのバスにて巡りました
11:00〜11:30 開会式 @ ラポルトすず
総合ディレクター 北川フラムさんがアーティストを紹介
ラポルトすず内の作品を体験(100円でガチャポン)
11:40〜11:50
作品No.26 力五山(日本)
「潮流〜ガチャポン交換器」
12:05〜12:50 ランチ@珠洲ビーチホテル
12:55〜13:25 (2作品30分)
作品No14. @ 旧蛸島駅周辺
トビアス・レーベルガー (ドイツ)
「何か ほかにできる」
" Something Else is Possible
作品No.13 @ 旧蛸島駅
エコ・ヌグロホ (インドネシア)
「Bookmark of dried flowers」
<車移動10分>
13:35〜13:50 (15分)
作品No.10 @ 森腰の古民家
岩崎貴宏 (日本)
「小海の半島の旧家の大海」
2トンの塩!
<車移動33分>
14:23〜14:38 (15分)
作品No.7 @ 旧日置公民館
さわ ひらき (日本)
「魚話」
映像をじっくりと観ていると、珠洲の深層へと引っ張りこまれ、能登の風土に同化していく体感.
<車移動7分>
14:45〜15:12 (2作品27分)
作品No.4 @ 木の浦海岸
よしだ ぎょうこ + KINOURA MEETING (日本)
「海上のさいはて茶屋」
作品No.5 @ 木の浦海岸
アローラ&カルサディージャ
(アメリカ/キューバ/プエルトリコ)
「船首方向と航路」
<車移動23分>
<バス車窓からNo.3 深澤 孝史「神話の続き」>
15:35〜16:03 (28分)
作品No.1 @ 旧清水保育所
塩田 千春 (日本)
「時を運ぶ船」
揚げ浜式塩田(えんでん)の近くに展示された塩田(しおた)さんの作品. 塩づくりに使われた船に赤い糸が絡んで.
<車移動32分>
<バス車窓から
No.30 ラックス・メディア・コレクティブ「うつしみ」>
16:35〜16:45 (10分)
作品No.32 @旧鵜飼駅
アデル・アブデスメッド
(アルジェリア/フランス)
「ま・も・なく」
*
<車移動5分>
16:50〜17:10 (20分)
作品No. 33 @見附海岸
リュウ・ジャンファ (中国)
「 Drifting landscape 」
見附島の絶景の前に広がる漂着物のようなアート. ゴミのようで全て焼き物.
17:20 ラポルトすず
***オープニング・ツアーおわり***
宿泊先の木ノ浦ビレッジへ
予約していた「まつり御膳」に舌鼓
キリコ祭りで、自宅にお客様をお招きして振舞われるヨバレ.
木ノ浦ビレッジで働く地元のお母さんの手作り.
栗入りお赤飯、おすまし、煮付け、お刺身、茶碗蒸し、どれも美味しくて.
木ノ浦ビレッジに泊まるならば、予約して、是非味わってほしいごはん.
開幕初日にいただいたので、
ビレッジのブログに姪と一緒に載ってます.
***海辺のコテージで波音を聴きながら就寝***
2日目 乗用車をドライブし巡りました
8:00 朝食 @木ノ浦ビレッジ
9:15 出発
作品No.2 村尾かずこ「サザエハウス」
サザエの貝殻集めから制作まで3ヶ月かかったサザエハウスは、中に入ると瞑想できそうな心地よい空間.*
金剛崎〜ランプの宿を見下ろす絶景〜
*
須須神社を参拝
〜日本一の高さのキリコを保有する集落にある神社〜
作品No.12 バスラマ・コレクティブ「みんなの遊び場」
*
作品No.18 ひびの こずえ「スズズカ」
ふわふわドレスをまとい、クラゲのようにただよいながら鑑賞.
作品No.20 田中信行「触生ー原初」
作品No.27 河口 龍夫「小さな忘れもの美術館」
作品No.28 EAT & ART TARO「さいはてのキャバレー準備中」
展示内のカフェ(キャバレー準備中の賄いみたいな設定)にてランチ.
作品No.31 石川 直樹「混浴宇宙宝湯」
***16:30頃まで鑑賞し、金沢へ***
***
お土産は、
ハザ干し米と塩に、
ひびのこずえさんのゴジラタオル がお勧め!
珠洲では新米が実り、ハザ掛けして天日乾燥する風景がアート作品のそばに広がってます.
珠洲の「米」と「塩」をお土産にして、
塩むすびを食べながら旅の思い出を語るのも楽しい.
***
奥能登国際芸術祭は、2017-9-3から2017-10-22までの50日間開催
半島の最先端で、現代アートの最先端!