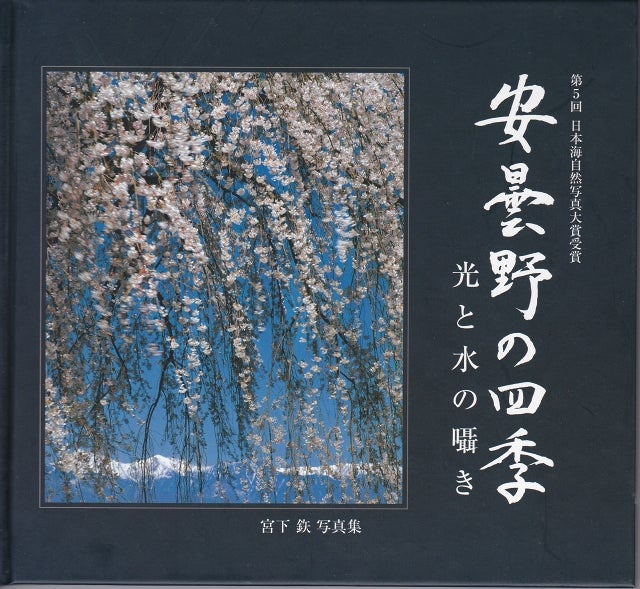三九郎の組立て
山形村の唐沢地区での三九郎の組立て風景です。ならだかな東斜面の農地で大人と子供たちが一緒になって三九郎を組み立てています。背景は美ケ原高原などの連山になります。
正月の間、玄関先を飾った松飾や飾り物、だるまなどを持ち寄って組み立てて行きます。高さは5mを超えているようです。最後にダルマを縄で一列に縛ったものを周りにぐるぐる巻いて仕上げるようです。
三九郎というのは松本を含む中信地域だけの呼び名で、他ではどんど焼き・どんどん焼き・どんと焼き・とんど焼き・左義長・鬼火焼き・道祖神祭りなど地方によって呼び名が変わりますが、正月明けから小正月にかけての松飾等のお焚き上げ行事として実施されているようです。以前は子供たちの行事として実施されていたようですが、今は親世代がほとんどを担っているようです。少子化で子供たちは忙しすぎるんでしょうか。
20250111撮影
同じく唐沢地区の別の場所の三九郎です。三九郎の完成形ですが、従来は大小2基を並べて親子に見立て、大きな方は大人が小さな方は子供たちが組み立てていたようですが、少子化の影響もあって今は1基になっているようです。
この地区のダルマは地元の「松本だるま」が目立ちました。太い眉に頬のまん丸いひげが特徴でユーモラスな顔になっています。高崎ダルマとの違いがよくわかります。
ダルマの他にお札が有りますが、よく見ると神社の御札とお寺のお札が混じっているようです。子供たちの書初めもあり、色々な願いが集まっているのだなと感じました。
Peace be with you !
ウクライナ・パレスチナ・ミャンマー・シリアに平和な日常が戻りますように!
≪写真集≫
![]() このたびは私のブログにご訪問いただきありがとうございます。
このたびは私のブログにご訪問いただきありがとうございます。
掲載している写真はノートリミング・フルフレームを基本としています。
掲載内容に誤りがありましたら、ぜひともご指摘願います。
≪掲載写真の著作権は筆者にありますので転用はご遠慮ください≫
よろしかったら下のランキングボタンを押してください。
ブログ掲載のモチベーションになりますので
どうぞよろしくお願いいたします。
↓↓↓↓↓ 作品に対する率直なコメントもお待ちしています。