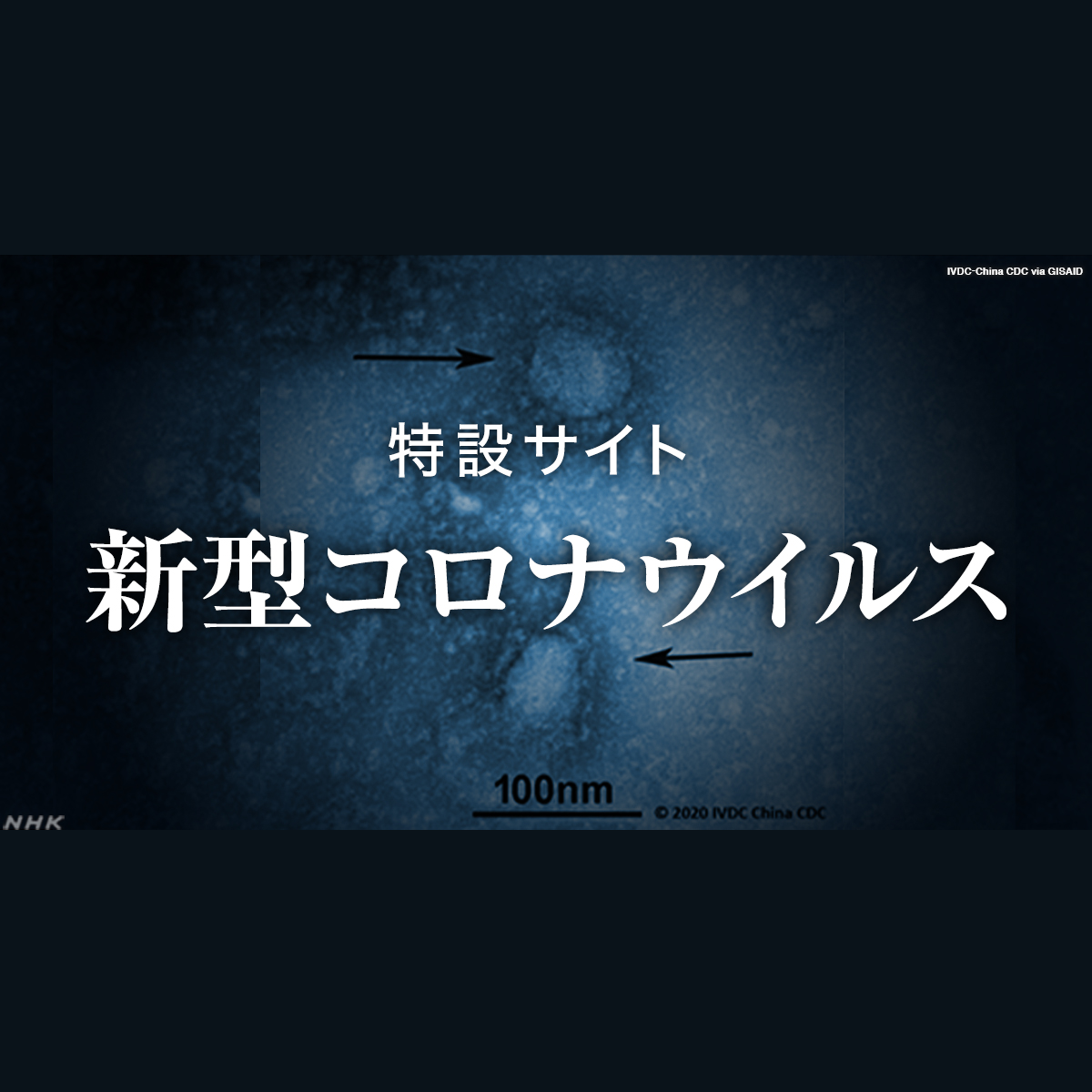昨日6/1から、学校再開、営業再開など
緊急事態宣言解除に伴い
少しずつ日常が取り戻される
ようになりました。
でもまだ油断はできません
第二波も心配されています。
そしてこの新型コロナを克服した
(ワクチンや治療薬ができる)
としても次なるウィルス感染症が
いつかまた世界を襲うかもしれません。
地球温暖化の時代を生きる私たちは
いつ感染症に襲われるかわからない、
ということは、以前から環境問題の
大きな課題として言われてきました。
私も昨年12月の市長への一般質問で
温暖化対策の必要性として
新たな感染症への危惧に触れました。
当時は市の職員の方も
感染症対策、やらないといけない、
という危機認識を共有してくれたことを
思い出しますが、まさかこんなに
早く危機が訪れるとは。。。。
地球温暖化がなぜ、
新たなウィルスを生むのか?
については長崎大、
山本太郎教授が解説しています。
世界各地でエイズなどの感染症対策に
携わってきた山本教授がNHKで語ったのは
“生態系への人間の無秩序な進出であるとか、
地球温暖化による熱帯雨林の縮小、
それによる野生動物の生息域の縮小によって、
人と野生動物の距離が縮まってきた。
それによって、野生動物が本来持っていた
ウイルスが、人に感染するようになってきた。
それが、ウイルスが人間の社会に出て来た原因だろうと思います。”
※詳細は文末のリンク参照
また酪農学園大学
動物薬教育研究センターの論文では、
“野生動物を材料とした料理を食べることも、野生動物とヒトの距離を近づけています。今回のCOVID-19の発生に関係していると考えられた武漢華南海鮮卸売市場では100種以上の野生動物や肉を扱っていた“ と述べています。
北里大学の獣医伝染病学研究の高野友美教授も、
「ヒトのコロナウイルスの祖先は
コウモリのコロナウイルスである!?」と
2017年、イタリアの研究グループが
既知のコロナウイルスの
遺伝子情報をもとに提唱したことから
(Forni 2017. Trends Microbiol 25: 35-48)
コウモリ由来、中間動物を介した
ヒトへの感染出現を論じています。
100年に一度のパンデミックも
今後はさらに短いスパンで訪れるかも
しれないことを覚悟しておかなければ。
けれども、それを乗り越えていく
原動力となるのは、
「未来の社会への希望」
だと山本教授は示唆しています。
子どもたちが成長したときにも
明るい未来であって欲しい!
そう願うならば、私たちは
いまコロナ対策と同時に
未来のための社会づくり、
ウィルスと共生して命を守る
地球の環境づくりも
進めていかなければ、と思うのです。
長崎大 山本教授のインタビューは
NHKの下記リンクのほか
今朝6/2 産経新聞コラムでも掲載されていました。