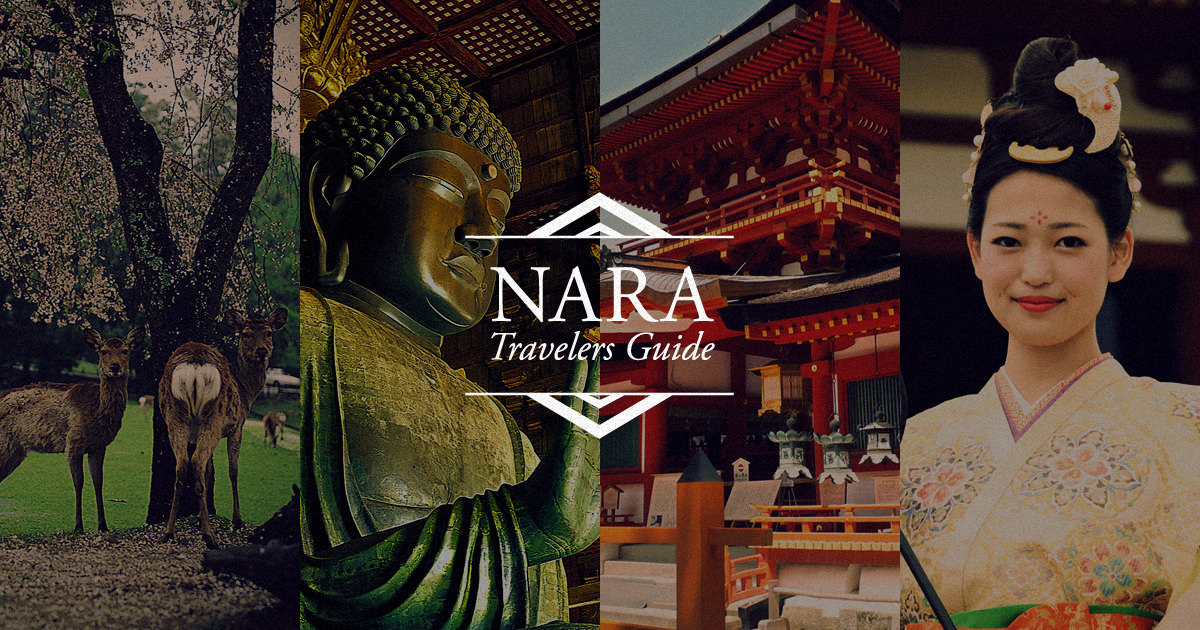東院庭園は
平城京跡の東南にあり、
グーグルマップで調べると
遺構展示館からは
徒歩15分と出ました。
私は駐車場へ一度戻って
東院庭園の駐車場に
車を停め直す事を
提案しましたが、
その場合は
平城京の周りの公道を
ぐるりと遠回りする事になるので
車で行くのと時間も変わらないから
(車で10分と出ました)
歩いてしまおうと
夫が主張した為、
「また車を取りに行くのに
徒歩15分かかるのに…。 」と
」と
内心思いながらも、
「こうして歩くのも
楽しいからいいか🎵 」と
」と
夫の言う通りにしました。
後でわかったのですが
(実際に後で通りました )
)
平城京跡の敷地には
近鉄電車が走っているだけではなく
地元の人が抜け道に使う
ほっそい車道
(歩道のような道 )も
)も
いくつか存在していて、
ショートカットして
車で東院庭園の駐車場まで
行く事も出来たのですが、
グーグルマップさんはもちろん
そんな道は把握していないので
まっとうな道を
指示してくれた訳です。
この時点では知らないので
私達は歩き始めました。

ホテルから眺めていた通り
平城京跡は見渡す限り
何もない草原(くさはら)で
時々高い芦の群落さえも
続いていました。
枯れ草を踏みしめながら
夫とのんびり歩いていると
悠久のかなたのその時代に
タイムスリップしたような、
自分が当時の人間になって
夫と2人語らいながら
歩いているような、
そんな不思議な気持ちがしました。
この後東院庭園の
ボランティアのガイドさんに
伺ったのですが、
木簡がたくさん出土したのは
この地が地下水が豊富で
土中の水分が多い為に
朽ちずに保存されたのだそうです。
湧き水に事欠かず
山の木材にも恵まれて
洪水や火山や津波などの
天災の影響を受けにくい、
暮らしやすい風土。
海がなくても
山幸川幸が豊かな
静かで落ち着いた場所。
海なし県と
まるで蔑むように言われるけれど
滋賀、奈良、岐阜、長野、
栃木、そして埼玉は
津波だけは来ませんから
どこも住むのには
とても良い所です。
「ナラ」という言葉は
韓国語で「国」を
表すそうです。
いにしえの中国や韓国の文化が
最先端とされた時代には
私達が英語やフランス語など
横文字をあえて
公的なものに使うように、
日出ずる国の新しい都も
世界に伍する為にと
「ナラ」と誇りをもって
名付けられたのでしょうか❔
それとも、もしかすると
日本に渡来して来た
彼の国の方々が
「私達の新しい国は
ここ日本なのだ。
今こそ、私は新しい
素晴らしい国を
ここに作ってみせるのだ。」という
決意と希望とに燃えて、
そう名付けたのでしょうか❔
高御座の前で思わず知らず
感涙した私は、
何が「やっと」で
何が「ここまで来た」のですか❔
私の体を借りて
感動で男泣きに泣いたのは
どなたなのですか❔
もっと詳しく教えて下さい、と
心で呼びかけながら
歩いていました。
東院庭園に着くと
ボランティアのガイドさんが
空いていらっしゃったので
ガイドをお願いする事にしました。
私は行く先々で嫌な人に
あったためしがありません。
日本国内どこへ行っても
みなとても親切で丁寧で
細かな気配りをして下さるので、
なんという美徳かと
いつも旅先では
人に本当に感動します。
その土地によって
シャイで控え目なのか
積極的にかかわろうとするか、
人へのアプローチは異なるなと
いつも感じます。
奈良の方々は京都の方々と異なり
全体にアプローチが積極的で
どんどん色んな事を
向こうから話して下さるな〜、
明るくてのびのびした
闊達な方が多いな〜と
前回も今回も
感じました。

東院の南にあるこの門は
建部門(たけるべもん)と
いうそうです。
平城京では門に氏族や部(べ)の
名前をつけていたそうですが
真南にあった大伴門は
藤原種継暗殺事件により
朱雀門と名前を
変えられたそうです。
小子部(しょうしべ)門という門の跡が
東院の西にあるけれど
ガイドさんの知り合いで
「小子部さん」という名前の人が
実際にいたそうです。

アンテナの立った建物は
旧そごう百貨店です。
1988年1月12日
奈良そごう建設にあたり
調査した所、
そこが長屋王の邸宅跡だった事が
4万点も発掘された木簡から
判明したそうです。
凄い発見❗
奈良では江戸時代から
地元の人達自ら
平城京跡を守ろうという
保存運動が始まっていたそうです。
昭和40年には
国道バイパス工事計画に伴う
事前調査によって、
平城京の東に張り出し部分があったと
判明し、計画を変更して
国道24号を東に大きく
迂回させています。
そごう建設について
当時地元の人達からは
反対運動が起こったそうですが、
そごうの社長さんは
遺跡を埋め戻してその上に
奈良そごうオープンを
強行したのだそうです。
しかし、駅から遠いせいもあり
そごうは早々に撤退、
その後入ったイトーヨーカドーも
撤退したそうで、
今は「ミ・ナーラ」という
商業施設になっているそうです。
長屋王が藤原氏によって
国家転覆の罪を着せられて
自○させられた後、
藤原4兄弟が天然痘で亡くなり
長屋王の祟りであると
大変恐れられたのだそうです。
奈良の人の中には
そごうとヨーカドーの不振について
長屋王の祟りだと
言う人もいたそうです。
「平城京の中を走っている近鉄電車は
(特に呪いもなく)
大丈夫だったんですね❔ 」と
」と
私が尋ねると、
保存運動の一環として
近鉄と長年交渉してきた結果
2020年にようやく
近鉄の地下鉄化が決まったそうです。
えっ、
奈良ってどこを掘っても
遺跡が出てくるから
地下鉄は引けないって聞いたのに
地下鉄作るなんて
大丈夫なの と
と
思ってしまいました。
そっちの方が遺跡にとって
悪い事なのでは❔

とまぁ、
奈良の人にとっては
知られたお話でしょうけれど
私達にとっては興味深いお話を
説明していただいた後、
東院庭園の中へと
案内されました。
ちなみに、
私達は寄らなかったけれど
ミ・ナーラの南には
別の庭園跡が復原でなく
今も現存しており、
無料で拝観出来るそうです。
昭和になって判明した
平城京の東に張り出している
南半分が
「続日本紀」に見える
「東院」にあたる部分です。
奈良時代には
「東宮」「東院」と
呼ばれていたようです。
他の宮城にはこうした
張り出し部分はないので
歴史的な大発見なのだそうです。
昭和42年にその南東隅に
庭園遺跡が発掘され、
奈良の世界遺産認定を目指して
その歴史的価値を
国内外にアピールせんと
様々な活動が行われ、
その活動の一環として
東院庭園は
平成7年から10年にかけて
復原されました。
めでたく平成10(1998)年には
世界遺産に認定されています❤
東南角にあった建物は
何をする為の建物だったか
よくわかっていないそうですが、
隅楼と呼ばれています。
柱の底に石や木の礎板を据えたり
貫を通して腕木とし
その下に枕木を交差するなど
手の込んだ作業から、
二階建ての物見のような建物を
復原したそうです。

建物の頂上にいる含綬鳥は
正倉院文様に見られる
権力の象徴を表す
おめでたい鳥です。
嘴に咥えている「綬」とは
紫綬褒章などの綬と同じです。
昔の身分のある人は
地位によって色の違う紐で
印を結んで腰から常時
ぶら下げていたそうで、
「綬」を授ける事が出来るのは
天皇陛下だけなのです。
夫はお役人にならなければ
歴史教師になりたかったというくらい
歴史に詳しいので、
見てすぐわかったらしいのですが
私は話を伺って
ただただ「ほぇ~」と
感嘆するばかりでした。

ここの柱は
正八角形だったそうです。
立ってみると、
なるほど柱の数に較べて
スペースが狭いです。

いいですねぇ、
住まいの中にのんびりと
月見や曲水の宴が出来る
お庭があるなんて…❤
わかります❔
東院庭園のご親切なガイドさんに
感謝いたします。
ありがとうございました❗
やっと当初の予定通り
法華寺と海龍王寺に行けます❗
続きます。