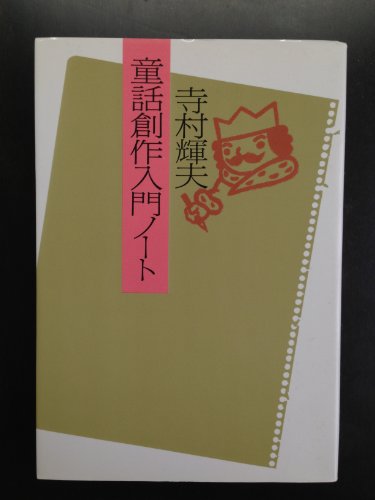寺村輝夫さんの著作を読んでの、幼年童話創作は悪戦苦闘中です。
一応は、原稿用紙10枚ぐらいは書けたのですが、明らかに枚数オーバーな書き方で、
20枚ぐらいになりそうだったり、
文章が寺村さんのものとは似ても似つかぬ説明調だったり
書いてて、ダメ出しで途中停止。
今、もう一度、書き直し中です。
同時に『寺村輝夫の童話に生きる 全一冊』にあった「わたしの童話創作ノート」の中で、
気になったアドバイスや書き方を、メモ帳アプリへワープロで打ち込んでしました。
こちらの方が描くよりも、朝から何時間もかけて書き写しています。
とにかく、分厚い本なので、今、読み終わったところを写すだけでも、全然、終わりそうもありません。
でも、読んでラインを引いたり、コメントを書き写すだけでは、全然、自分の心に刻まれないので、いつもこの方式です。
で、あまりにアドバイスが的確で凄いので、まるで自分のいま書いている原稿を寺村さんが読んで、
ダメ出しして添削していただいているようなので、
たまらず、時々、その記憶の鮮明なうちに、自作を推敲しつつ書き足しています。
「人間が人間をのみこむのは不合理だなどと考えてはなりません。そういう合理的な現世的な思考は、童話のリズムにはじゃまです。子どもらしく、即物的な論理に徹してください。童話はつくりものです。大いに創るのです。
(略)こうなると。まさに遊びです。知恵くらべです。作者は大いに遊びましょう。知恵を出しましょう。楽しみましょう。遊びなしには思考は育ちません。このあたりが、子どもと作者の接点になるのです。」
「鬼のやつ、たまげるやら痛いやら。とっつあも、きゅうに腹がふくれて、大きな屁を一ぱつ、せつぶーん!/鬼は屁といっしょにとびだして、どこかへ(略)賢明なる作者は、この意外な結末に、ただのひとことも解説はしません。(略)すべてを感じることはできるのです。にやりと笑い、なるほどと納得するのです。よぶんな解説は、いらない仕組みになっているのです。(略)おならを音高々に鳴らせるために、ストーリーはあったのです。
ストーリーの組み立てが骨太に、単純に、よくできていればこそ屁は鳴ります。」
「作者は〈入口〉〈出口〉にかかわりすぎているのではないでしょうか。そのために、やや平凡の感じがまぬがれないのです。(略)ファンタジーは個人的な体験です。夢から出てきた子どもは、あとで、だれに話てもわかってもらえないのです。(略)つまり、ファンタジーを体験したものは、体験する前とはちがったものになっていなければなりません。心の中で、イメージの中で、成長をとげなければならないのです。(略)しゃれた後味です。それだけに、ともきの〈変化〉が弱まっているのです。やはり〈母親〉のほうに(大人の視点に)かたよってしまったのです。」
「〈意外性〉その1 まさかあ(略)日常性になれきっている読者は、常識の支えによって生きているようなものです。だから、意外な話の展開に、ショックをうけるのです。」
たぶん、これらの言葉を、10年前の僕は、頭で納得しているだけで、
幼年童話は書けないしな、と知識にしたものの、実感も身体化もできないままだったのでしょうね。
そして、ここに書いていることは、ほとんど、全て、童謡や幼年向けの詩に当てはまることで、その意味では詩を書くときに一部、感覚化や身体化できていたことでした。
つまり、ここに書いていることを気をつけていけば、童謡とか以外の大人向けの詩の創作感覚にも影響を与えたり、
短歌、俳句の制作にも最終的には変化を引き起こす予感があります。
すごく意味のあることだと確信があります。
また一段、正解に近づけたのでしょうか。