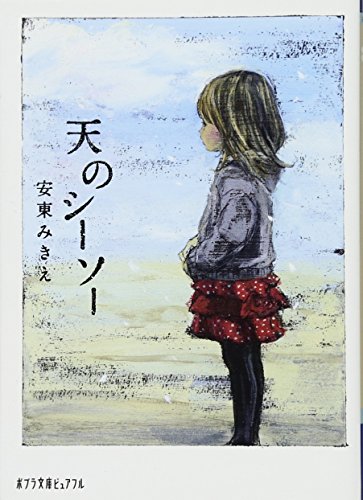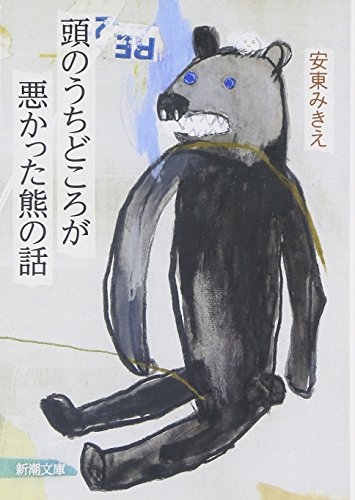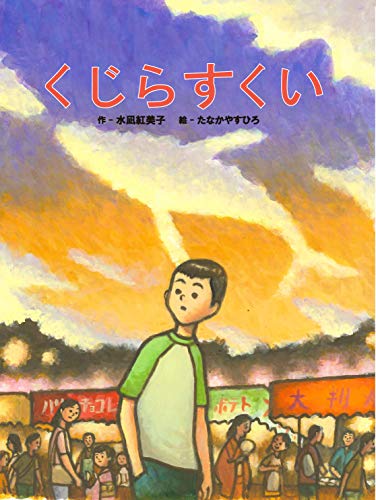昨日、書いたように、とりあえず過去の落選作品の書き直しから始めましたが、
その作品からそのまま改稿する直し方をしていると、引っ張られて変わり映えがしないのは何度も経験済みです。
なので、
何となく1回読み直して、それを今度は全く見ずに、
「こういうところを変えた設定だったら、どうなるのかな」とか、
「同じ設定で現代詩の異化現象を書くとしたら、どうするだろうか」とか、
無茶振りしながら、書き直しを始めました。
わかりやすくいうなら、これは児童文学じゃない、詩だよ、童謡だよ、と自分に言い聞かせながら書いています。
(これ、思わず、笑い出したくなるのは、それまで全然詩が書けなかった自分に、
3年半前は、今、書いているのは詩じゃなく、童話かショートショートですよと言い聞かせて、「きっと書けるから、大丈夫だよ」と自己暗示を掛けて、ようやく書けたんですよね。
その、まるっきり逆です。笑wwwww)
また、昔、読んで「凄いな」「どうしたら、こんな変な(=「すごく不思議で面白い」の褒め言葉)話を書けるんだろう」と感心しきりだった、
安藤みきえ著『頭のうちどころが悪かった熊の話』なんですが、
今、久しぶりに読み返すと、まるで現代詩的な感性では、スッキリと、書けそうな気がするんですよね。
生真面目な童話的な感覚で読むと、ハチャメチャな話も、詩的に読むと、「アナロジー(類比)」と「ズレ」で了解できちゃいます。
散文じゃないんですよね。
ところが、やっぱり上手くいかない。
童話の落選作は、全く使い物にならないクズばかりでした。
そこで、これもどうも生活童話っぽくて苦手で、二度応募して無理だと思った〈日産の童話と絵本のグランプリ〉コンクールの
童話部門入賞作品を読み直してみました。
僕が応募した10年前とは、選考委員が富安陽子さんとかファンタジー系も書く方に変わったせいか、
(それまでは、生活童話系の方でした。)
近年の入賞作品は、とても面白く、ある意味、ファンタジックか、詩的ポエジーがある作品に変わっていて、
これなら自分の作風にぴったりと思いました。
(生活感というよりも、子どものみずみずしい感性主体の、感覚的生活童話なら、大丈夫です。今はそれが書けるんです。
けど、文科省推薦マークがつくような、立派な子どもなりましょう系の大人満足の生活童話は、大の苦手です。
途中で、嘘じゃんと思ってしまうし、楽しくならなくて嫌になるんですよ、書いてても。
どうして、書き終えられるの? 楽しいのそれ、になってしまいます。)
そこで、それら作品の良かった点を十分に咀嚼して、
過去の自分の一番の成功作「からくり天狗飴」(明石市文芸祭・議長賞)を再分析。
そのフォーマットを、咀嚼した作品のポイントを混ぜ合わせ、
そこに俳句の簡潔文体と、現代詩の展開感覚と異化・メタファー・アナロジー現象言語感覚を足してみました。
(書くと無茶苦茶ですが、頭おかしい人みたいですが、要は全部自分の感覚なので混ぜ合わせ可能です。笑)
まるっきりの新作になります。
ともかく、自分の書く現代詩や童謡詩の作風を、散文に移籍した10枚ぐらいの作品を、2・3作、案を立てて書いております。
それを、明石市文芸祭や、〈日産の童話と絵本のグランプリ〉、その他の童話部門に出してみるつもりで。