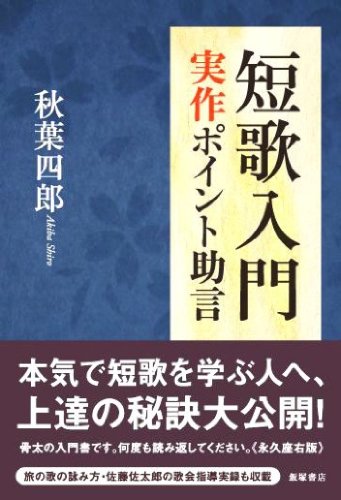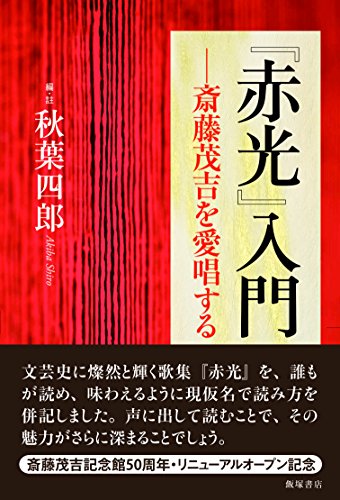前回、某新聞の文芸欄の詩作品で、最優秀賞が一つの最低目標と書きましたが、
他にも、永瀬清子現代詩賞など一連の公募賞へ入賞することを当然、目標としています。
去年は、正賞の次、準優勝の位置ばかりだったので、今年は1位をどれも目指しています。
今年は、それら詩に関する目標とは別に、短歌・俳句にも目標があります。
短歌では、河野裕子短歌賞(8/19〆切、3句1組まで3,000円)に、ベストな短歌作品を出すこと。
俳句では、西東三鬼賞(11/30〆切、5句1組まで2,000円)に、同じくベストな俳句作品を出すこと。
普段、例の十二音日記で書いているのは、どちらかと言えば、俳句ばかりで、
短歌のストックは、10分の1ぐらいでしょうか。
前に書いたように、僕が書いている短歌は俳句的な写生感覚にプラスして、近代詩的なテイストとのハイブリットになっています。
それが正しいか否かは、今のところ、確かめられていません。
短歌教室に通って、真正歌人の先生との感覚の差を何人もで確かめたく思うんですが、今のところ、コロナで休講なので、どうしようもありません。
たぶん、予想では、俳句より短歌の方が「詩」の感覚を活かせるかな、と思います。
だからこそ、異質な俳句を勉強することが肝要かな、と信じています。
実際、詩単独しか作れなかった頃にくらべて、
今は前に書いたように、季節に敏感になりましたし、
雲や雨、花が「友達」のようになりましたから。
その分、短歌の立ち位置が自分の中では、微妙になっちゃってるんですね。
ちょうど、短歌の技法書で秋葉四郎さんの『短歌入門』という本に、次のような一節がありました。
「そこで短歌を作る人は、いろいろな表現手段があるのになぜ自分は短歌にしたいのか、短歌はどんな文学、詩であるのか、短歌に未来があるのかなど、それぞれの作者の発達段階に従って考え、理論化する必要がある。これを「歌論」というが、短歌作者は作り始めから、初心者には初心者なりの歌論のある事が大切になる。」p 15
秋葉さんは、文学博士で研究者でもあるんですね。
この本は、短歌の個々のスキルよりも、こうした文学ジャンルからの意識とか、妙に僕の中の研究者魂にフィットしてくるので、
図書館の本では満足できずに、買ってしまいました。
もちろん、ここでも、カロンだけでなく、僕の中では、「僕には詩論ってあるかな。そういえば、あるな」
「うーん、小説でも、碌な作品もかけないのに、小説論だけは山ほど頭に入ってるぞ」とか、
「その小説メソッドで、詩を作り続け、その詩のメソッドで、さらに、俳句・短歌を作ってるよな」などと思っちゃうんですよね。
この一文だけで、ムッチャ妄想、雑念が一瞬で浮かびました。
上の文に続けて、秋葉さんは、こう仰います。
「作歌はどんな場合でも、文学の創作だから、直感的であり、感覚的であり、常に自身の実感が大切にされる世界である。しかるに作歌初途から歌論がいるということはどういうことか。
一つには、短歌が千三百年も続いている伝統文芸であるということにある。日本人であれば学校教育で学んできている文芸であるから、最初から相当な判断が要求され、指導者や短歌教室などに対しても主体的に選ぶ必要のある世界である。つまり何人と家でもゼロから始まる世界ではない。その本質や進むべき方向、根本的なあり方などを最初から考えつつ進まなくてはならないものである。(略)
もう一つには、新円となるカロンが実作と共に進んでゆかないと、作歌が継続できないという事がある。日本が近代となって正岡子規の提言した短歌革新は「短歌写生論」として理念化されたから、今日まで継続され、強い流れになっているのである。」p17
うーん、誠に達見です。
僕のような感覚的人間なのに、何事も頭で納得しないとできない人間には図星そのもの、どストライクでした。
ともかくも、僕の企ては、こうした俳句や短歌を勉強する過程で、自分の中の詩論が明確化されたり、自分の文章力が刺激され変容してゆくことに、真の目標があります。
真剣に俳句や短歌をやってる人間からは、ふざけていると叱責されそうですが。
でも、文学ジャンル自体、常にこうして、他からの刺激で変容し、それが「進化」と捉えられたり、「革新」と呼ばれたりするものだと思うのです。
蛸壺に篭っている事だけがプロフェッショナルではないはず。
何よりも、僕自身の思惑とは別に、日々、俳句や短歌との距離感もどんどん変化してますから。
ともあれ、前記の賞二つとも、今回が初めての応募になるので、1年間のお試し投稿の一つと思っています。
とにかく、一歩一歩、何かしら進歩すること。
何かへ挑戦すること、立ち止まらないこと、努力すること。
これしか頭でっかちで、不器用な僕には、できることがありません。