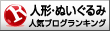夜、携帯の電話が鳴る。いつものことだが、電話に出るとそれは彼女だった。遠距離恋愛の相手との心のすれ違いが彼女を苦しめていた。僕はいつだって聞き役で、週末の金曜には何時間も彼女の愚痴を聞かされたこともある。人の恋路のアドバイスなどはできようもない。僕はただ聞いているだけだ。だから僕は別に彼女の役にたっている訳ではない。それでも彼女は僕に話を聞いてもらっているだけで安心するようだ。おそらく僕は彼女の精神安定剤のようなものなのだろう。彼女はメールではなくて直接僕の声が聞きたいと言う。休日には彼女から呼び出されてあてどなく彼女と街をさまよう。「彼に会いに行けばいいじゃないか。」と僕は言う。「彼、休みの日も仕事に追われているみたい。月に一度会えればいい方。」と彼女は言う。
実は、僕は彼女に魅かれている。街をふたりで歩いている時、喫茶店で向かい合ってコーヒーを飲んでいる時、僕は思う。彼女が僕の恋人だったらよかったのに、と。僕はいつも彼女の悩み事を聴いているわけじゃない。いつも頬をつたう彼女の涙を見ているわけじゃない。遠方の支社に勤務し、仕事に追われて、時間のない恋人の代わりに、寂しい彼女の心を埋めるように僕は彼女の横を歩く。彼女の無邪気な笑いが僕は好きだ。僕に向けられる微笑みが好きだ。そして、たいがいの時間を僕らはむしろ楽しく過ごしている。はた目からはカップルに見えるかもしれない。でも彼女は僕の恋人じゃない。「あなたは、わたしがつらいとき一緒にいてくれる大切なお友達。」と彼女は言う。僕はピエロのようなものだ。彼女の前で僕はいつも笑っている。でも心は泣いている。彼女は僕の笑顔が好きだと言う。だから僕は泣き顔を隠さなくてはいけない。彼女は一緒にいられない彼を想い、僕は一緒にいる彼女を想っている。
僕は私立の高専のデザイン学科を出てから、木工と金工の職業訓練を1年間受けて、実家の離れを工房にしてアクセサリーや工芸品の通信販売を始めた。でも、始めていきなり食っていけるはずもなく、書店のアルバイトもしていた。彼女とはそこで知り合った。彼女はそのとき大学生だった。同い年の僕と彼女はすぐに打ち解けて、とても仲良くなった。僕は彼女に魅かれていったが、彼女には同じ大学の一年先輩の恋人がいた。やがて彼女の就職が決まり、大学を卒業する時、僕らは互いの住所と電話番号、メールアドレスを教え合った。それから僕は、通信販売も軌道に乗り出し、兄夫婦が両親と同居して離れに住むことになったので、秩父の山あいの町の空き家を借りて独立した工房を開くことにした。秩父の山あいといっても、埼玉副都心にはすぐにでられるし、東京もさほど遠くない。立地は理想的だと思った。彼女と離れたことは寂しかったけれど、僕はまだ23歳だったし、一時の恋心と思い、創作に専念した。
彼女から頻繁に電話がかかってくるようになったのは、独立工房を構えて、1年ほどたった頃だった。彼女とは暑中見舞いや年賀状のやりとりをするくらいだったが、一年前、彼が遠隔の事業所に転勤になり、しかも当分は東京に戻ってはこられないという。遠距離恋愛にありがちな心のすれ違いが彼女を不安にさせたのだろうが、その相談相手が僕になるとは思ってもみなかった。そうして僕は良き友人として彼女の相談相手を3年間もしている。最初は電話で話をするだけだったが、ここ2年ほど僕らは埼玉副都心で会うようになった。そして僕はまた彼女に魅かれていった。
頻繁に電話をして、週末には街で会っても彼女は恋人ではない。それは切ない想いだった。それでも僕はそれでいいと思っていた。泣いたり笑ったりする彼女を見ていられるだけで幸せだと思った。彼女は我儘で、自分勝手で、すぐむくれるくせに、人一倍の寂しがり屋だった。そんな彼女が愛おしかった。そしてやがて切なさは次第に痛みに変わっていった。彼女が笑うと僕も笑う。でも心の中では僕は泣いていた。遠く離れてはいても彼女には恋人がいる。それにいつ東京に戻ってくるかもしれない。所詮僕の想いは届かない。それはもう鋭い痛みとなって、僕はもうピエロを演じることができなくなった。
さくらの花も盛りを過ぎ、葉桜となった頃、僕は公園の池の水面を見つめながら彼女に言った。「僕はいい友達かい。」、彼女はにっこりと笑いながら「もちろん。」と答えた。僕はもう笑えない。池の鯉に餌を落としながら、「僕はね、本当は君のことが好きだ。ずっと前から好きだった。そろそろ限界だ。もう友達のふりができない。だから、サヨナラかな。」今日、僕は彼女にサヨナラをしにきた。僕の本心を言った以上、もう今までの関係は壊れる。「だから、もうサヨナラ。」彼女の顔はこわばっていた。「そこのベンチにすわろう。」と彼女が言い、僕らは池の畔のベンチにすわった。僕は彼女からの別れの言葉を待った。
彼女は何も言わなかった。ただ、肩を震わせていた。彼女は泣いていた。僕にはその涙の意味が分からなかった。「どうしたの。僕、何かわるいこと言ったのかな。」というと。「彼女は「ごめんなさい。ごめんなさい。」そう言いながら、彼女は肩を震わせて泣いていた。「どうして泣くの。君は何にも悪くないのに。」涙は次から次へと滴り落ちていた。「わたしね、嘘ついてた。本当は2年も前に彼とは別れていたの。それなのにあなたを無くしたくないから、彼がいないと、あなたまでいなくなってしまう気がして怖かった。だってあなたに相談することがなくなるとあなたに会う理由がなくなる。でも本当は、わたしね、わたしね、あなたが好きだよ。だからサヨナラなんて嫌だよ。」、まったくなんていう三文芝居だろう。2年間もお互いに片思いをしていたなんて。あきれるくらいどうしようもなく僕らは怖がりだ。27歳にもなって、いったい僕らは何をしているのだろう。中高校生でもあるまいし。いや、こういうことに年齢は関係ないのかもしれない。
それから、「わたしも、あなたみたいに自分の好きなことをして、自由に暮らしたい。」、「貧乏するけどね。」、「時間を盗まれるよりいいでしょ。」と言って、彼女は会社を辞め、僕の広くて少し持て余している工房のスペースの一部を使って、小さな学習塾を開いた。そして生徒は少ないが、学校や進学塾ではできない、彼女なりの教え方を楽しんでいる。僕の服飾アクセサリーや装飾雑貨も結構評判がいい。空き家の持ち主が安い価格で家を譲ってくれて、とりあえず僕たちは、僕たちを生きている。もちろん僕らが一緒に暮らしていることは言うまでもない。そして新しい命も。
ブログランキングに参加しています。クリックしていただけると励みになります。