エディット・ピアフとおっしゃる。
プレミアム・ツイン・ベスト ばら色の人生~エディット・ピアフ・ベスト/エディット・ピアフ
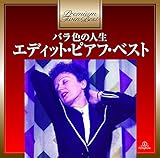
¥2,057
Amazon.co.jp
まずはいったい、
どのくらい昔の方かということで、
生没年月日を記しておく。
1915.12.19~1963.10.11。
第一次大戦の最中に生を享け、
次の大戦をまるまる経験し、
僕の生まれる三年前に
お亡くなりになっている。
――そうか、今年生誕100年だったのか。
まあ、今のパリは、
それどころではないのかもしれないが。
ちなみにプレスリーが35年、
本邦の美空ひばりさんが
37年の生まれだから、
彼らはたぶん、彼女の
レコードを聴いて育っている。
音楽の世界にいて、
『愛の讃歌』を知らないということは、
まず間違いなくないだろう。
そう考えてみると、ひょっとすると
この人の残した音源というのは、
僕が手元に置いて聴いているうちで、
一番古い時期に
録音されたものである
可能性だって十分にあるのか。
そういうのは、
やっぱりものすごく不思議に思う。
極端な話をすれば、
僕らはベートーヴェンやショパンが、
自身がいったいどれほど
優れた演奏家だったのかを、
自分の耳で確かめることは、
タイム・スリップでもしない限り、
どうしたって叶わない訳で、
20世紀になって登場してきた
音楽家についてのみ、
それが叶う可能性があるだけである。
厳密には、1877年12月6日以降、
ということになるのかな。
いや、まったくエジソンに感謝である。
だから、それ以前はたぶん、
音楽というのは本当に、
その場限りのものだったのだろう。
一期一会なんて言葉がまた、
どうしても思い出されてきてしまう。
でも世界初の音楽ソフトって、
いったいなんだったんだろうなあ。
まあクラシックであることは
九分九厘間違いはないのだろうけれど。
いや、不惑過ぎて十年近く経っても、
知らないことはまだまだあります。
ちなみに僕らがよく知っている、
いや、知らない人の方が、
実はもう多いのかもしれないけど、
LP/EP、つまりヴィニール盤が、
世の中に登場してくるのは、
第二次大戦の終結後、
48年くらいになってからのことである。
だから今回のこのE.ピアフの
歌っていうのは、最初はたぶん、
あのSPってやつだったのである。
あのすっごく重いやつ。
いや、持ったことないけど。
だから本当は知らないんだけれど。
まあ、僕の本来の仕事の
本質っていうのは
結局のところ嘘つきなので、
その辺はまあ、
笑って流していただければと。
でも本当の本当は、一回だけだけど
持ち上げてみたことある。
なんか資料館みたいなとこで。
さて、ちなみにこちらのネタは
もう前に一度
どこかで書いてもいるのだけれど、
世界で初めて、商品としての
コンパクト・ディスクが
発売されたのは、
なんと我が国での出来事である。
もちろんクラシック作品群を筆頭に、
それからMJのTHRILLER、
ビリー・ジョエルの52nd STREETなど、
複数のラインナップが、
一度に発売されているのだけれど、
その中には、
大瀧詠一さんの『A LONG VACATION』と
佐野元春さんの『SOMEDAY』が
タイトルを連ねていたりするのである。
だから、お二人は実に、
世界で一番最初に
CDをリリースした
アーティストの一人なのである。
さらにさらに横道に逸れると、
世界で一番最初に配信、つまりは
データのスタイルで、
音楽を売ろうとしたのは、
たぶんデュランデュランである。
このネタはまだちゃんと
十分なウラ取りをしていないのだが、
どうやらアルバム
MEDDAZZALAND(97年)の時に
それをやって、
当時のリテイルから
ものすごい反発を喰らったらしい。
リテイル=小売店なんで、念のため。
だからそういうところがね、
実はこの人たちは
相当すごいんだよなあ、と、
僕がこの年になっても、
何度も改めて
思ってしまう所以なのである。
などといいつつ、気がつけば
今回はピアフの話をまだほとんど
全然していないではないですか。
ごめんなさい、さすがにさほど、
詳しい訳ではないもので。
でも上で触れた『愛の讃歌』や、
あるいは『バラ色の人生』なんかを、
たとえそれとは知らなくても、
一度も耳にしたことのない方というのは、
さほどいらっしゃらないのでは
ないだろうかと思うのだが、どうだろう。
『愛の讃歌』は、あれである。
貴方の燃える手で
私を抱き締めて
僕だってメロディーを聴けば、
この歌詞が空で出てくる。
いや、もし間違ってたら
相当カッコ悪いけど。
本当に空で書いたので、
漢字表記はあるいは
違っているかもしれませんが。
でも大丈夫だと思うんだけどなあ。
さて、という訳で今回表題にした、
Sur le Ciel de Paris
(邦題『パリの空の下』)と、
それから上のLa Vie en Roseとは、
なんかもう、どちらも、
イントロを聴くだけで、
パリだなあ、という感じである。
こういうのをだから、
シャンソンというのだと思っている。
とりわけ『パリの空の下』の方はね、
全編に入ってくる
アコーディオンのラインが、
もうまさにパリ。
石畳、焼き栗、カフェ。
ムーラン・ルージュ、
それからピカソとか
モディリアーニとかユトリロとか。
いやむしろ、僕はこの音の方から
パリという街を
自分のイメージにしているのかもしれない。
そういう訳でこの方については、
僕はせいぜい、
映画を見たくらいの知識しか
実際は持ってはいないのだけれど、
それでもどうやら相当、
エキセントリックな方だったようではある。
まあ、アーティストっていうのは
そういうところが
あるものなんだろうなあ、と
思うくらい。
レコードというよりは、
パフォーマンスで聴衆を圧倒する
そういうオーラみたいなものの
持ち主だったのではないかと思う。
出生や、あるいは大戦中にも
いろいろなエピソードが
ある模様なのだが、
なんかここで文字に起こせるほど、
まだ咀嚼できてないなあ。
だってねえ、あのジャン・コクトーが、
彼女の死に驚いて、
その翌日には自分も
死んでしまったのだというのである。
それはもう、本当オーラかあるいは
それ以上のものとしか
いいようのない影響力だろうと思う。
すごい人だったんだろうなあ、と、
現段階では正直それしか出てこない。
それでもなんとなく、我が国での、
美空ひばりさんみたいな
存在だったのではないかと思って、
まあ今回は、最初の方で
ひばりさんの名前を出しみていたりする。
ちなみにこのピアフは、本名ではなく、
雀を意味する俗語だそうで。
そんなところもまた、
なんとなくひばりさんと
カブる気がするのは、
まあたぶん僕だけだろうなあ。
ほとんどこじつけみたいだな、と
書いていて自分でも思います。
彼女の墓所を訪れるファンは
いまだに絶えないのだそうです。
そういうことが自由にできる日常を、
あの街が取り戻して
くれることを切に祈っています。
この場所からでは、
さらには僕ごときでは、
それ以上のことはほとんど何も
できないといっていいのですが。
なお、このピアフによって見出され、
世に出て名を成した
シンガーというのも少なくはなく、
イヴ・モンタンとか
シャルル・アズナブールなんかが
挙がってくるのだそうです。
なお、例によって横道上等ということで、
名前を出してしまった以上は
一応触れておくことにするけれど、
このシャルル・アズナブールなる方、
一目瞭然だとは思われるが、
あのシャア・アズナブルの名前の
元ネタになった方である。
その証拠に、このシャルルには、
アルテイシアという妹がいる。
いや、こちらは嘘である。
――いや、だから、嘘つきだから。
本当に厳密なところをいうと、
これに関しては、
まだちゃんとしたウラを取っていない。
もし実際このアズナブールに、
アルテイシアという名前の妹がいたら、
それは、富野さんすげえってことに、
なるのかもしれないとも思うけど。
そうそう、万が一シャアも
アルテイシアも
全然ピンと来ないという方には、
御自身でググッてみてください。
すぐ出てきますから。
さて、では締めの小ネタ。
本邦を代表する
シャンソン歌手といえば、
まずは越路吹雪さんの名前が、
一番に挙がるのだろうと思うのだけれど、
もうお一人、いわば
国民的シンガーがいらっしゃる。
たぶんこの方の声を
耳にしたことのないという人の方が、
むしろめずらしいのでは
ないかくらいにも思う。
もっとも万が一、
日曜の六時半のあの番組を、
一度も見たことがない場合は別である。
そう、あの『サザエさん』の
OP/EDを共に歌っていらっしゃる、
宇野ゆう子さんという方、
実は本来はシャンソンの
歌い手さんなのである。
これは本当に本当である。
いや、しかし今回は、
週末の余韻引きずって
まだ文章が
少なからずどころでなく浮かれてますね。
書いていて自分でわかりました。
来週はもう少し落ち着きます。