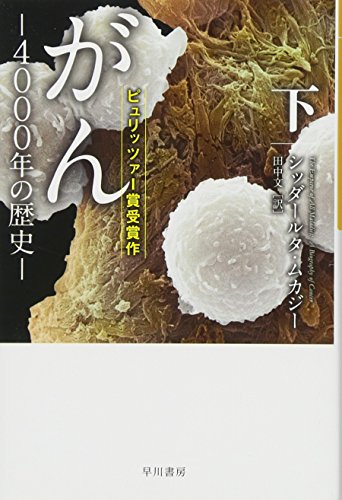がんにならなかったら、手にすることがなかったと思うのですが、本当に読めてよかったです。
タイトルに「4000年の歴史」とあり、古代エジプトの古文書にあるがんについての記録からスタートしてはいますが、そこから18世紀くらいまでは概要をおさらいしていく程度で、19世紀に「麻酔」と「消毒」が登場してから、話がどんどん深掘りされていきます。
そしてがん研究のメインステージは20世紀へ。
アメリカの医学界を中心に、手術の術式の変容、抗がん剤や放射線療法の発見と発展などが、ドラマチックに描写されます。
治療だけでなく、それを支える病理学や統計学、(昔の治験…それはそれは…)患者のQOLの領域の進歩も、今日の私たちが受けられる恩恵です。
さらに本書が重要視しているのが、社会的な運動。
お金がかかる研究の推進力として慈善団体や患者会が、政府や製薬会社に働きかけ続けてきたことにもページがさかれています。
下巻になるとより先進的な研究の領域になり、分子生物学的な記述が増えてくるので、ちょっと読みづらかったですが、医師でもある著者が、自分の患者さんの一人の生き方と、人類とがんの歴史を重ねるエンディングには、しみじみしました。
がんサバイバーの方、特に抗がん剤治療や緩和治療を受けている方にはオススメ!
ぜひ、上巻だけでも。
つらい治療ではありますが、20世期の状況に比べたら、2020年はなんと進歩していることか。
細かいことは省きますが、私たちが受けている治療は、なんだかんだでたくさんの犠牲がもたらしてくれた成果なんだと実感できます。
わりと最近のエピソードだと、シスプラチンの登場が印象的でした。
その著効性に対して「ささやかな副作用」…が、1日平均12回の激しい嘔吐だったそう。
1970年代には効果的な吐き気止めがほとんどなく、ようやく多少のコントロールができるようになってきたのが80年代。
そもそも患者の痛みや吐き気を本気でなんとかしよう、という発想は「がん撲滅」を掲げていたアメリカの腫瘍医の中に長らくなかったんですね。
この本では、緩和医療の潮流はイギリスからと書かれています。
今後、自分も抗がん剤治療が辛くなってきたら…
時代時代で果敢に新しい抗がん剤に挑戦して生きた人、亡くなった人…またチャンスがなかった人…小さい子から年配の方まで、数えきれない人たちからのバトンを私も手にしているのだ、と考えたいです。