皆々様…。
いよいよ、萌え~っとな場面が登場
(ΦωΦ)フフフ…
これよ…。
これを待っていたのよ(笑)
priest作『天涯客』より
第十七章「瑠璃」
曹蔚寧は呆然として、尋ねた。
「彼……彼はあの賊の祖先である方不知なのですか?」
若い女性はうなずき、死体の左手を指差して言った。
「見て。伝説で語られる方不知は三十代の男性で、左手が奇形なの。もし確信がもてなければ、実は彼は他にも……」
彼女は顔を赤らめ、続けることができなくなった。
周子舒は死体の美しくなめらかな顔と顎をじっくりと見て、傍で続けた。
「そのうえ、方不知は自分が障害を持っていることを知らなかったと言われている。お嬢さんは気分が悪くなったら先に出て行くか、背を向けたらいい。お前たちは彼の下衣を脱がせてくれ。そうすれば、彼が本当に神業的な盗人かどうかわかるだろう」
女性は気まずそうに同行していた青年をちらりと見ると、青年は軽く咳払いをした。
「小怜、先に出ていなさい」
若い女性は身を翻して出ていくと、扉の外で、背中を向けて待った。
彼女が背を向けると、すぐに温客行はてきぱきと死体の下衣を脱がせ、その体の特定の一部位が切断されているのを見、考え込むように顎を撫でながら、感嘆した。
「本当に彼だったのか。道理で私の体に触れて物を盗ったというのに、気づかなかったはずだ」
それからそれだけに留まらず、てきぱきと方不知を丸裸にし、無遠慮にあれこれと探し始めた。ごちゃごちゃに散らばった物の中から、自分の財布を見つけ出すと、開けて確認し、銭が減っていないことに驚き、喜んだ。大満足して懐にしまい込むついでに、丁寧に付け加えることも忘れない。
「曹兄、君も見たらどうだ? 君のものはまだあるか?」
曹蔚寧と傍らの青年は呆然として、この人を見つめていた。
「温善人、死者は尊重しろ」
周子舒が冷ややかに注意する。
その後、見知らぬ青年が賛同のまなざしを投げてきたにもかかわらず無視し、少し間をおくと、またひと言付け加えた。
「私に借りた三両の銀子を今回返してもらえるかな」
温客行が哀しそうな顔をする。
「私の全てはもう君のものなのに、君はまだ私と銀三両ごときで言い争うのか?」
その見知らぬ青年の顔色が、より良く上気した。周子舒は手を伸ばして温客行の襟をつかみ、この邪魔者を一旦脇に寄せると、しゃがみこみ、頭からつま先まで死体を触り、眉をひそめて結論を出した。
「一撃で命を奪っている。掌印は胸から心臓の後ろに貫通しているから、おそらく羅刹掌だろう」
見知らぬ青年は 「あっ 」と声を出し、驚いたように言った。
「あなたが言っているのは、あの喜喪鬼の羅刹掌のことですか?」
「おそらくはな」
周子舒はうなずき、言い終えると死体を布で覆い、入り口の外の若い女性に言った。
「お嬢さん、もう入ってきてもいいよ」
見知らぬ青年は彼ら三人をしげしげと見ると、抱拳した。
「私は鄧寛、師匠は高崇、こちらは師妹の高小怜と申します。私たち二人は、もともと修行の旅に出ていたのですが、数日前に師匠からの伝言を受け、洞庭大会が始まる前に急いで帰ってきました。あなた達は何とお呼びすれば?」
曹蔚寧が慌てて言った。
「ああ、失敬失敬。鄧少俠のお名前は以前から伺っております。そしてこちらのお嬢さん、高崇大俠の娘さんですね? 私、清風剣派の曹蔚寧は掌門の命を受け、洞庭大会に出席するため出向きました。師叔は近いうちに到着するはずです。私は道中でこの人……この神業的盗人に路銀を盗まれ逃げられたのですが、おかげさまで、あの周兄と温兄に義理堅く助けていただきました」
「お二人の英雄は、どちらの……」
鄧寛が聞く。
周子舒はまだ地面にしゃがんで調べていたが、その言葉を聞いて振り向き、彼に笑いかけた。
「英雄なものか。私の名前は周絮、どこへなりと放浪している単なる流れ者で、宗派にも属してはいない。そちらの……」
彼は温客行を指差し、微妙な間を置いて、続けた。
「あの温客行、温兄は、聖人君子のように振る舞っているが、実は経験豊かなごろつきだ……」
「阿絮、私がそのようなことをするのは、君ただ一人だよ」
温客行が平然と告げる。
「お前は私を過大評価しすぎだ」
周子舒は静かにゆっくりと言った。
明らかに高小怜の注意力は、すでに全く死体に向いていなかった。鄧寛は逆に平然としていて、言葉を聞いても寛容に微笑み、態度も謙遜でも傲慢でもない。むしろ正統派の名門、洞庭の主のような風格をみせながら、二人に対して抱拳した。
「お二人は本当に面白いですね。あなたたちは曹兄と一緒に我が洞庭にお越しになっているのだから、同じ志をもつ仲間でもある。――周兄はこの神のような盗人も、喜喪鬼の羅刹掌でやられたと思いますか?」
鄧寛と高小怜が視線を交わす。周子舒と温客行は知らないふりをして、茫然とした顔をしてみせた。曹蔚寧がさっそく尋ねる。
「『も』? 趙家荘の外で鬼谷の人が暴れたようだと聞きましたが、もしかして……」
高小怜が答えた。
「曹少俠はご存知ないでしょうが、先日太湖趙家荘から連絡がありました。趙家荘を訪れていた断剣山荘の穆雲歌が、この羅刹掌で亡くなったそうです。鬼谷の悪鬼衆は、本当に悪事の限りを尽くし、こんなところにまでのさばっている」
ここは洞庭からもうそれほど遠くない。言わずもがな、一日程度の道程で、翌日にはもう、あの高大侠の領地と言えるところだった。あの娘が本当に正義のために義憤にかられていたのか、それとも自分の父親の領地に侵入されたのを不快に思っていたのかはわからない。
いずれにしても、鄧寛と曹蔚寧は無意識に頷き、賛同した。
「間違いない」
「まさしく」
当時、武林大同盟の時代には、合わせて三つの「山河令」があった。それは徳の高い重鎮が持ち、大きな災害や困難がある時にだけ使用できる。三つの「山河令」が集まった時、英雄大会が開催され、天下の豪傑を広く招き、共同でこれを図ることができたのだ。今ではこの三つの「山河令」は、一つは「鉄判官」の高崇の手にあり、一つは少林寺にあり、そしてもう一つは、長年世情に無関心な長明山の古僧の手にあると言われていた。
意外にも、今回の全ての目標が鬼谷へと向けられた動乱が、不老不死を修め、俗世のことには関心を持たなかった古僧まで動かしたのだ。
鄧寛と曹蔚寧は相談し、また他の者とも話し合い、馬車を雇うことに決めた。方不知の遺体を高崇のところに夜通しで運ぶためだ。時間がかかりすぎて状況が悪化することを避けなければならない。
曹蔚寧と鄧寛はほとんど一目で意気投合し、周子舒は冷ややかに傍観していた。あの高崇の人柄がどうかはともかく、弟子や娘への教育は悪くない。高小怜は傍らについていたが、時々差し挟む言葉は、年若い女の子にしては、話し方や態度もとても礼儀正しかった。彼女と顧湘は同じ年ごろだが、全く騒ぐことなく、我がままでもなく、節度のある態度で接してくれている。
温客行はふとため息をついて、感慨深く言った。
「我が家の阿湘が高さんのような人柄であれば、私は死んでも安心して目を閉じることができるのに 」
高小怜は振り返り、温和で礼儀正しく、微笑んだ。
「温大哥はお世辞がうまいですね」
周子舒はくすっと笑って、低い声で言った。
「高さんは高大侠の娘さんですから。顧湘は……本当はいい子なんだけど、上に立つ者が正しくないと下の者も悪くなるんだよ」
温客行はまじめな顔で言った。
「阿絮、高さんは素敵だと、私は素直に言っただけなんだから、君は嫉妬して、焼きもちを焼く必要はない……」
高小怜はすぐにとても気まずそうに彼ら二人を見た。急いで数歩歩き、鄧寛と曹蔚寧に追いつく。周子舒と温客行は後方においていかれた。
周子舒は軽く笑い、声を落とした。
「温兄、わからないことがあるんだが――私たちが中に入った時、なぜ方不知の死体は衣が乱れていたんだ? 私の知る限り、あの方兄は日の出とともに働き、日没とともに休むような人ではない」
温客行は手を伸ばしてあごを持ち上げ、しばらく考えていた。
「君が言いたいのは、喜喪鬼が方不知のことを気に入って、彼と不埒なことをしようとしたが、必死に抵抗されて、うまくいかず、怒って殺したということか?」
言って温客行は首を振り、ため息をつく。
「本当に古来より、美人は薄命だ」
周子舒が表情を消して、言った。
「温兄は本当に見識があるな。私は、犯人が方不知が持っていた何かを殺してから探そうとしたのかと思っていた」
温客行はしばらく咳き込み、調子を合わせて頷いた。
「それも一理ある」
顔を横に向けると、周子舒が意味ありげに自分を見ているのが見えた。周子舒がただ尋ねてくる。
「温兄の身から、あの日、財布以外に何かなくなったものはないのか?」
温客行は彼の目をまっすぐ見て、率直に答えた。
「ある。銀銭はすべて財布の中にあったが、瑠璃甲だけがなくなっていた」
周子舒の顔から、だんだん笑顔が消えていった。その目は氷水で洗ったかのように、暗くて冷たかったが、温客行はそれに気づかない様子で、まだにこにこと笑っていた。
しばらくして、周子舒がやっと低い声で言う。
「温善人、お前は伯仁を殺していない。だが伯仁はお前のせいで死んだ。これはどういうことだ?」
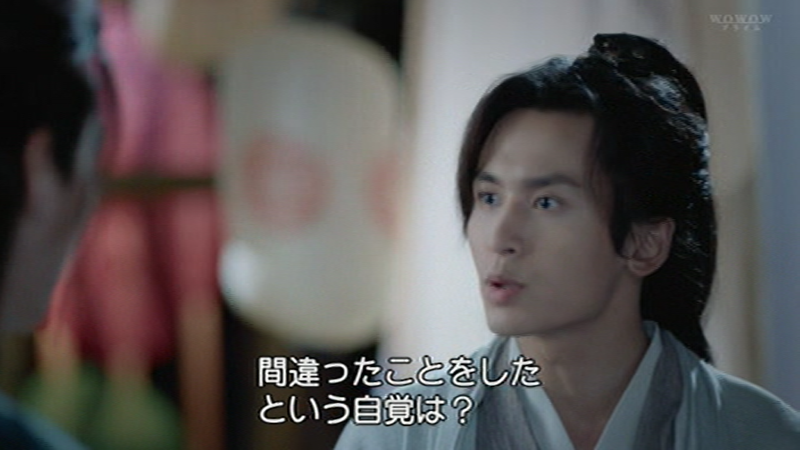
画像引用元:©Youku Information Technology (Beijing) Co.,Ltd.

温客行は黙っていた。ちょうどその時、前方にいた曹蔚寧と鄧寛が、周子舒が体調不良のようだという話に触れていた。鄧寛が周子舒を振り返り、深夜に道を進むことができるか、馬車を調達する必要があるかを聞こうとしたが、ちらりと見ただけで、二人の間の雰囲気が少し異常だと気がついた。
温客行の顔から笑みが消え、周子舒の目は言葉では言い表せない、謎めいた輝きを放っているように見える。鄧寛は不思議に思い、尋ねようとしたその時、温客行が突然微笑んだかと思うと、稲妻のように素早く周子舒の顎をつかみ、頭を傾けて口づけをした。
鄧寛はそれを見て呆然と立ち尽くしていたが、さすがに大家の風格で我に返ると、大きく頭を振って平静を装い、同じく呆然としていた高小怜と曹蔚寧に向かって言った。
「ならば……こうなったからには、私たち四人は一足先……一足先に行くとしよう……」
残念ながら、気を抜くと人員の数え方さえ間違えてしまう。
三人が振り返る勇気もなく逃げ出した後、周子舒はようやく温客行の制止から逃れ、彼の腹部を強く殴り、表情を凍らせた。
「温兄、この冗談は全く笑えない」
温客行は腹を押さえて屈みこみ、人を少し不快にさせるような笑みを浮かべながら、低い声で言った。
「私は伯仁を殺していないのに、伯仁が死んだのは私のせいだと? 阿絮、君は勘違いしているのでは?」
周子舒は冷たい目で温客行をじっと見つめていた。

画像引用元:©Youku Information Technology (Beijing) Co.,Ltd.
なかなか…。該当箇所の画像を探し出すのに苦心す(笑)
温客行はゆっくりと腰をまっすぐにすると、真夜中の静かな通りで、ため息のように低い声で言った。
「瑠璃甲には、至高の武功や敵国の宝物を手に入れる術があるかもしれない。誰がそれを欲しがらないだろうか?」
彼は黙って口元を曲げたが、その目尻には笑い皺がなかった。
「あの方不知はとるに足らない輩で、全て自分の利己的な欲望に基づいて行動している。何に対しても見た目が重要で、人の命を救うためのお金でさえも気にかけず、ただすぐに奪うだけだ。彼は欲しくないのか? あの喜喪鬼は、悪事を多く働いて、追い詰められて鬼谷に入った。何年もの間、人でもなく、鬼でもないように生きてきたのに、彼は欲しくないのか? 君は欲しくないとでも? 君が徳や善行を語るのは、黄泉へ行った時に、過去に犯した悪事を裁く、十八層の地獄が待っていることを恐れているだけだからだ。では聞くが、もしも君を天下無敵にする、そのようなものがあるなら、真夜中に鬼が扉を叩いても怖くなくなるものがあったら、君は欲しくないか?」
周子舒は非常にゆっくりと首を振り、鼻で笑った。
「私は元々、真夜中に鬼が扉を叩いても怖くない」
彼は言葉を投げかけた後、彼を見ようともせず、大股で前に歩いて行った。
温客行は暗く曇った表情で、しばらく彼の背中を見つめていたが、突然また笑い出した。
「周聖人、金木犀の酒は本当においしいね」
周子舒は聞こえないふりをしようとしたが、思わず袖をあげて激しく口元を拭い、心の中で罵った。
(温客行、この野郎!)
