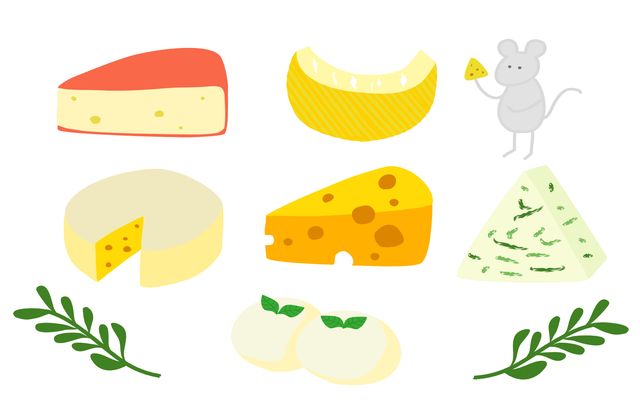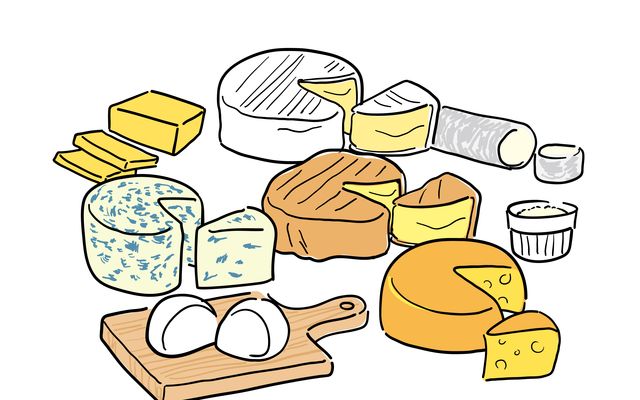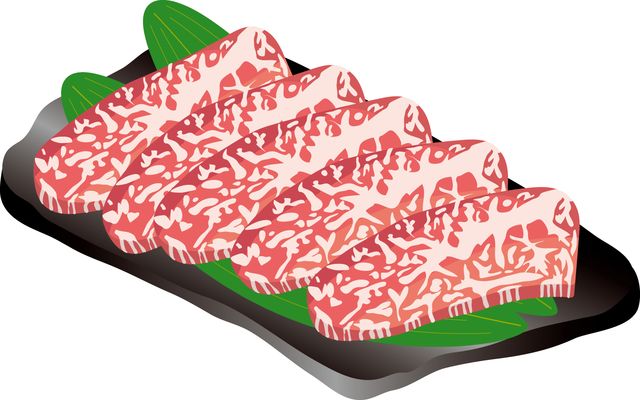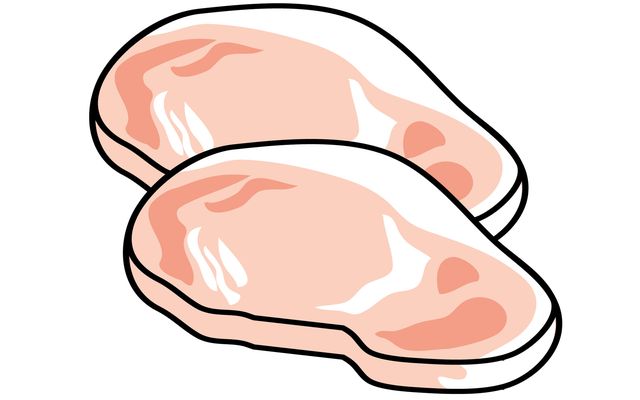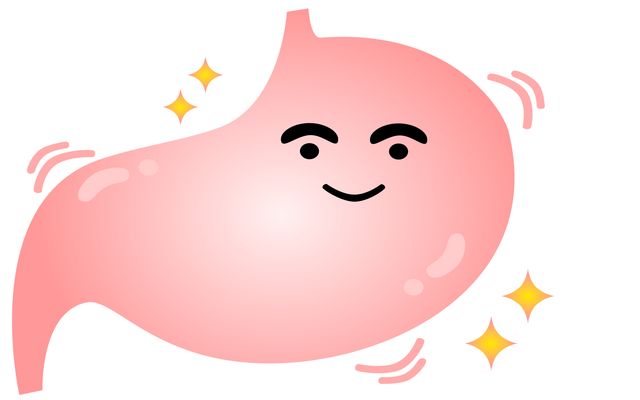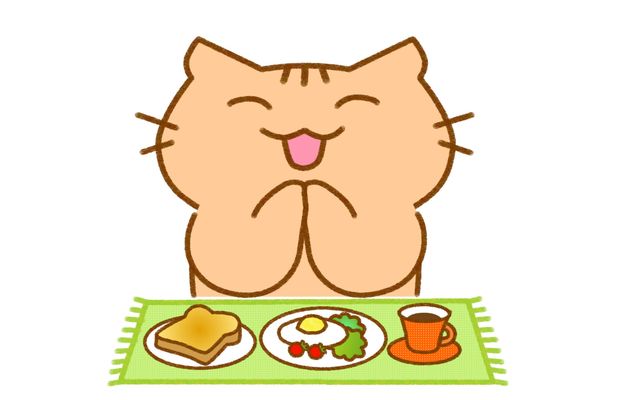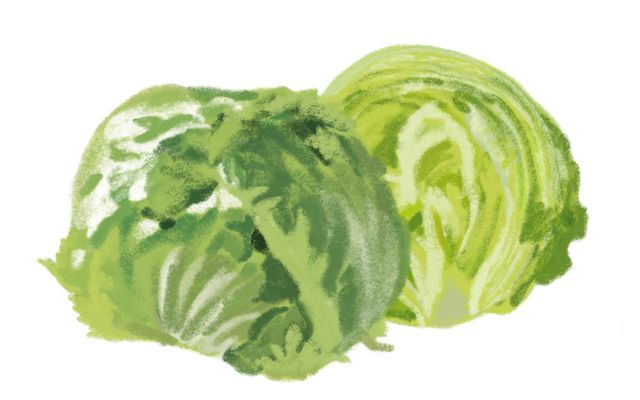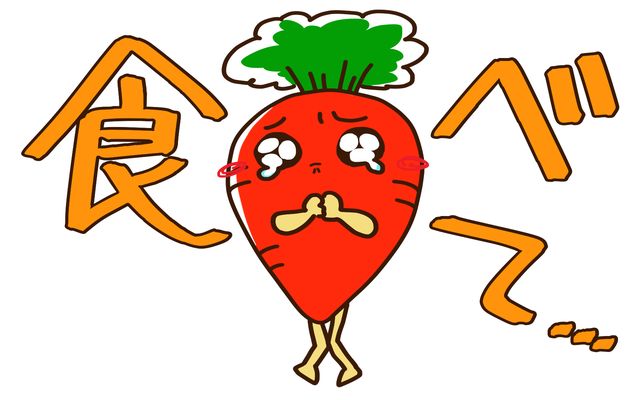健康づくりやダイエットの一環として、炭水化物(糖質)の量を適正範囲に収めようとしている方は多いのではないでしょうか?
米やパン、麺類などの主食は意識していても、普段よく食べるものから、知らないうちに炭水化物を摂りすぎている事があると言われてらどうします。
せっかく頑張ってるのに知らない内に、我慢してた以上炭水化物を摂ってしまっていたら。
今回は炭水化物の過剰になりやすい食べ物の例をご紹介します。
意外と知らない 主食は3食とっても過剰にならない!

米やパン、麺類などの主食は、適量であれば3食とっても炭水化物の過剰になる心配はありません。
主食は私たちのカラダや脳の大切なエネルギー源となるため、なるべく減らさずに毎食しっかり食べたいもの。気をつけたいのは、主食以外の食べ物です。
もし「主食を減らそうかな?」と考える方がいたら、以下の食べ物をとりすぎていないか、まずは確認してみてはいかがでしょうか。
炭水化物に気をつけたい食べ物・飲み物
甘いジュースや砂糖入りコーヒーなどの飲み物や、洋菓子や和菓子、菓子パンなどの菓子類は、イメージの通り炭水化物を摂りすぎやすい食べ物です。
気を付けているかも多いと思います。
それ以外にも、体に良いと思っているものが実は炭水化物が多かった……などというものもあります。
あくまで一例ではありますが、7つご紹介します。
炭水化物制限時気を付けたい食べ物1.スポーツドリンク
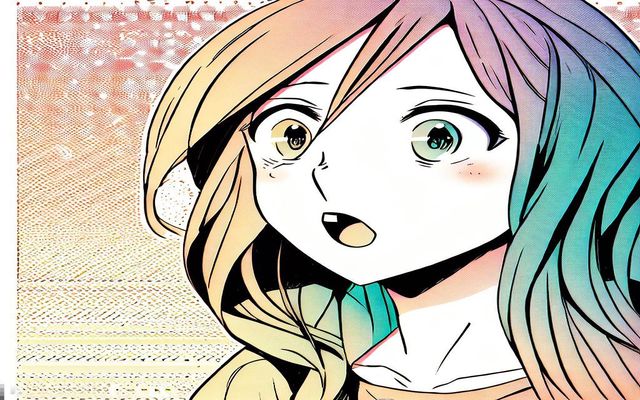
スポーツドリンクは約5%の炭水化物が含まれ、500mlのペットボトルでは25.5gの炭水化物を摂る計算になります。これは砂糖に換算すると、大さじ3杯弱の量です。
熱中症対策として、大量の汗をかいたときはスポーツドリンクや経口補水液の摂取が勧められますが、室内など汗をさほどかかない状況で喉が渇いたときに水分補給代わりに飲むのは炭水化物の摂りすぎにつながりかねません。
普段の水分補給にスポーツドリンクをよく飲む方は注意が必要です。
炭水化物制限時気を付けたい食べ物2.栄養ドリンク・エナジードリンク
もうひとがんばりしたいときなど、栄養ドリンクやエナジードリンクを頼る方もいるかもしれませんが、中にはジュースと同じくらいの炭水化物が含まれるものもあります。
量が多いタイプのエナジードリンクは、大さじ3~5杯もの砂糖をとる計算になるものもあります。
どうしても取り入れたいときは、糖質オフタイプなどを選ぶと良いでしょう。
炭水化物制限時気を付けたい食べ物3.果実酢

健康効果が期待される果実酢。
意外とりんご酢やザクロ酢、ぶどう酢などの果実酢は、酸味をやわらげるために砂糖などが使われているものが多くあるんです。
酢にはさまざまな健康効果が期待されていますが、飲みすぎは控え、選ぶときは炭水化物の量をチェックするのも大切です。
炭水化物制限時気を付けたい食べ物4.野菜ジュース
野菜不足の方は野菜ジュースを上手に活用するのも方法のひとつではありますが、果実酢同様、意外と思われるかもしれませんが炭水化物が含まれています。
野菜100%のタイプでも、にんじんやかぼちゃなど、甘みのある野菜が使われていることが理由のひとつとして考えられます。
炭水化物の量が気になるときは、なるべく食べ物から野菜を取るのが基本となります。
炭水化物制限時気を付けたい食べ物5.乳酸菌飲料

乳酸菌飲料は100ml程度と量が少ないものから、500mlサイズのペットボトルのものまでさまざまですが、これもジュースと同じように炭水化物が含まれます。
もし量が少なくても、「チリも積もれば山となる」で、ほかの甘い飲み物をとっていれば、知らなうちに炭水化物を摂りすぎているかもしれませんね。
炭水化物制限時気を付けたい食べ物6.加糖ヨーグルト
腸内環境を整えるのに役立つヨーグルトですが、加糖タイプを選んでいる方は要注意です。
なるべくプレーンタイプを選び、甘さを足したいときはプレーンヨーグルトをフルーツと一緒に食べるなどの工夫を取り入れてみてはいかがでしょうか。
炭水化物制限時気を付けたい食べ物7.かぼちゃ・芋類
かぼちゃや芋類は、野菜の中でも炭水化物が多く、主食に分類されることもあります。
食物繊維やビタミン、ミネラルの良い補給源ではありますが、ほかの野菜のように「たっぷり」食べると炭水化物を摂りすぎてしまいます。
先に取り上げた野菜ジュースに炭水化物が多くなる要因の一つなんです。

他にも以下のようなものにも意外と炭水化物が含まれています。
- 果物:果物には自然に含まれる糖質が含まれています。特にドライフルーツは、糖分を濃縮しているため、同量の新鮮な果物よりも炭水化物が多く含まれています。
- 豆類:豆類は、良質のたんぱく質や食物繊維を含むため、健康的な食品として知られていますが、同時に炭水化物の多い食品でもあります。特に、豆腐、納豆、枝豆などが炭水化物の多い食品として挙げられます。
- ナッツ類:アーモンド、ピスタチオ、カシューナッツなどのナッツ類にも炭水化物が含まれています。ただし、同時にタンパク質や良質の脂質も含まれているため、栄養バランスの良い食品としても知られています。
最後に
これらの中に、普段よくとっているものはありましたか?
食品に含まれる炭水化物の量は、品種や栽培方法、加工方法、調理法などによって異なることがあります。
したがって、栄養成分表を確認することが重要です。
また、個人的な健康状態や栄養摂取目標に応じて、炭水化物を含む食品を選択する量や頻度を調整する必要があります。
炭水化物の摂りすぎが気になる方は、主食を減らす前に一度、習慣的に食べているものを振り返ってみてはいかがでしょうか。