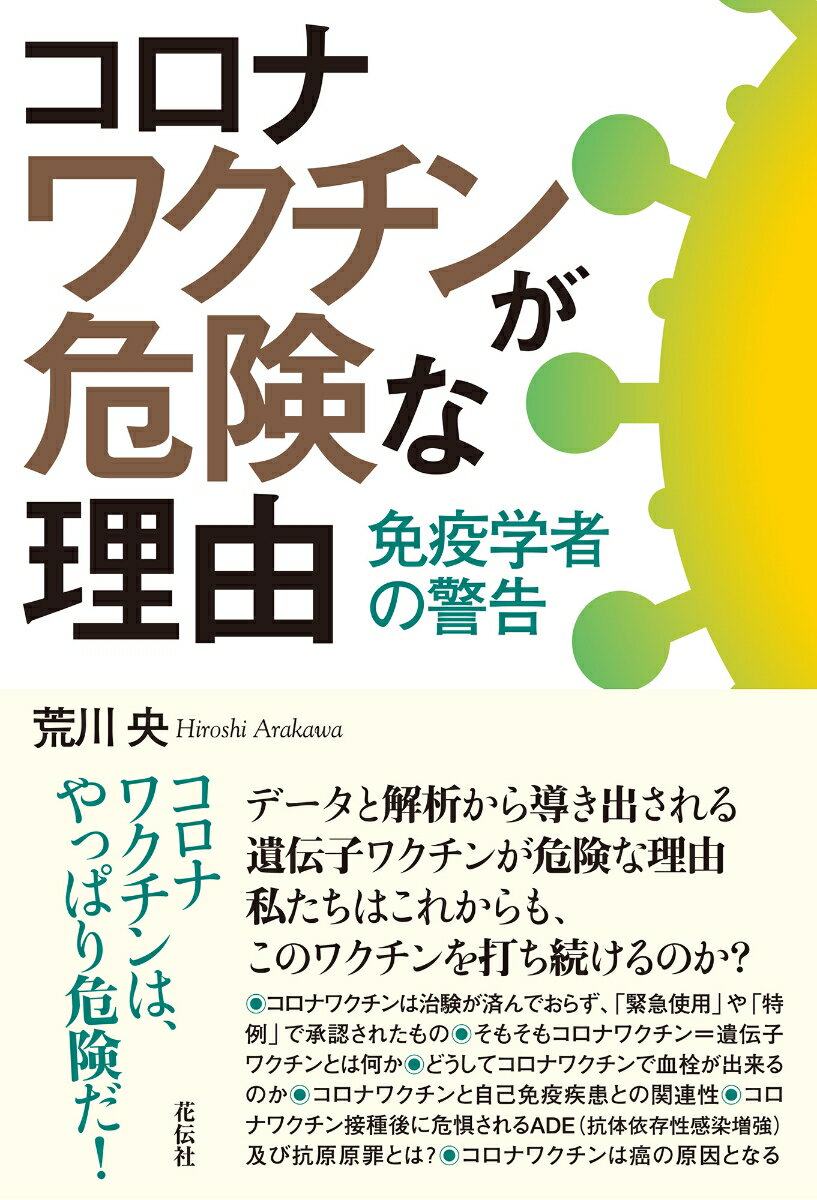レプリコンワクチンについて
Xのスペースにて、華さんが、
有識者を招いての討論の様子を
配信されました。
及川幸久氏が、荒川央先生に
質問している場面を抜粋して
文字起こししました。
【レプリコンスペース】記録的な参加者数のスペースとなりました。皆様、ありがとうございました🙏。感想や先生方へのコメントをお寄せ下さい。
— Trilliana 華 (@Trilliana_x) December 9, 2023
👉音声が聞けなかった方、大人数すぎて重いスペースだったからでは?と思います。こちらからアーカイブをぜひお聴きください。https://t.co/aqwNwMkb5n
新しいmRNAワクチンが
開発されたという事です。
日本ではその名前が、『レプリコンワクチン』
と呼んでいます。この呼び方(名前)は、
日本だけのようです。
英語ではSelf-amplifying RNA
自己増殖型mRNA
ということで、聞いただけで、
恐怖を感じる名前です。
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7911542/
このワクチンを承認して、使用許可したのは、
この日本が初めてなんです!
まずは、荒川先生から注意点を、
お伺いしたいと思います。
13:50~
荒川:
余談ですが、日本語のワクチンは、
可愛い響きですが、英語では
VACCHINEで、怖いイメージ。
だから、日本人はワクチンに対して
抵抗感があまりないのかな?
14:50~
荒川先生:
ファイザーやモデルナの
コロナワクチンは、
シュードウリジンメッセンジャーRNA
を使っています。
本来の細胞内のmRNAは、
壊れやすいものなんですよ。
壊れやすいものなら、
壊れないようにすればよい
というのが、
シュードウリジン化mRNAの
発想であり、手法であるんです。
別の手法として、
mRNAが壊れやすいのであれば、
増やせば良いんじゃないか?
というのが、
レプリコンワクチンの手法です。
このレプリコンワクチンだと
RNAの中に、
抗原遺伝子に加えて、
RNAを増やす為の酵素も入っている。
正確には、酵素複合体で、
4つのタンパクの複合体なんですが、
それが、レプリカする酵素、
複製酵素という意味です。
基本的な生物学的な話をすると、
分子生物学的な基本の概念、
セントラルドグマというのが、
あるんです。
細胞を持っている生物は
バクテリアでも、
昆虫でも動物でも、
植物でもヒトでも、
DNAがゲノムなんです。
セントラルドグマだったら、
DNAからDNAが作れる。
RNAは、DNAから作る。
タンパクは、RNAの情報を使う。
ということで、RNAからは、
RNAは、作れないんですよ!
しかし、このセントラルドグマに
例外がある事が、分かってきました。
それが、ウイルスであり、
ウイルスの中に、RNAのゲノムを
持つヤツがあるんですよ!
セントラルドグマ(の概念)だったら、
RNAから、RNAを作れないから、
一体どうなっているのか?
RNAウイルスのひとつのタイプは
「レトロウイルス」
と呼ばれるタイプです。
これを英語で、表すと、
retroviruses
日本語にすると、
「逆転写酵素を持つ癌ウイルス」
名前の略語なんです。
このタイプのRNAウイルスは、
RNAをDNAに逆転写して、
逆転写したDNAを
ホスト(宿主)のゲノムに
取り込ませるんですよ。
そこから転写してRNAを作る。
しかも、これは、動物には
よくあるタイプの癌ウイルスで、
ゲノムをいじるわ、
癌にさせるは、
ろくでもない理屈なんです。
もうひとつのタイプは、RNAから、
直接RNAを作れる
RNAウイルスなんです。
実はこのようなRNAウイルス
というのは、
結構ありふれたウイルスで、
身の回りにある
インフルエンザウイルスが、
RNAウイルスなんですよ。
コロナウイルスも
RNAウイルスです。
このようなウイルスは細胞がもともと
持ってないような酵素を持っている。
これが、先ほどお話した、
RNA依存性RNAレプリカーゼ
なんです。
そうです。これが、
RNAからRNAを複製させる酵素
なんです。
レプリコンワクチンに
使われているのは、
αウイルスと呼ばれる
ウイルスのグループの
ベネズエラウマ脳炎ウイルス(VEEV)
というウイルスです。
https://medical.jiji.com/medical/023-1010-01
(中略)
ウイルスの殻の遺伝子を取り除いて、
抗原遺伝子に入れたのが、
レプリコンワクチン。
自己増殖型メッセンジャーRNAワクチン
なんです。
殻の遺伝子を取って、
他のに入れ替えたので、
構造は、割とウイルスのゲノムは
そのままで、
簡易型人工ウイルス
みたいなものなんです。
殻を持って、自由に外に行き来は、
できないんだけど、
細胞の中で複製したものが、
変わっていく段階で、
どうなるか分からない。
もうひとつ予備的な基礎知識として、
●何故?mRNAが不安定なのか?
必要な時に必要なだけ、
タンパクを作る為、わざとRNAは、
作った端から壊すような仕組み
に細胞を使っているんですよ。
例えば、僕等の身体だったら、
色々な臓器がある。
心臓、脳、皮膚、肝臓、腎臓、
胃、膵臓、目、
それらの細胞が違った働きを
持っているのは、
違ったタンパクを持っている
からなんですよ。
細胞毎に違ったタンパクを
持っているというのは、
細胞毎に違った遺伝子の
mRNAを作っている。
作った後は、壊さないと、
どれだけタンパクを
作り続けるか分からないから、
基本的にはmRNAは、
作った先からわざと壊すような
仕組みになっているんです。
ということで、
壊れないRNAとか、
増えるRNAというのは、
ヒト本来のmRNAとは、
似て非なるもの。
本来の人のmRNAと
違うものを、
体内に注入したら、
どうなるか
分からない
ということなんです!
ヒトだったら、ゲノムは、
23×2本染色体があって
3×10の9乗の文字列なんですよ。
複製する時に間違いが
起こる事があるので、
修正するような修復機構が
普通に僕等は、
使っているんです。
でも、RNAには、基本的には、
修復機構がないんですよ。
RNAウイルスの中で、
最低限の修復機構を
持っているものもあるんです。
複製の過程で、
間違った塩基を取りこんだと
気付いたらその1塩基だけ、
削って、更生するという
機能を持っている酵素も
あるんですけど、
コロナウイルスのRNA酵素はそれを、
持っているんですが、
アルファウイルスのレプリカには、
その更生機能が無い。
(中略)
RNAウイルスは特に、
間違いが起こりやすい。
(複製の過程で間違った塩基を
取り込みやすい)
基本的な事をお話しすると、
DNAでもRNAでも、
文字列は4種類なんです。
ウイルスの情報の解析は
デジタルで行っていますが、
問題は、
アナログで作っているんですよ。
小さな小さなナノスケールより、
もっと小さな部品を、
ひとつづつ繋げていく。
しかも、活性酸素分子が
あっただけで、壊れるような
分子で・・・・
アナログで、デジタルコピー
のようなことをするので、
複製する度にちょっとずつ、
間違うんですよ。
そうです。
このアルファウイルスのゲノムは、
しょっちゅう変わるんですよ。
しかも、質が悪い事に、
しょっちゅう間違う事を、
ウイルスの方でも分かっているから、
組み替えるのも早いんですよ。
例えば端っこの1個を
間違ったウイルスのゲノムが
あるとすると、
2つ壊れているんだけど、
工作が得意な人だったら、
ジャンク品を2つ買ってきて、
組み立てて、ちゃんと
動かせるようにする
じゃないですか?
変異率が高い。
組み換え率が高い。
という最悪のコンビで、
これは、人工進化の実験
をするのに、ちょうど良いんですよ!
変異種が出来て、しかも、
変異種が出来るのを、
促進する仕組みすら
持っている。
進化の過程は、基本原理は簡単で、
変異と選択なんですよ。
少しずつ変わっていく。
その中で、環境に適応したものが、
競争により勝って生き残る。
弱肉強食とは違いますが、
少しずつ競争に勝つ個体が後で
有利になり最終的に勝ち残るんです。
これは、
機能獲得実験
による、
人工進化と同じ事を
やっているんですよ!
選択は自然にかかるんですよ!
増やせ増やせ!という選択は、
デフォルトで入っているし、
それを免疫で排除しようとするが、
免疫に対抗して生き残ろうとする
選択圧も、かかるんです。
人工進化の実験をやるのであれば、
大概は、培養細胞を使ったり、
動物実験をしたりするのですが、
まさかそのヒトの本体で、
ヒトに感染しやすい
ようなものを、
人工進化するような
機能獲得実験をするとは、
倫理的に許可が
降りないような
ものを、
承認をして、
始めてしまった!
(つづく)➡次の記事へ