なかなか一般消費者には伝わらず、ともすれば、
●「安かろう、悪かろう」の印象を与える。
●バーゲンハンターを育成し、顧客育成が出来ない
というような印象があった。
それをうまくまとめていたのが、
TRENDYヒット研究所】◆西友「KY」戦略の裏側(1)~価格コミュニケーションとは?
まず、EDLPと特売の違いを簡単に。
特売
ある商品に通常価格を設定し、ある特定の期間中、
通常価格から割引いた価格を提示することにより買い得感を演出するというメカニクス
・通常価格を「品質シグナル」
・割引価格を「価格シグナル」
として、品質・価格両方をコミュニケーション
要は
 一部の商品の価格を短い期間内に大幅に上げ下げし
一部の商品の価格を短い期間内に大幅に上げ下げし  その他の商品とのミックスにより利益の帳尻を合わす
その他の商品とのミックスにより利益の帳尻を合わす それによって見えにくオペレーションコストがかかっている。
 チラシを印刷し、折り込み配布するコスト(プロモーション経費)
チラシを印刷し、折り込み配布するコスト(プロモーション経費)=チラシのデザイン費用及び印刷費用
=新聞折り込みの費用
 チラシ記載商品を大量陳列したり、ゴンドラエンドに積んだりするコスト
チラシ記載商品を大量陳列したり、ゴンドラエンドに積んだりするコスト=店内で商品を移動し、積み上げる人件費
 大量陳列へのPOP貼り付けコスト(資材費(企業によっては販促費))
大量陳列へのPOP貼り付けコスト(資材費(企業によっては販促費))=POP制作及び店内貼付するための人件費
=印刷費用
 特売にかかる発注量の上方修正コスト
特売にかかる発注量の上方修正コスト =売り上げ予測・発注量のイレギュラー対応のための人件費
 対象商品の価格データ修正コスト
対象商品の価格データ修正コスト =システム対応するための人件費
 特売期間終了時、これらを元に戻すコスト
特売期間終了時、これらを元に戻すコスト =上記 b ~ e を原状復帰するための工程
それと実は対極するのがEDLP
EDRP
 商品全般について水準より安い値付け(特売のように 赤字覚悟の値付けではない)
商品全般について水準より安い値付け(特売のように 赤字覚悟の値付けではない)  それらの価格は、あまり変更しない
それらの価格は、あまり変更しない 特売で記載した見えないコストが発生しないので、店舗の運営コストが大きく低減。
ただし、この経費を下記につかう。
[1]オペレーションにコストをかけないぶん、魅力的な値付けが実現する
[2]魅力的な値付けをすることにより、売り上げが上がる
[3]売り上げが上がることにより販売量が増え、それに伴って
仕入れ量も増える
[4]仕入れ量が増えることにより、商品調達原価が下がる
[5]商品原価低減分を商品価格の引き下げに使う
[6]さらに魅力的な値付けが実現し、売り上げも上がる
[7][3]に戻る
このループ現象回すと、売り上げ拡大・仕入れ量拡大・価格競争力強化が順番に繰り返され、
ビジネスがどんどん拡大!
ただし、このループ現象を獲得するにはかなり大変。
[1]魅力的な値付けが実現すると[2] 売り上げが上がる の間に
「商品品質が高く、かつ安いお店である」という認知を獲得しなければ、ならない。
ちゃんと伝わらなければこのループ現象は起こらない。
まったくもって意味がないものになる…。
顧客に“伝わる”&“認識される”って非常に大変なことだと思います。
 価格認知を形成する
価格認知を形成する  しかしながら、品質認知は低下しないようにする
しかしながら、品質認知は低下しないようにする  価格認知とともに、Live betterの価値認知形成も促進する
価格認知とともに、Live betterの価値認知形成も促進する これをクリアしなければ無理…
そこでコミュニケーション戦略が重要となるわけです。
西友はすごいそれが上手。
安売りの多い小売業店が多い中、
「なんかいつも安いお店」っていう認識がちゃんと私の中にも
あります。
それってすごいことだなと。
もちろん、広告・販促・売り場とすべてが連携となって
やっと確立できるブランドイメージ。
それよりも前に、
このEDLPと特売の戦略を掛け違えている小売業態が多いように感じるのは
私の気のせいでしょうか?
今年もまだまだ景気回復ってわけにはいかないので
このあたりの違いをちゃんと理解しないと
小売業店はジリ貧になりそうな気もします。
買物欲マーケティング―「売る」を「買う」から考える/博報堂買物研究所
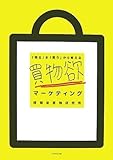
¥1,890
Amazon.co.jp