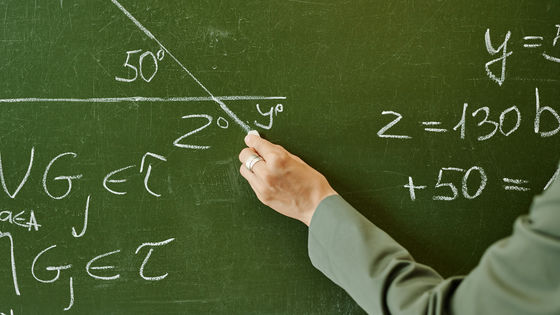中学受験の話
以下は2020年の開成中学入試の算数の問題です.
https://www.inter-edu.com/files/nyushi/2020/kaisei/kaisei-mat.pdf?1580609158
大問が4つ.これを60分で解く.一問平均15分.
合格点が何点かは知らないが,これを制限時間内に解けるのはそうとうの算数アスリートだ.
特に4番は難しい.
しかしながら,どれも結局はスピード勝負であって,時間さえかければいずれは満点にたどりつく.計算機使えば更に簡単だ.
結局は,速くミスをせずに解答する競争なのだ.特に3番など易しい問題も含んでいるので,ここでケアレスミスをしないことが難しい問題を解く事よりも重要になってくる.
現実の場面で計算機も使わずに紙と鉛筆だけでこれだけの速度で解く事を要求されることは無い.
これを小学生に鍛えさせることは,”競争”としての意味しかない.この能力が将来の役に立たないことは小学生は分かっているはずだ.
現実の大抵の職業ではもちろんのこと,数学者でさえもこのような能力は必要が無い.分刻みの時間制限競争などはありえないからだ.
中学受験の能力と大学受験の能力との違いを見ていこう.
国語や社会はほとんど同じと思われる.中学受験で国語・社会でトップクラスなら中高時代は全く勉強していなくても私大マーチくらいは勢いだけで受かってしまうだろう.
数学はどうか.
以下は2024年2月東京大学の入試の数学の問題である.(前期日程・理科)
数学は大問が6問ある.これを2時間半で解く.一問平均25分.
例年より易化したらしいが,開成中学の入試とは難しさが本質的に異なる.
開成中学の入試はロボットに解かせようとするのは易しい.方針をたてるのにひらめきは必要なく,ありきたりのアルゴリズム(手順)に従えば正解が出ることは目に見えている.
東大の問題も,少なくともこの年度に関してはどの問題も基本的な方針にそったアルゴリズムが正解を出力する.特に第1-5問はそうだ.
数学の論文で補題としてこれらの問題を解く必要が出てきたら多くの場合は”容易に”などと導出方法の詳細は省いてラフスケッチだけ(あるいは答えだけ)で次の目的へ急ぐだろう.数学者なら決まった手順だけで正解にたどり着くことは明らかだからだ.
第6問は(東進以外の)3予備校の評価だと”やや難”とあるが,第6問(2)は入試問題としてはかなり難問だと私は思う.(例年と比較したらもっと難しいものも出たことがあるというのが予備校の言い分なのだろう.あるいは(1)が易しいからか)東進ハイスクールのみ,第6問を難問と評価している.
実際,第6問(2)で以下の4つの模範解答を比べてみよう.
・代ゼミ
これは読売オンラインにも記載されている.
・駿台予備校
https://www2.sundai.ac.jp/sokuhou/2024/tky1_suu2_1.pdf
・河合塾
https://kaisoku.kawai-juku.ac.jp/nyushi/honshi/24/t01-21a.pdf
・東進
http://27.110.35.148/sokuho/data/2024/0l/m02/m0l2426.html#mtop
4予備校の中で一番簡潔で良いのは河合塾のものだろうと思う.
一番要領悪いのは代ゼミの解答だ.(2)だけで3ページもある。これでは解答欄に書ききれないだろう.しかも途中では<同様にして>と書いて一部を省略してさえいるので減点恐れてちゃんと書けばもっと長くなる。この解答者は解答を得るのにそうとう時間を使ったはずだ(それだけ時間かけたら試験には落ちる).
まあしかし,代ゼミ以外の3予備校の解答は似たものとしても,解答方針は複数立ちうる.どの方針で正解までたどり着くかどうか,たどり着いたとしても短く終わるか長くかかるかはある程度やってみなければ分からない.そういう意味で運の要素が入ってくるので難しい問題と言える.訓練と感で運の要素をある程度減らせるとしても無くすことはできない.
そういう意味では,開成中学の算数の問題よりも東大の数学の問題のほうが,真に難しい問題を含むことは間違いない.
まあGoogleDeepMindのチームが数学オリンピック問題を解くAI(AlphaGeometry)を開発しているそうなので,第6問(2)をAIが初見で解いてももはや不思議ではない.
第6問(2)以外はだいたい方針がたつ.全部で120点満点として第6問(2)の点数配分は10-15点程度だろう.合格するための時間配分からして馬鹿らしい.
よって,合格点をとる意味では,東大入試もやはりケアレスミスとスピードの勝負となる.
そういう意味では開成中入試と変わらないと言っても良い.
難しい問題を解く能力ではなく,易しい問題を速く正確に解く競争にすぎなく,AIで代替可能である.
代ゼミの模範解答を悪く言ったが,それは受験問題解答者としての話であって,大人として数学者としての能力が低いことは意味しない.受験生でもなければ、トリッキーな要領よい解答を瞬時に思いつく能力は必要なく,時間かけても着実に問題を追い詰める自信があれば,器用さは(試験中で無ければ)本質的ではない.未解決の問題を初めて解決するのが開拓者のする仕事で,出来上がった仕事を奇麗に整理するのは二流の仕事だったりもする.
もちろん模範解答を読んでも理解できないレベルなら話にならないが、制限時間内に紙と鉛筆で解ける人は、制限時間の2倍かけてネットも計算機も使って解ける人に対して、数学研究の場においてはアドバンテージは無いと言って良い。それを実力の差と呼ぶのであれば、メガネかけて解ける人は裸眼で解ける人より劣っている事になる。が、それが現実の場では差にならない事は明らかだ。
続き
(関連記事)