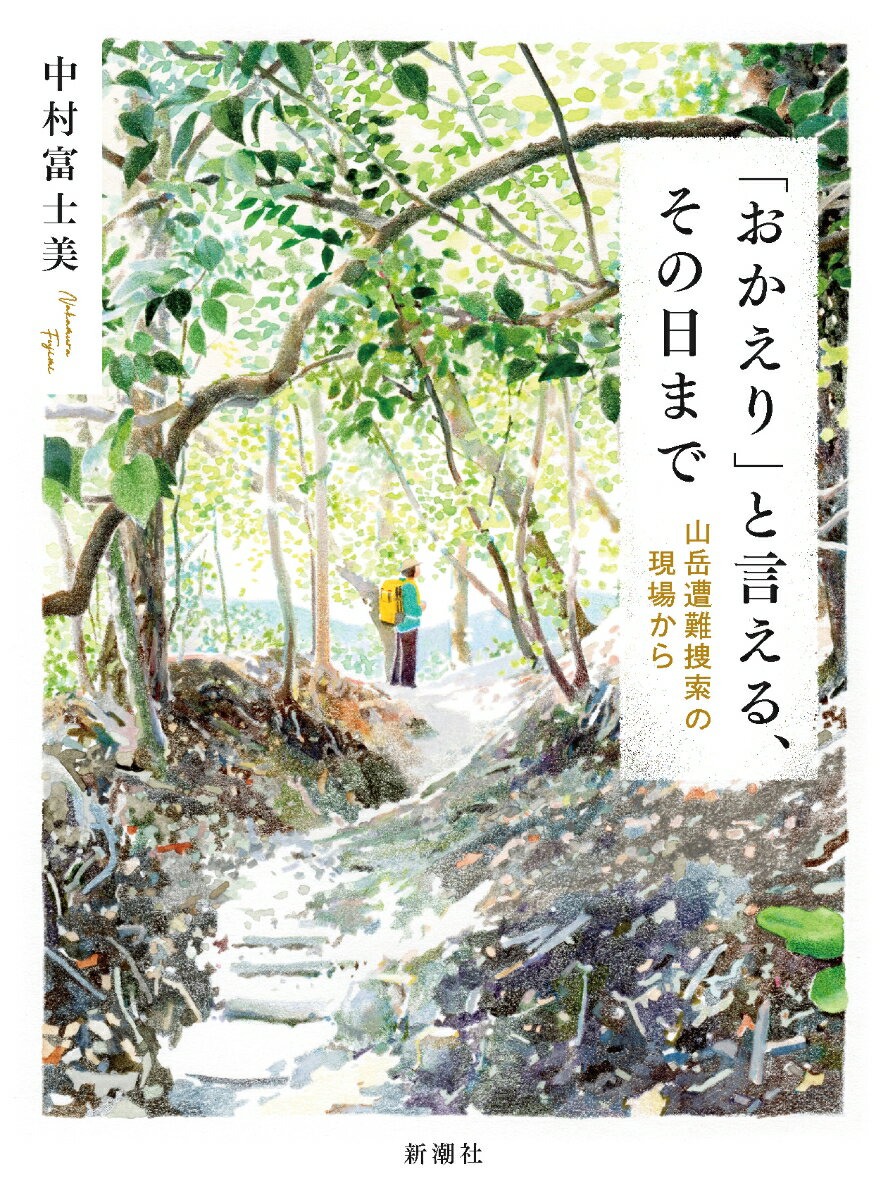その理由は
コロナ禍で
出かけるのを控えていた人たちが
再び登山を始めたものの
体力や技術が落ちているから……
などと言われてましたね。
私は50才を過ぎてから登山を始め
最初の頃は『登山は事故や怪我をする恐いものだから気をつけなくちゃ』
と思ってました。
数年たつと
『楽しい!もっと高い所に行きたい!もっと険しい所に行きたい!』
になってて
でも、更に5~6年たって
自分達が登山している際に
事故や怪我した方を見たりで……
体力の衰えてきた自分がトラブル起こしたら、みんなに迷惑がかかるな……と、グループ卒業
残りの人生は高尾山とかをゆるゆる登るつもりでいました。
でもね、低山こそ気をつけなくてはいけない部分もあるようです。
「おかえり」と言える、その日まで
山岳遭難捜索の現場から
「どうして、こんな身近な里山で大けがをするのだろう?」
登山スポットの近くの病院の救命救急センターで働く著者は、不思議に思っていた。
エベレストやマッターホルンで命を落とすニュースは見るけど
小学生が遠足で登るような山でなぜ?
著者は、山岳救助の現場に参加し
本格的に登山をする人たちには気づかない
初心者ハイカーの著者だからこそ気がつく
道迷いや迷ったときの進み方を考え
遭難者の発見をしていくようになる
著者 中村富士美さんが
遭難した家族に寄り添い、性格や行動パターンを想像して捜索していく推理はとても素晴らしいもので
そこに愛すら感じます。
自然の中を歩くのは大好きなので
まだまだ歩き続けたい。
でも、改めて
もしもの時に家族が困らないように
自分の行動予定を書いてから出かけよう。
山で迷ったら下に行かず上に行こう
(自分にできるか疑問だけど……)
と決めて本を閉じました。