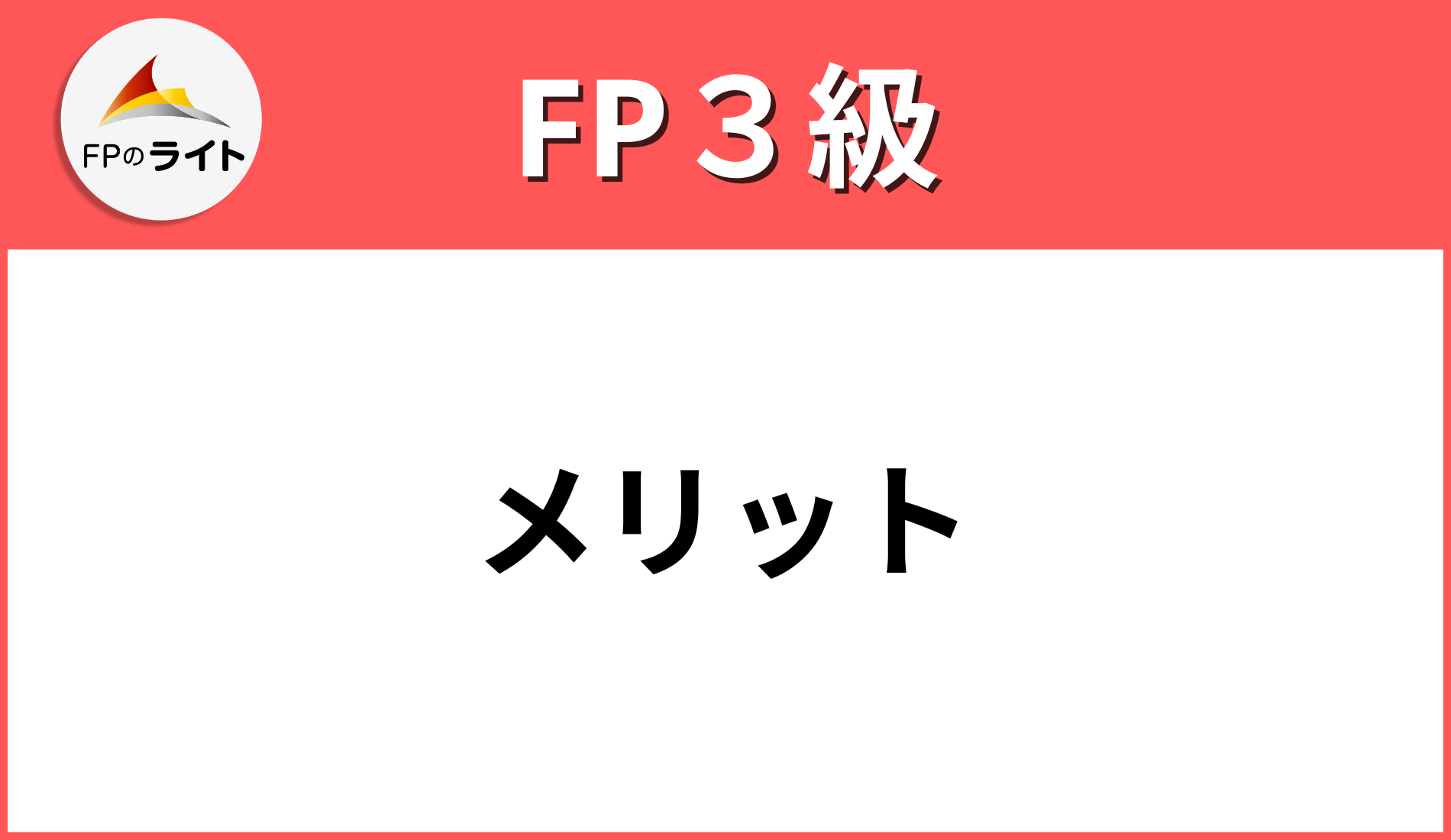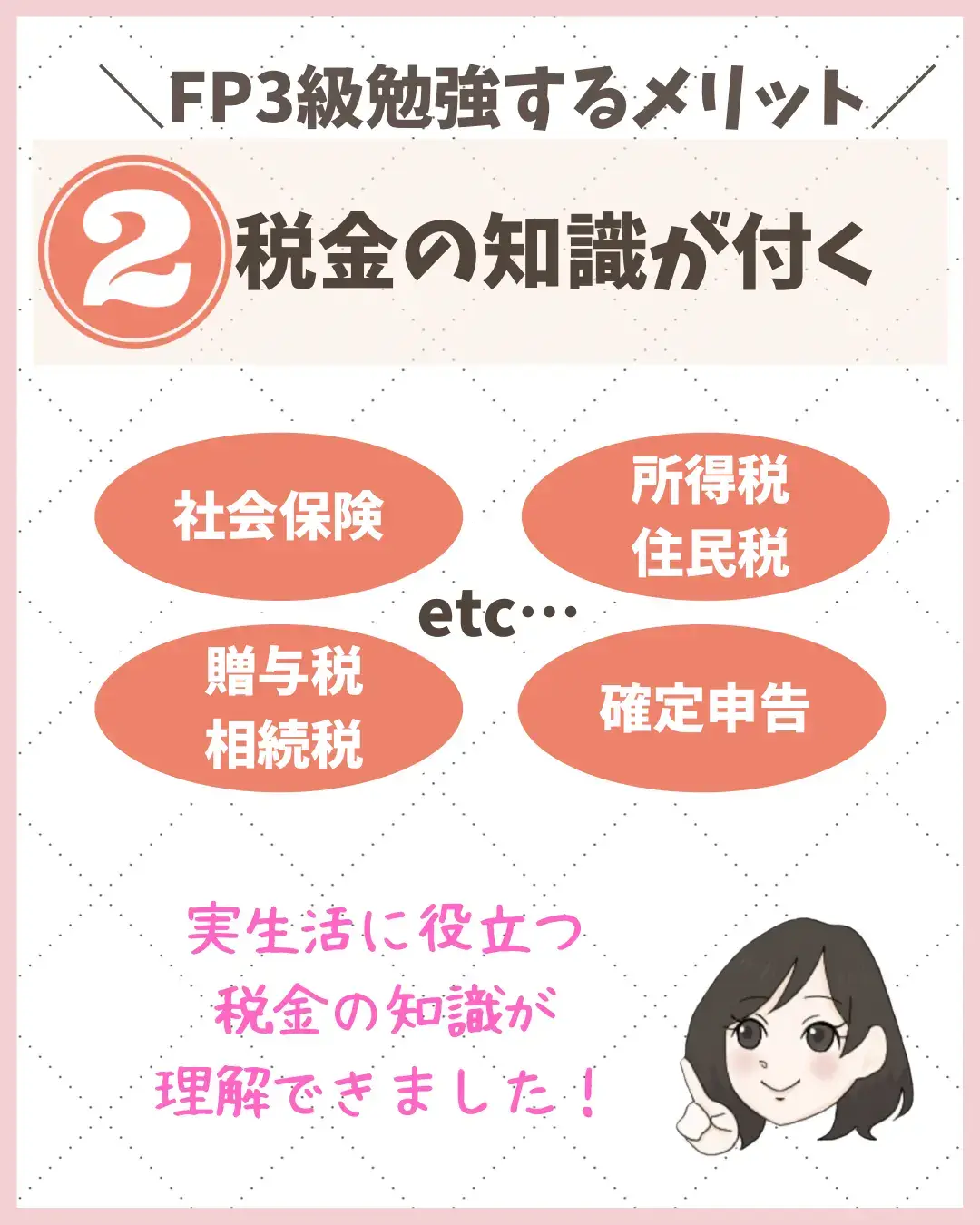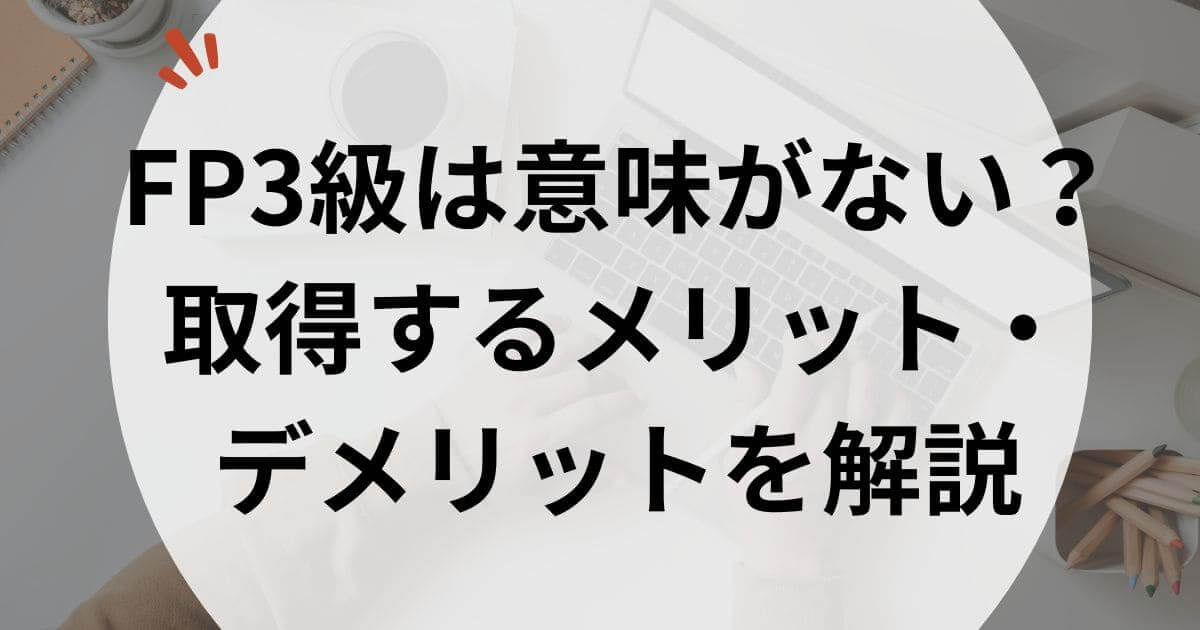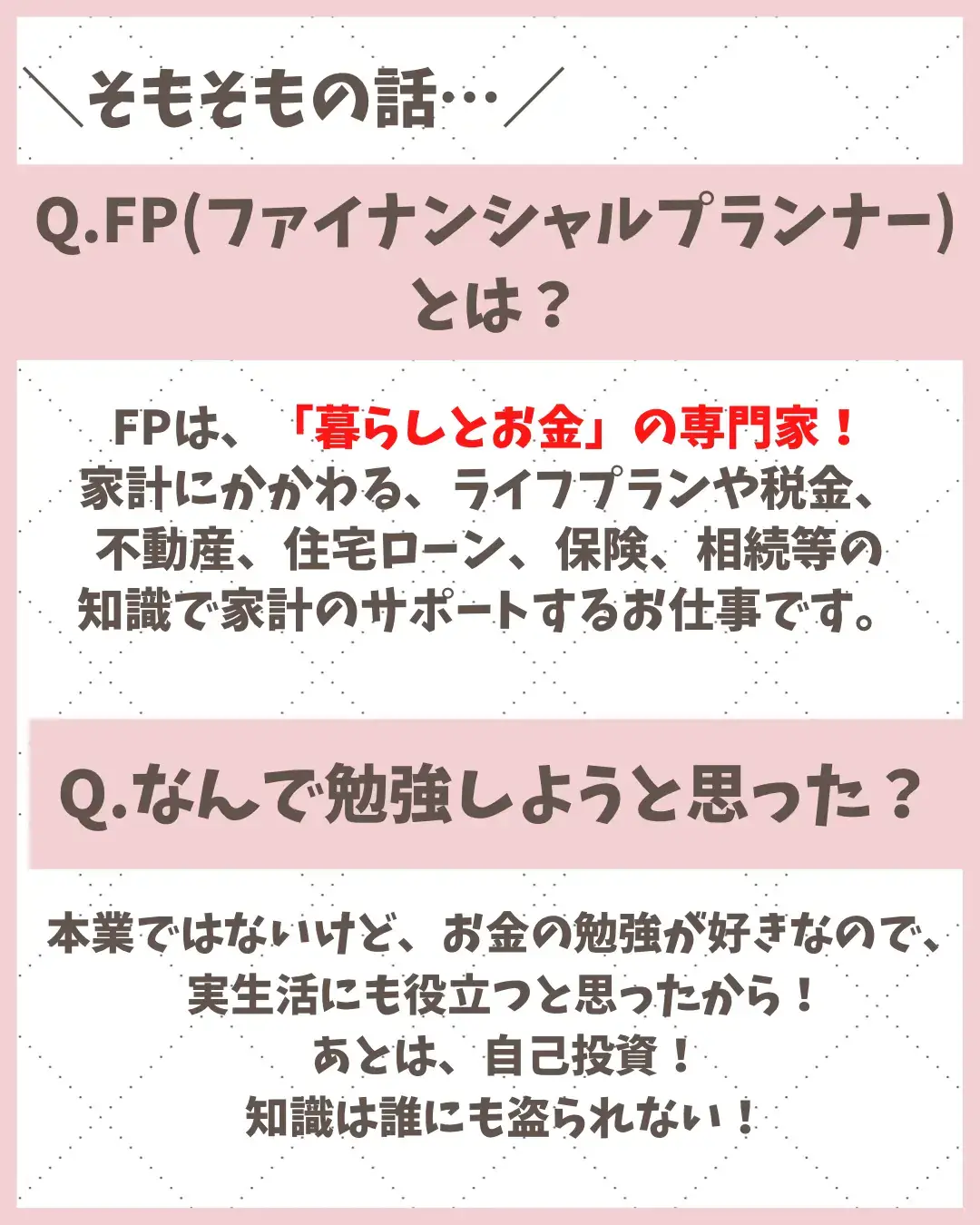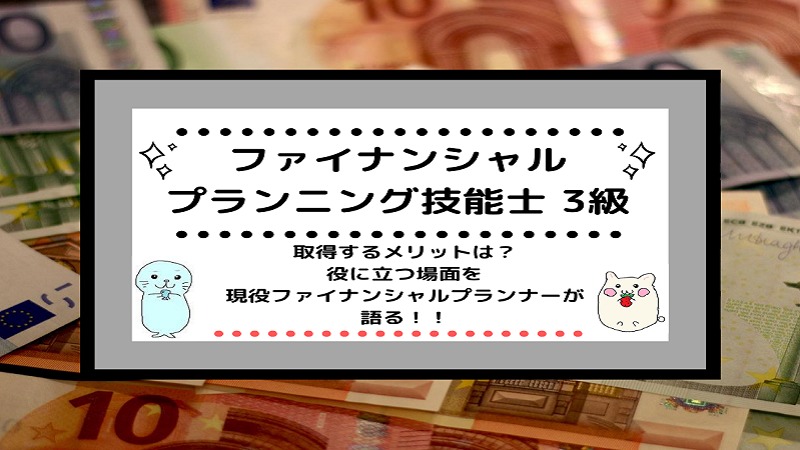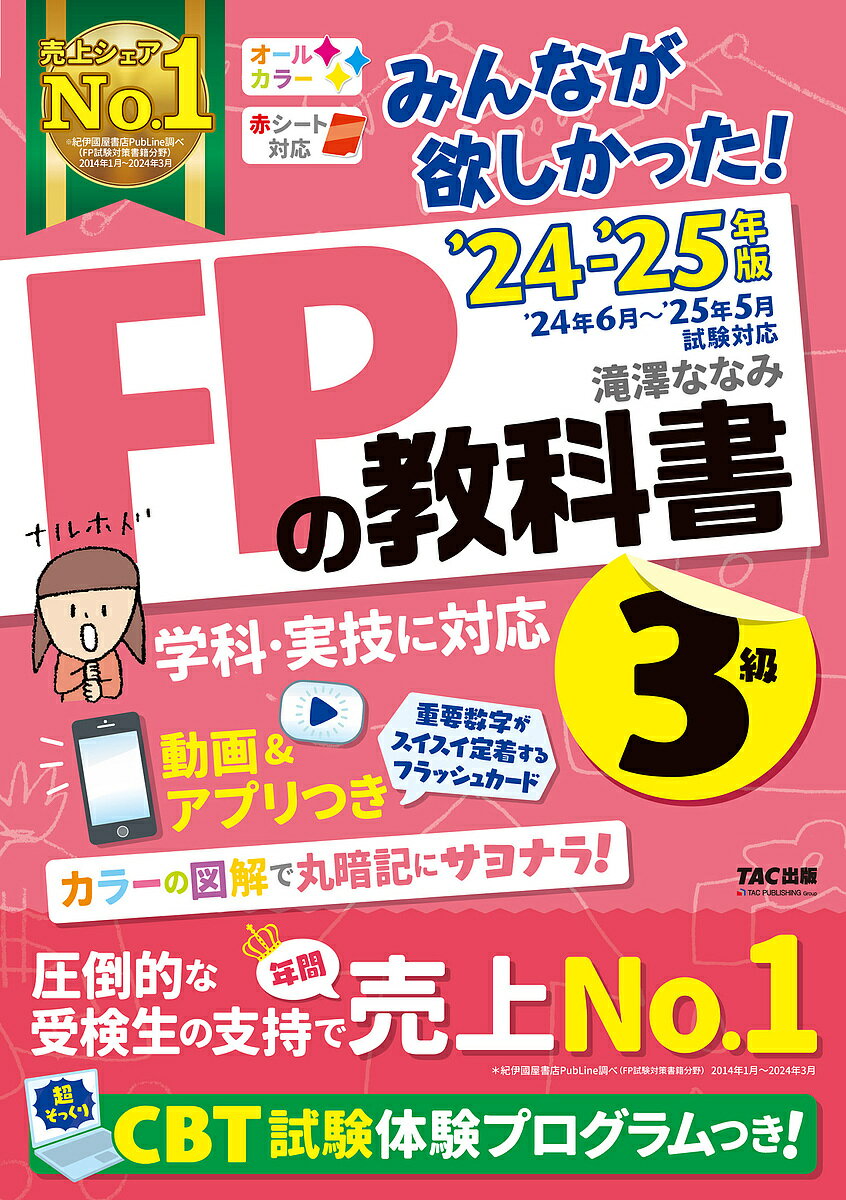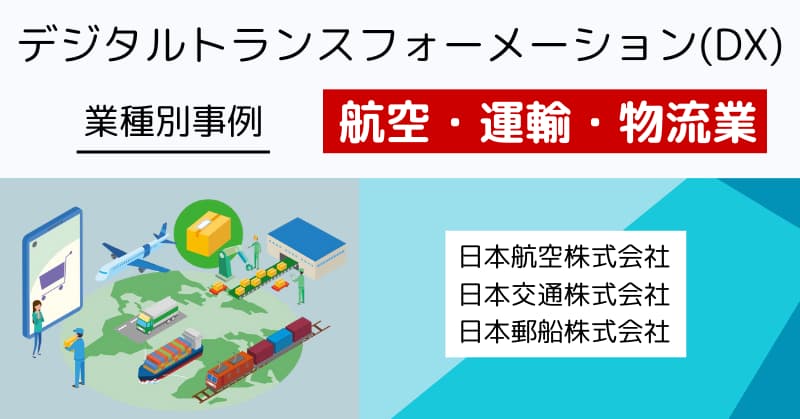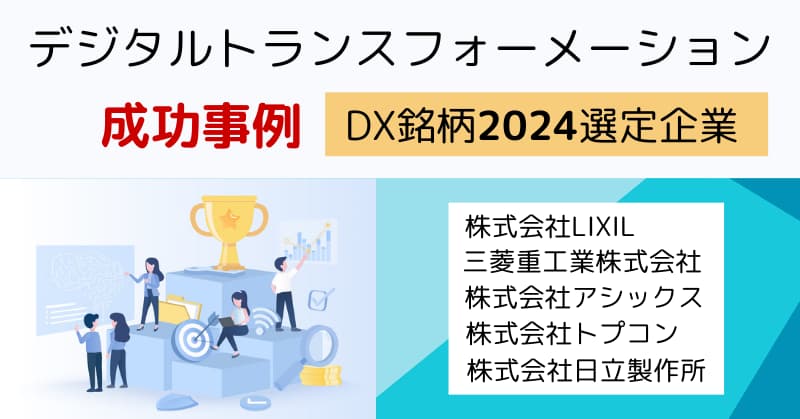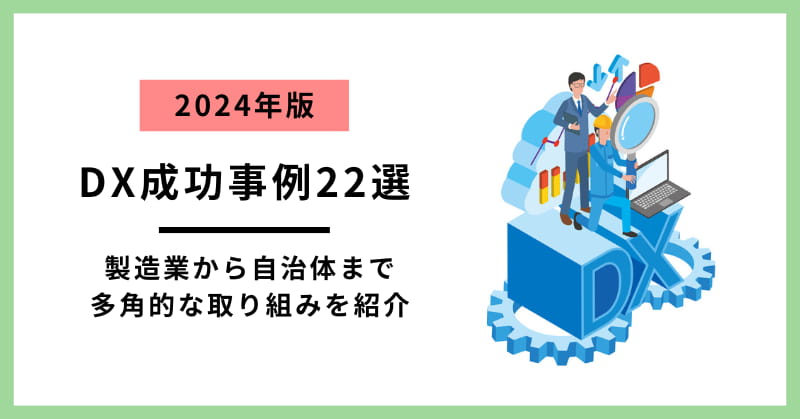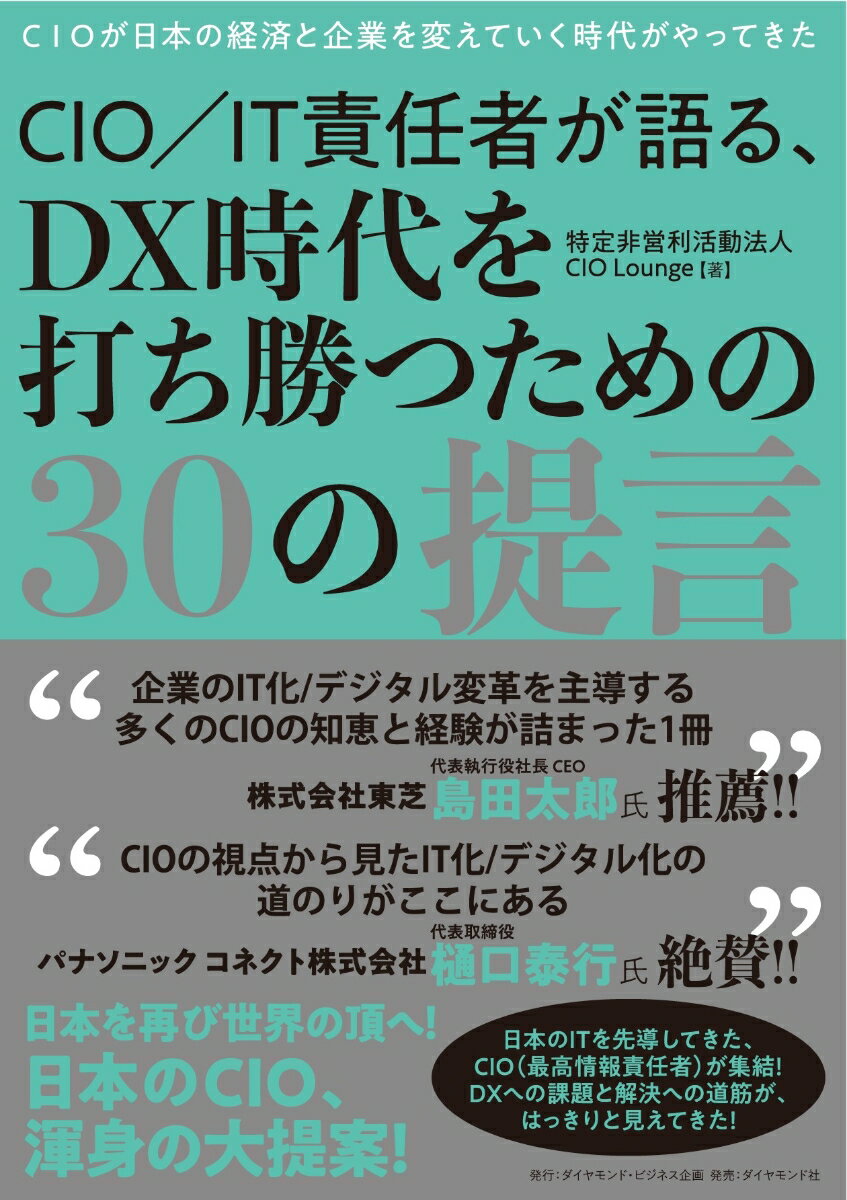仕事から帰ってきたら、ビールとおつまみで晩酌をする父親の姿を子供ながらに「大人とはああいうものか」と考えていました。ただ、自分が40代になり、現実は仕事で疲れ、帰るとご飯を食べて、お風呂に入ると、もう寝る時間になっています。なので、晩酌をするのは金曜と土曜日の晩ぐらいです。世間はどうなのか気になり、調べてみました。
晩酌の頻度はどのくらい?
最近の調査によると、晩酌をする頻度は人それぞれですが、全体的には週に1回から3回程度が多いようです。特に、男性は週5~6日晩酌を楽しむ人が多い一方で、女性は週2日程度が一般的です。以下のグラフは、晩酌の頻度を示しています。

このグラフを見ると、男性の方が晩酌をする頻度が高いことがわかります。特に「ほぼ毎日」と答えた人の割合が目立ちます。女性は、仕事や家庭の事情から、晩酌の頻度が少ない傾向にあるようです。
晩酌のシチュエーション
晩酌をするシチュエーションも多様です。仕事の疲れを癒すために飲む人もいれば、友人や家族と楽しい時間を過ごすために飲む人もいます。調査によると、「疲れた時」や「仕事の後」が最も多いシチュエーションとして挙げられています。

このように、晩酌はただの飲酒ではなく、リラックスやコミュニケーションの手段としても重要な役割を果たしています。
飲まれるお酒の種類
晩酌で人気のあるお酒の種類は、ビール、ワイン、日本酒、カクテルなど様々です。特にビールは、晩酌の定番として多くの人に親しまれています。以下のグラフは、性別による飲まれるお酒の種類の割合を示しています。

このグラフからもわかるように、男性はビールを好む傾向が強く、女性は日本酒やワインを選ぶことが多いようです。お酒の選び方にも、性別による違いが見られます。
晩酌の支出
晩酌にかけるお金の傾向も興味深いです。多くの人が晩酌にかける金額は、1000円から3000円未満が一般的です。

このグラフを見てみると、男女ともにこの価格帯に集中していることがわかります。
晩酌は、楽しみながらも経済的な負担を考える必要があります。無理のない範囲で楽しむことが大切ですね。
健康への影響
晩酌を楽しむことは、ストレス解消やリラックスに繋がりますが、健康への影響も考慮しなければなりません。特に、毎日飲むことが習慣化すると、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。週に2日程度の休肝日を設けることが推奨されています。
最近の研究では、週1~2回の飲酒が適量とされており、過度な飲酒は健康リスクを高めることが示されています。お酒を楽しむ際には、適度な量を心がけることが重要です。
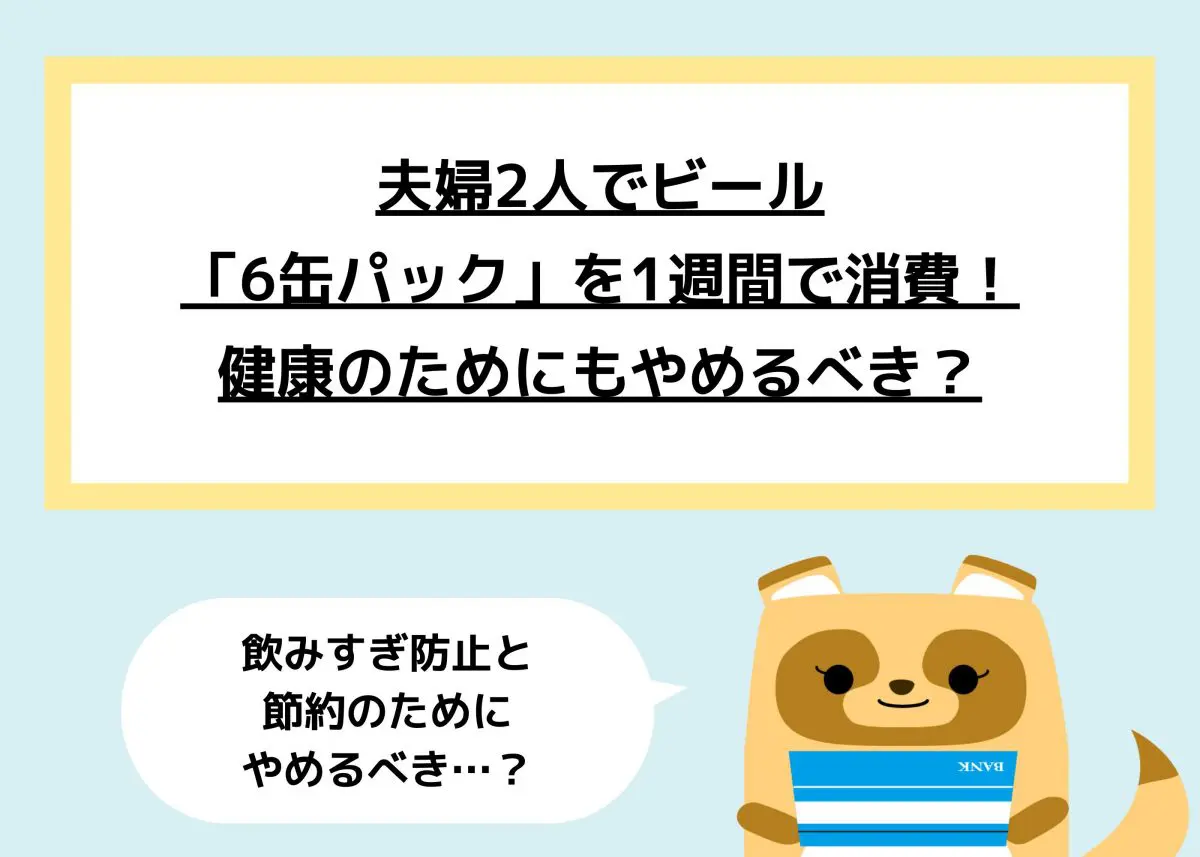
晩酌を楽しむためのポイント
晩酌を楽しむためには、無理のない範囲での飲酒が大切です。自分の体調や生活スタイルに合わせて、楽しむことができる晩酌のスタイルを見つけることが重要です。また、友人や家族と一緒に楽しむことで、より良い時間を過ごすことができます。
晩酌は、ただの飲酒ではなく、心のリフレッシュやコミュニケーションの場でもあります。自分に合った楽しみ方を見つけて、素敵な晩酌ライフを送りましょう!
ちなみに、最近お気に入りのビールは、こちらです。