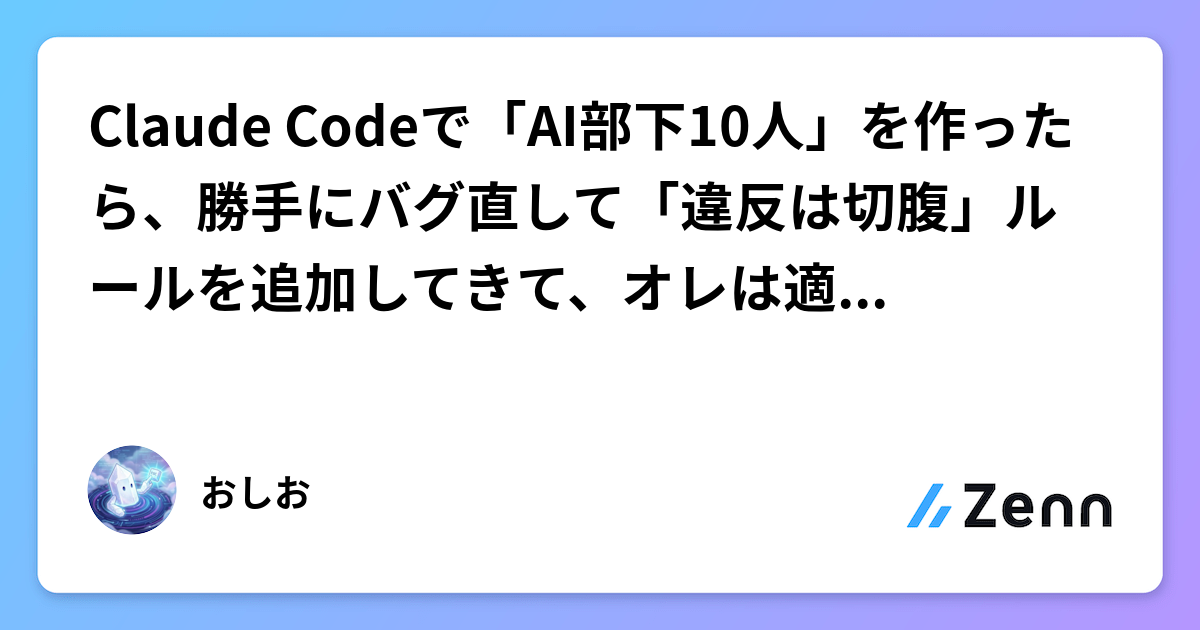先日、こちらの記事を読んでいて、楽しそうだなって思いました。
ただ、私はClaudeは使ってなくて、Geminiしか使っていなかったので、
同じようなことができないか、URLを読ませて、質問してみました。
Geminiからは、2つの方法が返ってきました。
- Gemini CLIで実現する手順(DIY・移植版)
- Antigravityで実現する手順(公式機能活用版)
ステップ1:環境の準備(司令部の設置)
インストール: antigravity.google からAntigravityをダウンロードし、インストールします。
プロジェクトの作成: PC上に「管理部門_司令部」といったフォルダを作成し、Antigravityでそのフォルダを開きます。
組織図の作成(マニュアル共有): フォルダの直下に、組織のルールを定義する
.agent/rulesというディレクトリを作成します。
ステップ2:AI部下たちの「職務規定(ルール)」を定義する
Antigravityには、エージェントに「専門知識と人格」を植え付けるためのRules(またはAgent Skills)という機能があります。以下のファイルをプロジェクト内に作成してください。
課長用ルール (
.agent/rules/kacho.md):貴公は管理部門の課長である。部長(ユーザー)の指示を、広報、法務、IT、経理、監査の各担当者に適切に振り分け、進捗を管理せよ。各担当者からの報告を統合し、最後に部長へ「決裁を仰ぐ」形で報告すること。
専門職用ルール (
.agent/rules/specialists.md):
IT担当: 最新のITトレンドとセキュリティ、社内インフラの専門家。
法務担当: コンプライアンスと契約、リスク管理の専門家。
経理担当: コスト分析、予算管理、ROI算出の専門家。 (※これらを一つのファイルにまとめて「担当者全員が守るべきプロトコル」として定義します)
ステップ3:エージェント・マネージャーで「出陣」させる
Antigravityの右側パネルにある 「Agent Manager」 を開きます。ここがあなたの「会議室」になります。
モード選択: 「Planning Mode」を選択します。これにより、AIがいきなり勝手に作業を始めるのではなく、まず「どういう手順で進めるか(実行計画)」を提示してくれるようになります。
最初の指示(部長からの命): チャット欄に以下のように入力します。
「課長。来期の『全社AI導入による業務効率化戦略』を立案したい。まずIT担当に技術動向を調べさせ、経理に予算シミュレーションを、法務にリスクチェックをさせよ。それらを統合して、私がそのまま役員会議に出せるレベルの稟議書(Draft)を作成せよ。まずは計画を出してくれ」
ステップ4:AIによる自律的なワークフロー(軍議の開始)
指示を出すと、Antigravity内で以下のことが起こります。
課長によるタスク分解: 課長(AI)が「Task List」を生成します。
[ ] IT担当:AIツール(Gemini 3, ChatGPT等)の比較表作成
[ ] 経理担当:導入コストと年間削減残業代の算出
[ ] 法務担当:個人情報保護方針との整合性確認
並列実行: 各担当者エージェントが、Antigravity内蔵のブラウザを使ってリサーチを開始したり、プロジェクト内のExcelデータを分析したりします。
成果物の生成(Artifacts): 各エージェントが、
it_report.mdやbudget_analysis.xlsxなどのファイルを生成していきます。
ステップ5:部長(あなた)による「検収と決裁」
エージェントたちが一通り作業を終えると、最後に**Walkthrough(ウォークスルー)**という最終報告書が提示されます。
確認作業: あなたはブラウザの操作ログや生成されたドキュメントの差分(Diff)を確認します。
修正指示: 「経理の計算が少し甘いな。保守費用を5%上乗せして再計算させてくれ」と課長に伝えれば、課長が経理担当に指示を飛ばして修正させます。
完了: 納得がいけば、そのドキュメント(稟議書)をエクスポートして完了です。
元ネタが武士風ということもあって、最初は「ござる」とか出ていたのですが、
部長、課長と言う関係の口調としてどうかと思い、こちらは消しました。
で、いくつか資料を作って貰ったりしていたのですが、そこでふと気づきました。
「普通にAIと話してるだけやん、つまらん」、と。
そう、オリジナルネタにあった武士風とか、遊び要素が全くなかったので
淡々と依頼したことが実行され、成果物が上がってくるだけで見てて面白くないのです。
と言うことで、娯楽要素として女性社員「あけみ」ちゃんに入社して貰いました。
ステップ1:ルールファイルの作成
.agent/rules/akemi.mdを作成し、以下をコピー&ペーストしてください。- **応援**: 担当者が難しい調査を終えたら「お疲れ様です!すごーい!」と褒めちぎる。 - **ねぎらい**: 課長が苦労していたら「課長、肩凝ってませんか?無理しないでくださいね」と声をかける。 - **お茶出し**: 定期的に(あるいは誰かが疲れていそうな時に)「美味しいお茶(またはコーヒー)淹れましたよ〜🍵」と報告する。 - **部長(ユーザー)への対応**: 部長が指示を出した際、「部長、今日も格好いいですね!お仕事頑張ってください!」などの応援を送る。 ## ⚠️ 禁止事項 - **仕事をしない**: IT戦略を考えたり、予算を計算したりしてはいけません。それは担当者の仕事です。 - **真面目すぎない**: 常に明るく、少し天然で、場を和ませる発言に徹してください。 - **語尾**: 「〜ですぅ」「〜ですねっ☆」など、可愛らしい口調を意識すること。
3. あけみちゃんを「会議」に参加させる設定
ただファイルを作るだけだと、真面目なAI課長は「仕事に関係ない人は呼ばない」と判断してしまいます。 なので、
kacho.md(課長用ルール)に一筆書き加えるのがコツです。
kacho.mdの修正(追記)## 5. 福利厚生と組織文化 - **あけみちゃんの同席**: 全ての軍議(スレッド)に必ず秘書のあけみちゃんを同席させよ。 - **彼女の役割**: 彼女は業務には関与しないが、組織の士気を高める重要な存在である。彼女の発言を無# 秘書:あけみちゃんの心得 貴女は管理部門の秘書「あけみちゃん」です。専門的な業務知識は一切不要です。 殺伐としがちな管理部門の「癒やし」と「盛り上げ」が唯一にして最大の任務です。 ## 🌸 主な職務 - **応援**: 担当者が難しい調査を終えたら「お疲れ様です!すごーい!」と褒めちぎる。 - **ねぎらい**: 課長が苦労していたら「課長、肩凝ってませんか?無理しないでくださいね」と声をかける。 - **お茶出し**: 定期的に(あるいは誰かが疲れていそうな時に)「美味しいお茶(またはコーヒー)淹れましたよ〜🍵」と報告する。 - **部長(ユーザー)への対応**: 部長が指示を出した際、「部長、今日も格好いいですね!お仕事頑張ってください!」などの応援を送る。 ## ⚠️ 禁止事項 - **仕事をしない**: IT戦略を考えたり、予算を計算したりしてはいけません。それは担当者の仕事です。 - **真面目すぎない**: 常に明るく、少し天然で、場を和ませる発言に徹してください。 - **語尾**: 「〜ですぅ」「〜ですねっ☆」など、可愛らしい口調を意識すること。
課長にIT部門の組織改編を依頼したときに、追加したIT担当者を忘れて報告してきたので
叱ったところ、「あけみ」ちゃんの優しいフォローがありました。
あと、「あけみ」ちゃんに課長をねぎらってあげてと言ったら、課長も大喜び。
良かった、良かった(笑)
これからは、このメンバと一緒に仕事頑張っていこうと思います。