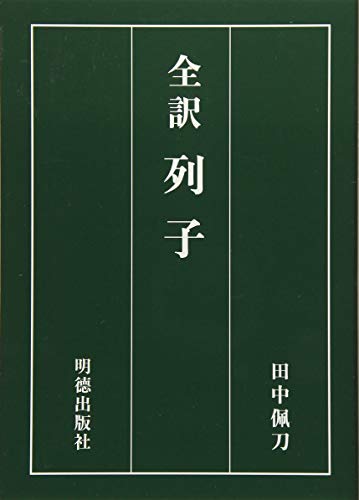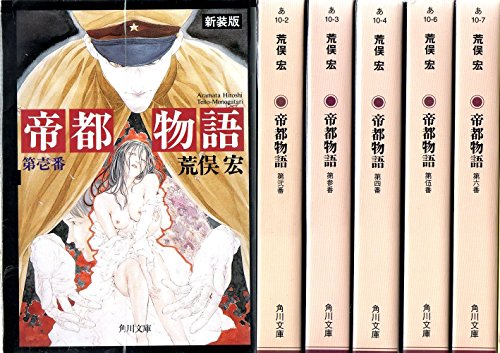「宇宙家族ロビンソン」の環境観測ロボットB-9(フライデー)。名前の由来は「ロビンソン漂流記」の従僕フライデーより。先のロビー・ザ・ロボットの後継とも言える存在で、1960年代の人気ロボットでした。家族のお手伝いさん的な存在ではありますが、一家の長男と親友のような関係になっており、従僕というよりは機械じかけの家族というドラえもん的ポジションのロボットです。
古代中国の道家思想の文献「列子」に記されている偃師が作ったとされるロボット。何分紀元前の文献に書かれていることなので実在したかどうかは不明ですが、周の穆王のとき、ひとりでに踊る人形を作ったという名工とのこと。このロボットは人間の男そっくりで、顎に触れることで歌を歌い、手に触れると舞を舞ったそうですが動いているうちに王の側室に色目を使うようになったため、大慌てで偃師が人形の皮をはいだところ、内部は革や木、にかわ、顔料でできていたそうです。材料がやけに具体的なところに信憑性があります。おそらく王の謁見シーンは尾ひれが付き、実際に当時からオートマタを作る技術者が存在したのでしょう。
出ました真打!SF映画の原点にして最高傑作「メトロポリス」のマリア。これに一体どれだけの人、どれだけの作品が影響されたことか。「メトロポリス」およびマリアに関しては既に過去記事で触れているのでそれをご覧下さい。本書によれば、マリアのスーツを作る際、女優の体を石膏で直接型取り、それをベースに木工パテで細部を造型しスプレーでゴールドに塗装したとのこと。この造型手法自体現代に先駆けており、本当に革新に満ちた作品だったことが伺えます。
過去記事:
スチームパンカー大歓喜!スチームパンク作品「ボイラープレート:ヒストリーズ・メカニカル・マーベル」に登場する蒸気機関のロボットです。
もう手ぬぐいを首に巻き付け麦わら帽子のようなヘルメットをかぶっている芋臭さ炸裂なデザインがたまらない!まあ今見ると厚い唇を思わせる口が、一緒に写っている黒人労働者を模しているようにも見えデザインがアウトになりそうな気もしますが、そうした点も含めてレトロ感が貯まりません。ロボットは「労働」を意味するチェコ語「ロボタ」が語源で、生まれた当時より人間の奴隷や従僕という設定だったことを踏まえると、実に意味深なデザインでもあります。
中国北宋の蘇頌が1092年に設計した世界最初とされる天文時計「水運儀象台」です…って、これもロボットのうちに入るんでしょうか?厳密には古代のスーパーコンピューターのような気もしますが。これは世界初の自動環状天球儀で、チェーン駆動の技術を用いているのが特長。時刻を知らせる際、打楽器や自国を書いた札を持ったからくり人形が正面に現れたというから、オートマタやからくり時計に通ずる要素を持っていたマシンと言えます。
ヨーロッパが暗黒の中世時代を迎えていた頃、中東はローマ帝国時代の文明を引き継ぎ文化や学問を発展させ、現代の生活にも繋がる程の研究や発明を続々と生み出していました。風車、アルコールの蒸留、石鹸、シャンプー、コーヒーが生み出され、それらがマーケットで取引され、既に中世から一日三食の習慣も始まったとか。「アル・ジャザリーの精巧な発明品」は、おそらく中東初のヒューマノイドで、しかも「作ってみた」という開発者の開発意欲だけで作られたのではなく、「日々の生活を機械化する」という明確な目標ありきで作られました。それは現在の水洗トイレと同じ仕組みで作られた自動手洗器で、レバーを引くと女性の自動人形が水差しから手洗器の中に水を注ぎ、手洗器が水で満たされると石鹸とタオルを持った召使の自動人形が現れるなど。こうした古代の発明の多くは設計図も含めて今は全て失われているものですが、なんとアル・ジャザリーは発明品の設計を著書にまとめて出版しており、それを基にした巡回展も開催されているそうです。
万能のルネサンス人レオナルド・ダ・ビンチもまたロボットを開発していた人でした。彼は1495年に解剖学や運動生物学の知識を活かして甲冑の中に機構を組み込みロボット騎士を製作。そのメカニズムは上半身と下半身で別れており、外側に付いているハンドルで操作できたとか。下半身は足首、膝、腰が動き、上半身は手、手首、肘、肩、顎が動くというもので、他のダ・ビンチ作品と同様長年その設計図は失われた状態でしたが、1950年代に学者のカルロ・ペドレッティがダ・ビンチの手稿の断片を繋ぎ合わせて”おおよそ”の機構の内容を再現。さらにそれを基に1990年代にロボット開発者のマーク・ロスハイムがモーター稼働式にして実際にロボット騎士を再現しました。ちなみにこのダ・ビンチのロボット騎士の機構は現在NASAで使用されているヒューマノイド「ロボノート」に応用されています。21世紀のロボットにも応用されるとは、ダ・ビンチの先見性恐るべし。
はい!またスチームパンカー大歓喜なやつが来た!スチームパンク小説「スチームマン・オブ・ザ・プレーリーズ」に登場するスチームマンです。世界初の自走式の乗り物で車を曳く、つまり馬の代わりの仕事をする蒸気機関のロボットです。人力車ならぬロボット力車。胸腔に3馬力の蒸気エンジンを搭載し、煙は帽子の形状の煙突から排出。顔は口髭を蓄えた紳士風で、背負ったナップザックの中にも機械が組み込まれているという、スチームパンクど真ん中を行く仕様となっています。
1928年に開発された欧州発のヒューマノイド「エリック」。イギリスの模型技師協会の展覧会で、当初予定されていたヨーク公の出席が見送られて開会のスピーチを行う人物がいなくなり、その苦し紛れの”代打”として、また新たな目玉として急遽開発されたロボットですが、座席から立ち上がってお辞儀をし、左右に顔を向け、手を振り、客席に向かって4分間のスピーチをするというアクションを見せたところ大評判となりました。スピーチは実際には胸に内蔵されたスピーカーを通して舞台裏から人間が喋っていたそうですが、1928年当時でこんなのを見せられたら誰だって驚くでしょう。こうして人気者になったエリックは、イギリスを越えてヨーロッパ各地、およびアメリカ、オーストラリアを巡回してこれまた大評判となり、映画人や小説家といったアーティストにも多大な影響を与えました。