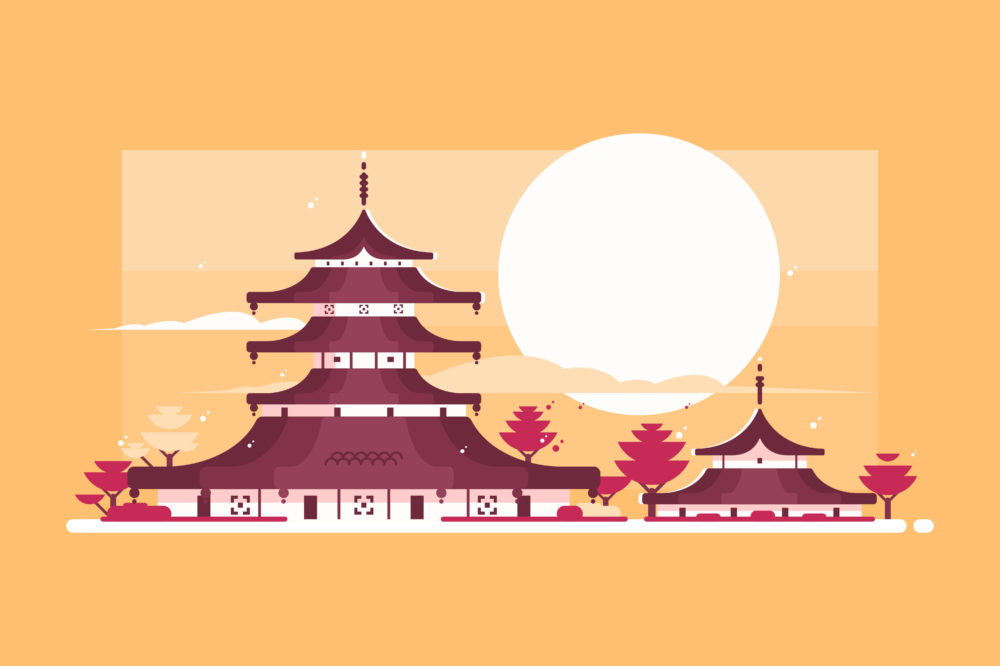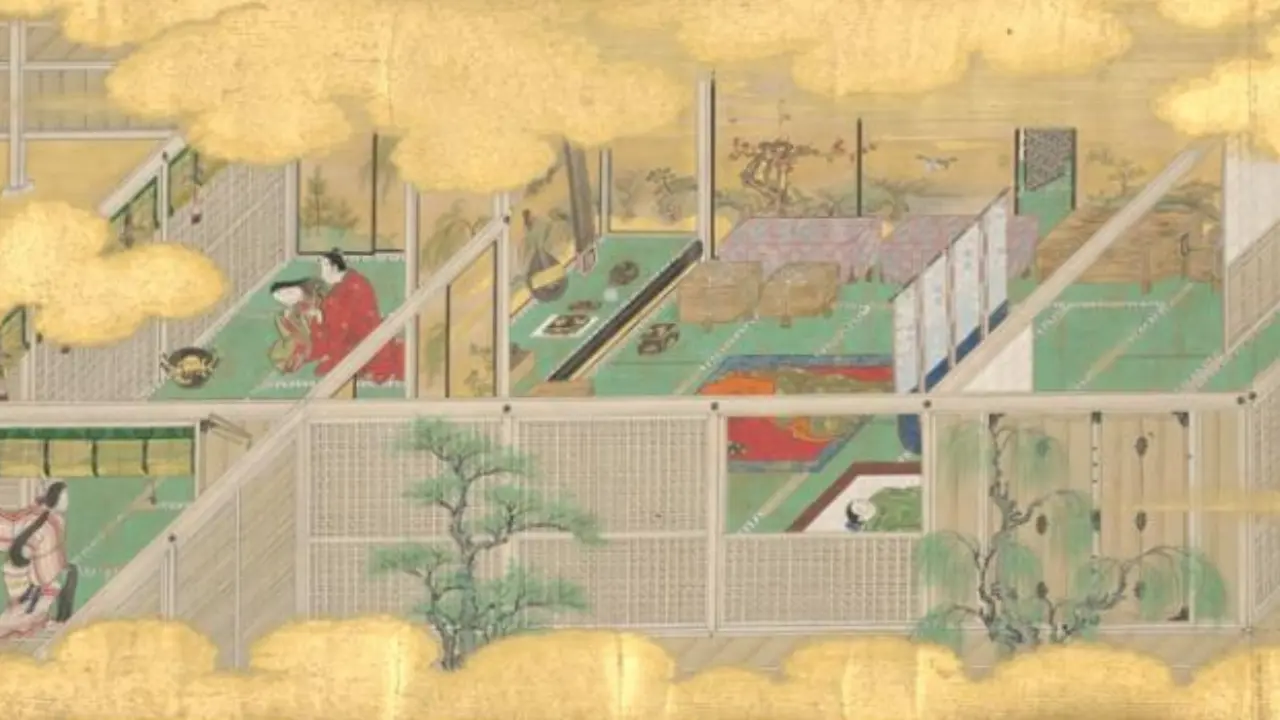当山は山号を豊山(ぶさん)と称し、寺号を長谷寺(はせでら)と
言い、正式には豊山神楽院長谷寺と申します。
朱鳥元年(六八六)道明上人は、天武天皇の銅板法華説相図
(千仏多宝仏塔)を西の岡に安置、のち神亀四年(七二七)
徳道上人は、聖武天皇の勅を奉じて、衆生のために東の岡に
近江高島から流れ出でた霊木を使い、十一面観世音菩薩を
お造りになられました。
徳道上人は観音信仰にあつく、西国三十三所観音霊場巡拝の
開祖となられた大徳(だいとく)であり、それ故に当山は
三十三所の根本霊場と呼ばれてきました。
現在の長谷寺は、真言宗豊山派(しんごんしゅうぶざんは)の
総本山として、 また西国三十三観音霊場第八番札所として、
全国に末寺三千余ヶ寺、 檀信徒はおよそ三百万人といわれ、
四季を通じ「花の御寺」として多くの人々の信仰をあつめています。
十一&三十三&三十三=77(11×7)
三十三&八&三千&三百=3342・・・3&3&4&2=12(6 6)
四&77&3342=3423・・・3&4&2&3=12(6 6)
仁王門
登廊 スタート地点
平安時代の長暦三年(1039)に春日大社の社司中臣信清が子の
病気平癒の御礼に造ったもので、百八間、三九九段、上中下の三廊
に分かれている。下、中廊は明治二十二年(1889)再建で、
風雅な長谷型灯籠を吊るしている。
(パンフから)
百八&三九九&三=600
牡丹
牡丹
蘇鉄 躑躅
天狗杉
紀貫之 故里の梅
「人はいさ 心も知らず ふるさとは
花ぞ昔の 香ににほひける」
蔵王三鈷
このあたりに、吉野山から虹が架かり、その上を三体の
蔵王権現が歩いて長谷寺までやって来たといういわれから、
この場所に金峯山寺の蔵王堂と同じ「弥勒」「釈迦」
「千手観音」の三体が祀られています。
蔵王権現は、インドや中国由来ではなく、日本独自
の修験道の神(本尊)です。
手水舎
稲荷大明神
本堂
本尊十一面観世音菩薩立像
木造 像高1,018.0cm
重要文化財 室町時代 本堂
現在の御尊像は、室町時代の天文七年(1538)に
大仏師運宗らによって造立されました。
雨宝童子立像
木造 総高178.1cm
重要文化財 室町時代 本堂
難陀龍王立像
木造 総高213.0cm
重要文化財 鎌倉時代 本堂
1&1&8&1&7&8&1&2&1&3=10&17&6=33(11×3)

長谷寺 本堂 | AONIYOSHI (eich516.com)
難陀龍王立像・・・藤原氏の氏神
木造 総高213.0cm
重要文化財 鎌倉時代 本堂
本尊に向かって右脇侍。本尊造立の際に影向した八大龍王
のひとり、また春日明神としても信仰されております。
頭上に龍を頂き、唐冠を被った老貌で中国風の服を着ています。
本尊大観音尊像春季特別拝観
普段は尊顔のみの拝観ですが、特別拝観では、
お御足に触れてご縁を結んでいただけます。(パンフから)
私は特別拝観をしなかったのですが、知り合いの人が
拝観したので、五色線を見せてもらいました![]()
鎌倉の長谷寺でも観音様のお御足に触れるというのを
やっていましたね。
本堂の右手真ん中あたりから、大観音尊像(顔)を見れます。
奥には、びんずるさん
びんずるさん
仏旗
平成二十六年十二月十日重要文化財に登録された。(パンフから)
二十六&十二&十=48・・・4&8=12(6 6)
「いざいざ奈良」2024年の新キャンペーンは、大和四寺めぐり。
© トレたび
五重塔
さらに開山堂から五重塔まで歩きます。
三重塔跡
昭和二十九年、戦後日本に初めて建てられた五重塔で「昭和の名塔」
と呼ばれている。塔身の丹土色と相輪の緑青色、軽快な檜皮葺屋根
の褐色は、背景とよく調和し、光彩を放っている。(パンフから)
本長谷寺
道明上人は天武天皇の御病気平癒のため国宝「銅板法華説相図」
を鋳造し、本尊としてお祀りされた。(パンフから)
686年5月24日に天武天皇は病気になりました。仏教の祈祷を
行い病気平癒を願いましたがその甲斐なく病気は平癒せず、
7月11日に皇后と皇太子に政治を委ねました。そして7月20日
に元号を改めて朱鳥と改めています。その後も神仏に祈りまし
たが9月11日に崩御しました。
長谷寺の濫觴を語る銅板法華説相図を4月1日から5月31日まで特別公開
天武天皇の勅を得て西の峯(今の五重塔辺り)に石室の仏像と
三重塔(銅板法華説相図の事)を建立した。
一切経蔵
弘法太師御影堂
花水木
枝垂桜
椿
姫空木(ひめうつぎ) 姫卯木 別名卯の花
花蘇芳(はなずおう)
花言葉は「裏切り」「不信」でキリストの弟子のユダが
師を裏切り、後悔してこの木の下で絶命したそうです。
ちなみに、ほかの花言葉は「高貴」「幸福」「豊かな生涯」。
大手毬
まだ、咲いていませんでした~~
花梨の花はとても可愛いのです![]()
今度、ブログに載せますね~♪
八重桜
六角堂(写経殿)
本坊は向かって右 西参道は左
紅花常盤万作
「私から愛したい」のほか、「霊感」「おまじない」といった
花言葉がり、東北地方では花の開花状況から豊作を占ったと
伝えられています。
本堂
芍薬(ピンク)
芍薬が見頃です長谷寺便り|奈良大和路の花の御寺 総本山 長谷寺 (hasedera.or.jp)
白色の芍薬の花言葉は「はにかみ」、「恥じらい」、「幸せな結婚」、
「満ち足りた心」です。
芍薬は奈良時代に日本に渡ってきたという説もあれば、平安時代
に伝わったという説もあります。
根が薬用として使われ、「当帰芍薬散(トウキシャクヤクサン)」
や「芍薬甘草湯(シャクヤクカンゾウトウ)」という漢方薬にも
なっています。芍薬の漢方薬は、鎮痛効果や婦人科系の病気に
効能があります。
芍薬と同じボタン科の花には、牡丹(ボタン)があります。 牡丹の
花言葉は「人見知り」、「恥じらい」、「富貴」、「風格」です。
中国の唐の時代では、「花王」や「百花王」とも呼ばれていました。
牡丹の「花王」に対し、芍薬は花の宰相という意味の「花相」とも
呼ばれます。
上皇陛下御手植松
長谷寺本坊 八棟
本坊
玉鬘観音像の特別拝観を、別料金で見学しました![]()
御開帳情報
奈良県の長谷寺で本堂と大講堂の2ヶ所で春期特別拝観を開催。
本堂の大観音特別拝観では十一面観音菩薩のおみ足に直接
触れることができる。
本坊大講堂での特別拝観では紫式部が記した源氏物語に登場
する女性「玉鬘(たまかずら)」にゆかりのある「玉鬘観音像」
を特別展示。
日程
2024年3月1日(金)~7月7日(日)
9:30~16:00
2&2&4&3&1&7&7&2(ヶ所)=8&18&2=28
9&3&1&6=19
28&19=47・・・4&7=11
源氏物語 切絵御朱印
仁王門から出て、普門院不動堂前にて
躑躅
藤
譜(はなふ)
桜(一月)~千両(十二月)まで86種の花が植わっているそうです。
奈良八重桜&百日紅&百日紅&十月桜&万両&万両&千両
(パンフから)
一&十二&86=99(11×9)
八&百(2)&十&万(2)&千=11218・・・1&1&2&1&8=13
99&13=112・・・1&1&2=4(2 2)(11×2)
「いにしえの奈良の都の八重桜 今日九重に匂いぬるかな」