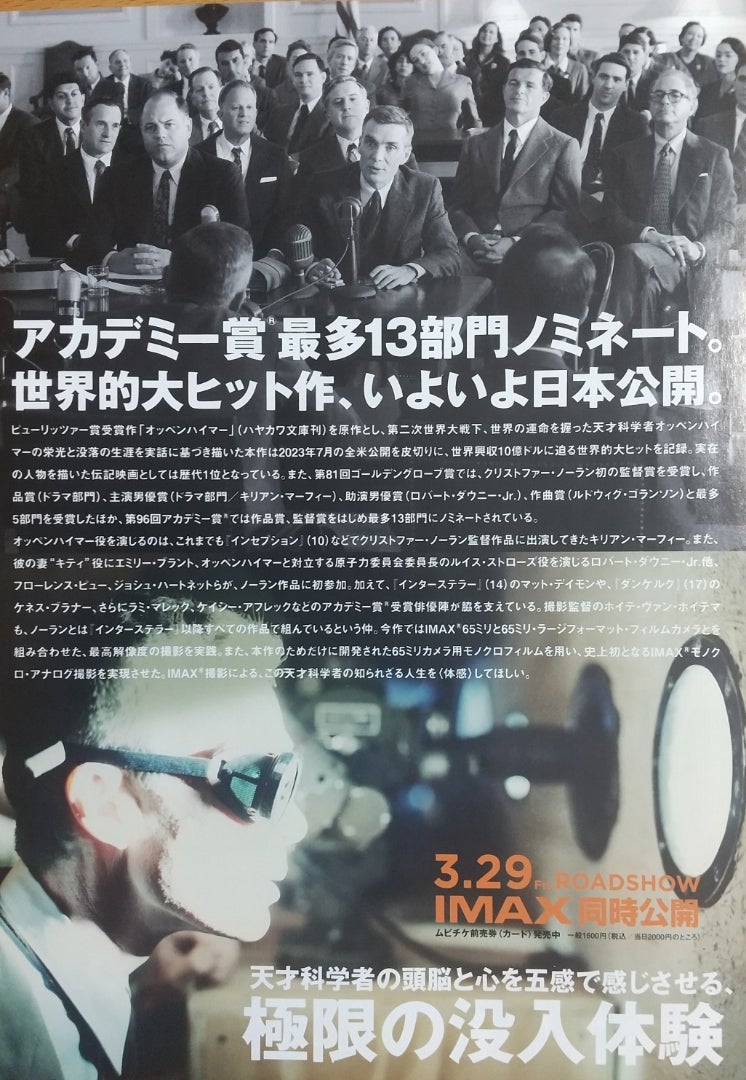4月8日(月)、『オッペンハイマー』を、見ました。
第96回アカデミー賞に、13部門にノミネートされて。
作品賞、監督賞、主演男優賞、助演男優賞、編集賞、撮影賞、作曲賞を受賞。
その賞の大きさ、重たさに見合うだけの作品。
監督・脚本は、クリストファー・ノーラン。
彼の、『クセの強い』作品に、好意的でない観客もいるかと。
しかし、この『オッペンハイマー』は、それを些事として、一気に押し流してしまう、圧倒的な映像と、音楽。
180分に、緊密な時が流れ。
チラシに、
「一人の天才科学者の創造物は、世界の在り方を変えてしまった。
そしてその世界に、私たちは今も生きている。」
また、
「第二次世界大戦下、世界の運命を握った天才科学者の栄光と挫折」
ただ、物語が、すんなりと入り込んで来るかというと、そうではなく。
ひとつには、時系列の変化。
1954年の、オッペンハイマーに対する公聴会。『オッペンハイマー事件』。
そこから、時間が、作品の展開とともに、行き来して。
それに惑わされないために、まずは自らが、一筋の『時間の流れ』を作り。
カラー映像場面と、モノクロ映像部門。その法則性。
それは、誰の『視点』かという、『視点』の違い。
そのことにより、この作品の、ふくらみが生まれ。
登場人物の多さ。その識別。
いつ、どこで知り合い。
オッペンハイマーとは、どのような関係性を結んでいるか。
極端な言い方をすれば、『敵』と『味方』の識別。
しかし、昨日までの『味方』が、今日の『敵』となり。
そして、歴史的背景の知識。
第二次世界大戦。ドイツの『核兵器』開発と。
それに対するアメリカの動き。
その渦中に送り込まれる、科学者たち。
そして、戦後。
ソ連との『冷戦状態』下の、アメリカにおける、反共産主義。『赤狩り』。
などなど。
言葉をかえるならば、一筋縄ではいかない、ということ。
しかし、それは、見終えたあとも、作品世界との、心地よい『格闘』が続くということ。
主人公の、J・ロバート・オッペンハイマーを、キリアン・マーフィ。
第二次世界大戦を終わらせる手段としての『原爆』開発。
しかし、実験を繰り返していくなかで、『原爆』の破壊力を知るようになると、そこに罪悪感が生まれ。
さらには、ソ連も原爆開発に成功するようになると、アメリカは、今度は、『水爆』の開発に邁進するようになり。
という、オッペンハイマーの苦悩。
そのオッペンハイマーを取り巻く人びと。
そして、そこに生まれる、科学者としての『対立』。
さらには、人間としての『対立』もあり。
そうした『関係性』。
それが、とてもなまなましく。
おもしろく。
戦後のアメリカに吹き荒れた『赤狩り』の嵐。
1954年の、オッペンハイマーに対する公聴会。
1959年の、ルイス・ストローズ(ロバート・ダウニー・Jr.)に対する公聴会。
それらの予備知識、基礎知識があれば、作品は、さらに深みを増して。
圧倒的な映像と、音楽。
大きなスクリーンと、優れた音響環境。
映画館を選びことからはじまります。
この『オッペンハイマー』の上映に関して、扱っている内容が、『原爆の父』とも呼ばれるオッペンハイマーであることから、日本での上映を危ぶむ声がありました。
そのため、二の足を踏んだ、配給会社も。
また、原爆に関して、投下された側の、広島と長崎の描写がないことに対しても、批判の声が。
基本的には、直接、その作品にふれて、それぞれが、その作品の良し悪しを判断することが大切だと思っています。
作品を見ずに、『情報』からだけでの判断は、するべきではないと。
この『オッペンハイマー』。
オッペンハイマーの視点から、原爆を見ています。
そして、その破壊力に、その悲惨な結果に、衝撃を受け。
水爆の開発に反対し。
つまり、アメリカが原爆を作れば、ソ連も。
アメリカが水爆を作れば、当然、ソ連も。
そのことにより、『核』の脅威が。
人類は、取り返しのつかないところに。
そうしたオッペンハイマーの考えに、トルーマン大統領は、不快感を示し。二度と俺の前に呼ぶな、と。
もっとも、そうした時代の波に翻弄されながらも、映画は、と、ここまでにしておきます。
2、3回見ないと、全体像がつかめないと、言われていますが。