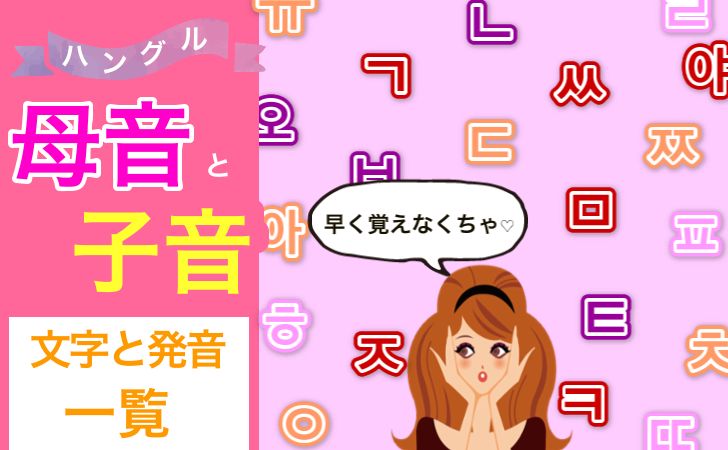江戸時代の俳句は全部平仮名にしても意味が混乱することがないようです。
「ふるいけや かわずとびこむ みずのおと」松尾芭蕉
「なつくさや つわものどもが ゆめのあと」 〃
「さみだれを あつめてはやし もがみがわ」 `〃
「めでたさも ちゅうくらいなり おらがはる」小林一茶
「すずめのこ そこのけそこのけ おうまがとおる」〃
漢字の読みが音読み(=漢語)なのは地名とか固有名詞のみで、あとはほぼ訓読み(=和語)です。
落語を聞いても、江戸時代の庶民は念仏とか題目とかの仏教語以外はほとんど漢語は使ってなかったのではないかと思います。
明治以降、やたらと漢語を多用するようになり「きしゃのきしゃがきしゃできしゃした(貴社の記者が汽車で帰社した)」とかは全部音読み(=漢語)なので、ひらがなにしたら混乱しそうです。
漢字の部分を全部知っていたら大体わかるでしょうけど、現在は「汽車」はほぼ死語になっていますし、「貴社」より「御社」の方が一般的のようですから、若年層は混乱するでしょう。
英語もtwoとtooが同音ですし、結構同音異義語が多いらしいのですが、日本語では「異常」と「異状」のように同音で意味もほとんど同じという超紛らわしい同音異義語があったりしますから、仮名だけで表記すると大混乱するでしょう。
韓国や北朝鮮では漢字をほぼ使わないみたいで、韓国旅行の時駅名も全部ハングル表記だったので困ったのですが、同音異義語で混乱するようなことはないのでしょうか?
韓国語=朝鮮語は日本語より母音・子音がはるかに多いので、全部ハングル表記にしても同音異義語が少ないのであまり混乱しないみたいですね。
現在の日本語の印刷物は「漢字かな交じり文」がほとんどなので、それらを読みこなすには数千語の漢字を覚える必要がありますので外国人にはかなりハードルが高いようですが、日本人にとっても結構高いハードルです。
戦後の政府の政策により漢字の使用が制限されていたのですが、最近の印刷物やWeb上の文章には当用漢字世代には読めない漢字が頻出しており、いちいち辞書を見ないといけないので面倒です。
2010年に196字も常用漢字に追加しているので、高齢者の方が知らない漢字が多いという変な状況になってしまっているわけですが、後から字数を増やすというのは困りますけどね。
「齎す」とか読めなくて、繁体字(台湾の漢字)に誤変換されているのではないかとしばらく思っていたのですが、常用漢字で追加されていたそうです。
ありがとうございます