作曲家古関裕而をモデルにした昨年の朝ドラ『エール・戦時下編』は、朝ドラとしては画期的な内容が盛り込まれた作品として大反響を呼びました。
私が画期的と思うのは、以下のような点です。
1 ファシズム体制下での息苦しい国民生活を多方面から描くことで、急速に右傾化しつつある現在のNHKでは許されるであろう限界まで踏み込んだ軍国主義批判を行なったこと。 2 軍歌 (ドラマでは「戦時歌謡」) が作られていく過程と軍歌が国民に与えた影響をしっかり描いたこと。
3 これまで銃後の国民生活しか取り上げてこなかった朝ドラとしては、初めて直接戦闘場面(インバール作戦)を取り上げたこと。(2回目という説もあるようですが)
今回は1の軍国主義体制下での国民生活がどのように描かれたかを見ていくことにしますが、2についての内容も含まれています。
第78話にこんなシーンがあります。
「何でもかんでも統制されて、不自由な世の中ね。」と嘆く音に対して、軍人の妻らしく軍国主義は当然と思っている吟はこう言って音をたしなめます。
「 お国を批判する者は裁かれても仕方がないでしょ。」「今は国民が一丸となってお国のために戦わんといかん時代なの。」
すると小説家の三女がこれに強く反論します。「それ言い出したら、音楽も芸術も死ぬことになる。表現の自由は侵されていいものじゃない!」 音も三女に同調します。「でも、人が心で思う事って止められんじゃないかな。一致団結とか一丸となってとか言うけど、人はそれぞれ違う考えがあって当たり前。」
同じ第78話ではこんなやりとりも描かれます。 五郎「今は戦意高揚の曲しか作らせてもらえんですかね。書きたいものが書けなくなるって大変ですよね。」 祐一「でも、僕はね、求められるものには全力で応えたいと思ってる。仕事がいただけることは本当に有難いことだから。」
第78話の以上のような描写によって、5人の登場人物たちの軍国主義や戦争への向き合い方の違いが明示されます。また、これは後の展開への伏線ともなるものです。
三女の梅は、キリスト教徒である関口家が特高の監視対対象になっていることを知った馴染みの出版社から出入り禁止を宣告されてしまいます。五郎は「 間違ってますよ、こんな世の中。」と憤りますがどうにもなりません。
この後、礼拝も禁止されたキリスト教の信徒たちは密かに集まって対応を話し合うシーンも出て来ますが、まるで共産党の地下集会のように見えます。戦争や軍への協力を巡り、信徒たちの意見の相違や対立も浮き彫りになります。
キリスト教も特高の監視対象になっていたことを知って驚いた視聴者もいると思いますが、戦前の軍国主義体制下では国体(国民体育大会ではなく、天皇が支配する国家体制)や国家神道に反する敵性宗教として、キリスト教は治安維持法の弾圧対象になっていたのです。
治安維持法は、「天皇制」という国体の変革、私有財産制の否認を目的とした結社、反戦思想等を取り締まるため、大正末期の1925年「普通選挙法」と抱き合わせのような形で制定された史上最悪の治安立法。
当初は、共産主義者を弾圧することが目的とされましたが、戦争や天皇制に反対していた日本共産党の壊滅後は、日本が戦時色を強める中で次第にその適用範囲が拡大して濫用されるようになります。労働運動は勿論のこと、共産主義とは何の関係もない社会運動や農民運動、文化運動(生活綴り方運動や青年団活動等)、宗教団体、果ては単なる自由主義者までもがその標的となって次々と検挙されました。その数何と10万人!
「データで読み解く戦争の時代① ETV特集『自由はこうして奪われた~治安維持法 10万人の記録~』」(2020)
最高刑も1928年には緊急勅令によって死刑に変更され、大日本帝国の戦争遂行のために邪魔になるとみなされた全ての団体、結社、集団、個人を根こそぎ弾圧していったのです。
「隣組制度」による相互監視や密告が横行し、しまいには少しでも厭戦的な事を言ったり、政府の悪口を言ったりしただけで警察や特高に拘禁され、厳しい取り調べや拷問を受けるまでにエスカレートして行きました。
基本的人権が全く保障されない戦前の大日本帝国は、まさしく「ディストピア」そのものでした。
『エール・戦時下編』最終回でも反戦思想を持っていた五郎が特高に逮捕されて、凄惨な拷問を受けるシーンが描かれていました。特高に「戦争反対とは何事だ、国賊め!と罵られた五郎は「身体の自由は奪えても、心の自由は奪えません。」と叫び、更に激しい拷問を受けます。
これらは決して遠い過去の話ではなく、戦前の国体回帰を狙う「日本会議」などの極右勢力が現政権の中枢深く食い込んでいるのは非常に恐ろしいことです。何しろ、現役の総理までが容易にネトウヨ化してしまう国ですから。
会合の最初に大日本国防婦人会(ドラマでは「大日本婦人会」)の綱領を唱和するのですが、これが凄まじい内容。いきなり「神を敬い詔を畏み皇国の御為に御奉公いたしませう」という神国思想に基づく滅私奉公の誓約が出てきてびっくりさせられます。 当日の奉仕作業が竹槍作りなのは、いろいろな意味でなるほどですが。
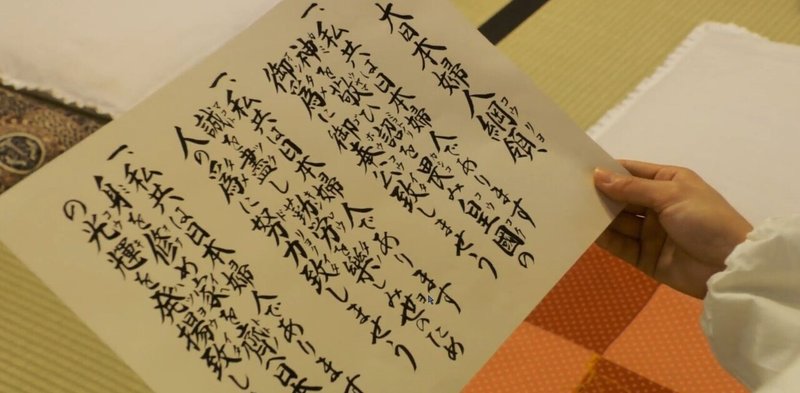
音楽挺身隊(実在した組織)を創設した小山田(モデルは山田耕筰)は、 「音楽は戦力増強の糧である。音楽を戦局のためお国のために全力で捧げることが我々の使命である。」と言い放ちます。 その音楽挺身隊に志願した音は、慰問先の工場で「愛国行進曲」を合唱しますが、「戦争の話ばかりでまるで軍隊のような音楽挺身隊」にこの先も付いていけるか不安になっています。
音楽挺身隊の仲間たちと相談した結果、音は慰問で歌う曲の選定を任されます。 しかし、音が選んだ曲は小山田の軍国主義思想の信奉者である責任者の神林に「軟弱」と非難され、一蹴されてしまいます。それに続く神林と音とのやり取りは、国家総動員法下での軍歌が担う本質的な部分が明らかにされており、脚本・演出共に非常に優れた内容でした。
神林「音楽の使命は、軍需産業に従事する者たちの士気を高め、日本の勝利に貢献することです。音楽は軍需品なのです。今は芸術だの楽しみだのと言う呑気なことを言っている時世ではありません、必要なのは決戦意識と戦力の増強、決戦の役に立たない音楽などいらないのです。それが分からないのですか!」
神林に罵倒された音は、それでもこう反論します。 音「よく分かりません。音楽は音楽だと思います。 音楽を聴いて何をどう思うかは人それぞれで。 」
神林「何のためにここに来ているのか!」 音「歌を聴いてくれた人たちに笑顔になっていただくためです。」
音の返答を聞いてあきれ返った表情の神林は「話になりませんね。お帰りなさい。挺身隊に非国民は必要ありません。」と宣告します。
挺身隊で非国民と言われてしまったことを裕一に話す音。 音「非国民と言われたら、さすがにこたえるね。でも、みんなが同じ考えでなくてはならないのかな。そうじゃない人はいらないって世の中は、私は嫌。」 裕一「でも、こうなってしまった以上、この国に生きる人間としてできる事やって行くしかないんじゃないのかな。」
軍国主義体制下でも表現の自由や思想・信条の自由を大切にしたいと考える音に対して、常に「長いものには巻かれろ」式の考えしかできない裕一。

