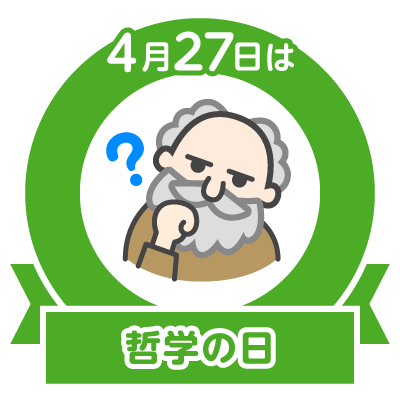4月27日(日)
日常で役立つ哲学の教えは?
▼本日限定!ブログスタンプ
哲学かどうかわからないけれど、中学の国語の先生から教わった「知足の喜び」。
『高瀬舟』の授業だったと思うけど、「上を見て不満ばかり言うよりも、足ることを知ることで心の安寧を得ることに喜びを見出しなさい」と言われました。
もちろん「現状に満足するだけで向学心を失うのはよくない」、とも。←先生、私にどうしろと?
その後何度か辞書を引いてみるのですが、「知足」はあっても「知足の喜び」が辞書に載っているのを見たことがありません。
先生の造語なのか?と最近はちょっと疑ったりして。
でも、「身の丈に合った生活」以上を求めようとは思わない私の原点は、この言葉にあると思っています。
「巧言令色鮮し仁」も同じく中学の国語で覚えた言葉。
私の人格形成に、結構な影響があった中学国語。
かわいげのない人間ではありますが、地に足がついた感じは自分ながら気に入っています。
昨日載せ忘れた写真。
中央の木の枝に雀がとまっているの、わかりますか?
なんかちょっとふくら雀的な…。
今日、長男が帰省しました。
我が家は夕飯前にお風呂に入るのですが、最後に入る10さんが「先にやってていいよ」と言ったので、ジンギスカンの肉を焼きながら、長男と二人分のご飯やほかのおかずを用意していました。
いざ食べようとしたら、10さんが慌ててあがってきて「え?そういうつもり?」と怒るので、どういうことかと思ったら、「先に焼いてていいよ」と言っただけなんですって。
焼いたら食べるでしょ、普通。
焦がしとけってこと?
結局3人そろっての晩ご飯になりましたけどね。
本日の読書:なんとかしなくちゃ。青雲編 1970-1993 恩田陸
これは、作者が相当楽しんで書いたに違いないと思った。
梯結子という女性の、幼少期から大学卒業時までの話である。
幼いときから彼女は、「理不尽だな―」「不便だな―」「もったいないなー」など「キモチワルイ」状況に陥った時に、何とかならないか考える癖があった。
一番最初は4歳の時。
いつも行く公園の砂場が、ある時見知らぬ子どもたちに占拠されてしまったのだ。
そして10日もたった頃、何事もなかったかのようにその子たちは来なくなり、いつもの砂場が戻ったのだ。
しかし翌年、再び見知らぬ子どもたちが砂場を占拠し…。
なぜ1年に10日、見知らぬ子どもたちが砂場にやってくるのか。
結子はどうやってそれを解決したのか。
「幼児が主人公の日常の謎」路線でその先も話が進むのかと思ったらそうではなく、お誕生日会におけるプレゼントの高額化の解消や、友だちを生徒会長にするための効果的な選挙演説など、ミステリとは無関係に結子は問題を解決していく。
少ない手数で効果的な結果を。
補助線を引いて解決するのなら、誰かの手助けを求めることも可。
少ないダメージで大勢を救う方法。
周囲をよく観察し、どうしたらよいかを自分の頭で考える。
これは私の大好きな、賢い女の子の話である。
賢いというのはもちろん学校の勉強が得意ということではなく、経験を積んで現実に反映させる能力が高いということだと私は思っている。
結子はまさしくそんな少女だ。
地の文に、折々作者の意見や思い出が差し挟まれるのも御愛嬌。
なんだか作者と二人で結子の成長を見守っているようで、なかなか楽しい読書体験だった。
作者は彼女の一生を書くつもりだったのだが、どう頑張っても一冊では終わらないことに気づき、今回『星雲編』として出版したとのことで、続きを書きたいという気持ちはあるらしいので、首を長くしてそれを待つことにしよう。
Amazonより
『「これは、梯結子の問題解決及びその調達人生の記録である。」大阪で代々続く海産物問屋の息子を父に、東京の老舗和菓子屋の娘を母に持つ、梯結子。幼少の頃から「おもろい子やなー。才能あるなー。なんの才能かまだよう分からんけど」と父に言われ、「商売でもいけるけど、商売にとどまらない、えらいおっきいこと、やりそうや」と祖母に期待されていた。その彼女の融通無碍な人生が、いまここに始まる――。』これは、作者が相当楽しんで書いたに違いないと思った。
梯結子という女性の、幼少期から大学卒業時までの話である。
幼いときから彼女は、「理不尽だな―」「不便だな―」「もったいないなー」など「キモチワルイ」状況に陥った時に、何とかならないか考える癖があった。
一番最初は4歳の時。
いつも行く公園の砂場が、ある時見知らぬ子どもたちに占拠されてしまったのだ。
そして10日もたった頃、何事もなかったかのようにその子たちは来なくなり、いつもの砂場が戻ったのだ。
しかし翌年、再び見知らぬ子どもたちが砂場を占拠し…。
なぜ1年に10日、見知らぬ子どもたちが砂場にやってくるのか。
結子はどうやってそれを解決したのか。
「幼児が主人公の日常の謎」路線でその先も話が進むのかと思ったらそうではなく、お誕生日会におけるプレゼントの高額化の解消や、友だちを生徒会長にするための効果的な選挙演説など、ミステリとは無関係に結子は問題を解決していく。
少ない手数で効果的な結果を。
補助線を引いて解決するのなら、誰かの手助けを求めることも可。
少ないダメージで大勢を救う方法。
周囲をよく観察し、どうしたらよいかを自分の頭で考える。
これは私の大好きな、賢い女の子の話である。
賢いというのはもちろん学校の勉強が得意ということではなく、経験を積んで現実に反映させる能力が高いということだと私は思っている。
結子はまさしくそんな少女だ。
地の文に、折々作者の意見や思い出が差し挟まれるのも御愛嬌。
なんだか作者と二人で結子の成長を見守っているようで、なかなか楽しい読書体験だった。
作者は彼女の一生を書くつもりだったのだが、どう頑張っても一冊では終わらないことに気づき、今回『星雲編』として出版したとのことで、続きを書きたいという気持ちはあるらしいので、首を長くしてそれを待つことにしよう。