今朝、駅に向かって歩いていた時のこと。
込み入った飲み屋さん街から細い通路を通ってバス通りに出るのですが、その細い通路を灰色の塊がこちらに向かって走ってきます。
サイズ的に…鳩?
しかしものすごいスピードです。
そして、鳩にしては黒い?
いや、でも、この辺の鳩は黒いからなあ…。
なんてことを考えながら、ぼーっと立ち止まって見ていると、急にそれが向かって左に進路を変えまして、その正体が明らかになったのでございます。
その距離、約2m。
走るの速い鳩と思ったのは、でかい鼠でした!
いわゆるドブネズミってやつ?
ほえ~って見ている間にいなくなっちゃいましたよ。
あんまりびっくりして、鳥肌も立たなかった。
映画『ネズミが襲う日』みたいにうじゃうじゃいたらそれこそ泡吹いて倒れたかもしれないけど、一匹だけだったし、目を合わすこともなく走り去っていったので、意外にも嫌悪感なかったわ。

『地道な努力が大吉を呼ぶ。努力は??見ている人がいる』を覆い隠す『今年の目標を再確認すると吉』
あー。はいはい。
今年の目標は、読みたい本リストの残を1900冊以下にする
すっかり忘れてました。
ひと月も経ってないのに。(T_T)
本日の読書:寺田寅彦随筆集 小宮豊隆編
Amazonより
『寺田寅彦の随筆は芸術感覚と科学精神との希有な結合から生まれ、それらがみごとな調和をたもっている。しかも主題が人生であれ自然であれ、その語りくちからはいつも温い人間味が伝わって来る。二十代から最晩年の五十代後半まで書きつがれた数多の随筆から珠玉の百十余篇を選んだ。』
目次
・鐘に釁(ちぬ)る
・北氷洋の氷の割れる音
・鎖骨
・火事教育
・ニュース映画と新聞記事
・自然界の縞模様
・藤の実
・銀座アルプス
・コーヒー哲学序説
・空想日録
・映画雑感(Ⅱ)
・映画「マルガ」に現れた動物の闘争
・物質群として見た動物群
・蒸発皿
・記録狂時代
・感覚と科学
・涼味数題
・錯覚数題
・神話と地球物理学
・試験管
・科学と文学
・科学者とあたま
・沓掛より
・さるかに合戦と桃太郎
・人魂の一つの場合
・思い出草
・踊る線条
・ジャーナリズム雑感
・函館の大火について
・庭の追憶
・藤棚の陰から
・とんびと油揚
最近読んだ夏目漱石の弟子(俳句の)で、中谷宇吉郎の師(物理の)である寺田寅彦の、晩年の随筆を集めたもの。
編者の小宮豊隆も漱石の弟子でしたね。
昭和8年から9年にかけて書かれた随筆ですが、私から見ると明治のにおいがかなり濃厚。
それはなぜかというと、文章から立ち上る空気というか、日差しの強さ、土埃のけぶる道、草花の濃密な匂いが私の知っている昭和よりもかなり強いから。
ああ、戦前の昭和は、まだ明治がこんなにも近かったんだなあと思いました。
さて、科学者としての寺田寅彦の業績はよくわかりませんが、身近な現象から思いもかけない着地点に到達する思考の幅が素晴らしいと思いました。
そして、本来は難しいはずの科学を、素人にもわかりやすく伝える文章の読みやすさ。
難しいものをやさしく書くことは簡単ではない。
しかしそれが出来た時、書いた本人の頭のなかもわかりやすく整理されているのだそうです。
振動に対する感覚の実験をしていて、われわれの「寿命」すなわち「生きる期間」の長短を測る単位は、われわれの身体の固有振動周期だということに思い至る著者。
これって、昔流行った『ゾウの時間、ネズミの時間』のことだよね。
なるほど~。
この中で読みたかったのは「科学者とあたま」
“頭のいい人は批評家に適するが行為の人にはなりにくい。すべての行為には危険が伴うからである。けがを恐れる人は大工にはなれない。失敗をこわがる人は科学者にはなれない。科学もやはり頭の悪い命知らずの死骸の山の上に築かれた殿堂であり、血の川のほとりに咲いた花園である。一身の利害に対して頭がよい人は戦士にはなりにくい。”
失敗を恐れない人。
人のためになってこその科学という信念の人。
ものすごく防災の重要性を主張した人。
頭の切れる、しかし心の柔らかな人だと思いました。

込み入った飲み屋さん街から細い通路を通ってバス通りに出るのですが、その細い通路を灰色の塊がこちらに向かって走ってきます。
サイズ的に…鳩?
しかしものすごいスピードです。
そして、鳩にしては黒い?
いや、でも、この辺の鳩は黒いからなあ…。
なんてことを考えながら、ぼーっと立ち止まって見ていると、急にそれが向かって左に進路を変えまして、その正体が明らかになったのでございます。
その距離、約2m。
走るの速い鳩と思ったのは、でかい鼠でした!
いわゆるドブネズミってやつ?
ほえ~って見ている間にいなくなっちゃいましたよ。
あんまりびっくりして、鳥肌も立たなかった。
映画『ネズミが襲う日』みたいにうじゃうじゃいたらそれこそ泡吹いて倒れたかもしれないけど、一匹だけだったし、目を合わすこともなく走り去っていったので、意外にも嫌悪感なかったわ。

『地道な努力が大吉を呼ぶ。努力は??見ている人がいる』を覆い隠す『今年の目標を再確認すると吉』
あー。はいはい。
今年の目標は、読みたい本リストの残を1900冊以下にする
すっかり忘れてました。
ひと月も経ってないのに。(T_T)
本日の読書:寺田寅彦随筆集 小宮豊隆編
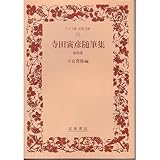 | 寺田寅彦随筆集〈第4巻〉 (ワイド版 岩波文庫) Amazon |
Amazonより
『寺田寅彦の随筆は芸術感覚と科学精神との希有な結合から生まれ、それらがみごとな調和をたもっている。しかも主題が人生であれ自然であれ、その語りくちからはいつも温い人間味が伝わって来る。二十代から最晩年の五十代後半まで書きつがれた数多の随筆から珠玉の百十余篇を選んだ。』
目次
・鐘に釁(ちぬ)る
・北氷洋の氷の割れる音
・鎖骨
・火事教育
・ニュース映画と新聞記事
・自然界の縞模様
・藤の実
・銀座アルプス
・コーヒー哲学序説
・空想日録
・映画雑感(Ⅱ)
・映画「マルガ」に現れた動物の闘争
・物質群として見た動物群
・蒸発皿
・記録狂時代
・感覚と科学
・涼味数題
・錯覚数題
・神話と地球物理学
・試験管
・科学と文学
・科学者とあたま
・沓掛より
・さるかに合戦と桃太郎
・人魂の一つの場合
・思い出草
・踊る線条
・ジャーナリズム雑感
・函館の大火について
・庭の追憶
・藤棚の陰から
・とんびと油揚
最近読んだ夏目漱石の弟子(俳句の)で、中谷宇吉郎の師(物理の)である寺田寅彦の、晩年の随筆を集めたもの。
編者の小宮豊隆も漱石の弟子でしたね。
昭和8年から9年にかけて書かれた随筆ですが、私から見ると明治のにおいがかなり濃厚。
それはなぜかというと、文章から立ち上る空気というか、日差しの強さ、土埃のけぶる道、草花の濃密な匂いが私の知っている昭和よりもかなり強いから。
ああ、戦前の昭和は、まだ明治がこんなにも近かったんだなあと思いました。
さて、科学者としての寺田寅彦の業績はよくわかりませんが、身近な現象から思いもかけない着地点に到達する思考の幅が素晴らしいと思いました。
そして、本来は難しいはずの科学を、素人にもわかりやすく伝える文章の読みやすさ。
難しいものをやさしく書くことは簡単ではない。
しかしそれが出来た時、書いた本人の頭のなかもわかりやすく整理されているのだそうです。
振動に対する感覚の実験をしていて、われわれの「寿命」すなわち「生きる期間」の長短を測る単位は、われわれの身体の固有振動周期だということに思い至る著者。
これって、昔流行った『ゾウの時間、ネズミの時間』のことだよね。
なるほど~。
この中で読みたかったのは「科学者とあたま」
“頭のいい人は批評家に適するが行為の人にはなりにくい。すべての行為には危険が伴うからである。けがを恐れる人は大工にはなれない。失敗をこわがる人は科学者にはなれない。科学もやはり頭の悪い命知らずの死骸の山の上に築かれた殿堂であり、血の川のほとりに咲いた花園である。一身の利害に対して頭がよい人は戦士にはなりにくい。”
失敗を恐れない人。
人のためになってこその科学という信念の人。
ものすごく防災の重要性を主張した人。
頭の切れる、しかし心の柔らかな人だと思いました。
