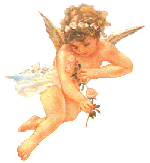Blanc Diary
好きなこと、書いてます♪
プロフィール
最新の記事
テーマ
ブックマーク
このブログのフォロワー
ブログ内検索
カレンダー
月別
お気に入りブログ
2008年11月16日 06時33分31秒
笄(こうがい)
テーマ:ブログ先日11月13日のべっ甲のかんざし の記事で、
べっ甲の簪や櫛の紹介をしました。
その中にどうやって使っていたのかわからないものがあったのですが、
カエル姫さん に「こうがい」であることを教えていただきました。
それで、少し調べてみたんです。
笄(こうがい;「髪掻き」の転訛)とは、髪を掻き揚げて髷 を形作る装飾的な結髪用具。元は中国 のもの。 頭が痒い時に髪型を崩さずに掻いたり、女性の装身具としても使われた。 日本では、「三所物」と呼ばれる日本刀 (脇差 )の付属品のひとつで、刀と一緒に持ち歩く場合も多い。
髪を掻き揚げやすいように頭部から長細い二本の足が出た形をしているか(頭部はイチョウ の葉型が一般的)棒形が普通。 棒形のものは「棒笄」と呼ばれ、最高級品は鶴 の脛の骨で作ったもので、頭痛のまじないにもなると好事家などに好まれたという。 鼈甲 製、金属 製、木製、象牙 製、牛や馬のひづめなど素材は多岐にわたる。 中でも、螺鈿 や蒔絵 や彫金、彫刻などを施したものは非常に高価であった。
(ウィキペディアより)
日本髪に欠かせない「櫛 」「簪 」「笄」の三点セットのうち、笄は櫛に継ぐ由来の古さを誇る。 形状が良く似ているため簪 と混同されることも多いが、ルーツはまったく別系統。
笄は結髪の根に挿すもので、一本しか使わず、髪型によっては省かれることもある。本来は髷の根を固定する実用的な道具であったが、江戸後期の複雑な結髪になると用途は後退し、ほぼ装飾品と同じとなる。その現れが「中割れ笄」という笄で、中心でふたつに分解できるようになっており、結髪を八分がた作り終えてから仕上げに挿すための、完全な装飾品である。棒状に変化したものを「延べ棒」と呼ぶこともある。
江戸時代の辞典には「先が耳かきのものを簪、そうでないのは笄」と区別してある。
(ウィキペディアより)
両輪(りょうわ)
江戸中期
御殿女中から発生。どちらかというと年配向。
髷に輪が二つ(縦の輪と笄に巻き付けた横の輪)あることから名がついた。
先笄(さきこうがい・さっこう)
江戸中期
島田髷と笄髷の折衷。島田髷の前部の毛を笄にからませて止めたもの。
上方の既婚婦人。おもに上流の人たちが結った。
片はずし
江戸後期
髷の一方だけが笄に巻き付けてある。
御殿女中、公家の奥方などが結った。
このような結い方があったらしいです。
浮世絵にも↓。
実際、このように使うものなのですね~。フムフム。
種類もいろいろ、螺鈿細工も・・・。
花嫁用の笄という華やかな作りのものもあったんですね。
自分も多分つけたのでしょうね(笑)
探してみたらありました~
画像はお見せできませ~ん![]()
他にも芸妓さんのお飾りも・・・。
華やかなものですね~。
普段使いするにはなかなか使いこなすには難しそうですが、
お正月や和服を着る機会に
手持ちの笄が役に立つ日があればいいなと思いました。