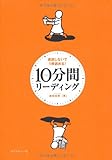- どーも、プレミアムです

本日紹介する本はこちら
¥1,500Amazon.co.jp
≪![]() この本を読むきっかけ
この本を読むきっかけ![]() ≫
≫
僕が読書に目覚めて、書評ブログをあちらこちらで
拝見していた時に著者の鹿田さんのブログ「読むが価値」 も
その1つでした。この方の場合は短期間で、
どんどん有名になられるのがブログを見ていて実感できました。
その鹿田さんの2冊目に出版されたのが本書で、
読書法に関する書籍ということで読んでみたくて
今回、読ませて頂きました。
≪![]() 付箋箇所の抜粋
付箋箇所の抜粋![]() ≫
≫
「はじめに」より
●本は必ずしも「すべて読む必要はない」
すべてを読んで得られることも、自分に必要な部分だけ
読んで得られることも、その大きさにあまり差はありません。
「本は大事な所だけ読む」
●読んだことを忘れてしまう、読んだだけで終わってしまう。
そんな人は書く事を取り入れることで好循環に変化する。
「書かなければ読む意味がない」
PART1:10分間リーディング
速読せずに速く読める「本の読み方」
●10分という時間を制限することで目的にフォーカスして読む。
●第2のタイトルをつける。
私が( )ための( )のポイント
私が( )するための( )の方法
例)私が記録を習慣化するための5つのポイント
読むゴールを最初に決め込んでから本を読む。
●10分間リーディングの読み方は「Read」より「Search」
というイメージ。
●全てを読まなくていい。①人名②数字③造語を探しながら
読むことで大事な1行に出会える。
●新しい情報を得るよりも、読み返すことで再発見するほうが
効率的で無駄がありません。
●目次はじっくりと時間をかけて読む。
目次は目標までの道しるべとなる情報がギュッと詰まっている。
●同じジャンルの本を10日連続で読む(1日1冊)
別の本に書かれていない部分がわかるようになる。
これを「差分がわかるようになる」
●難しく分厚い本は10分間リーディングには不向きである。
●本は出会った瞬間が買い時!
PART2:10分間レコーディング
速く読んでも忘れない「記録のルール」
●本から抜き出す3つの内容
①新しいフレームワーク(考え方の枠組み)
②人に話すときに使える引用句
③第2タイトル(ポイント・事例や比喩)
●読書カードを作って持ち運ぶ。
●ウェブ上に自分の本棚を作る。
「ブクログ」「メディアマーカー」などが代表的。
●記録は毎日5分ずつ読み返す。
何度も何度も読み返す習慣を身につける。
PART3:ノマドリーディング
いつでも、どこでも、読書しやすい環境を手に入れる
●電車やお風呂ではサムシングという読書補助具を活用する。
サムシングは→こちら
●ⅰPhoneスタンドには洗濯バサミが便利
●ブログを書く時に便利な「書見台」
書見台は→こちら
PART4:ワンランク上を目指すReading3.0
学んだことを発信する「知的生産のルール」
●チームリーディングは3~10人で別の本または同じ本を
読んで、ポイントなどを紹介し合う。
難しい本や分厚い本を読むときに効果的である。
●チームリーディングで読んだ本のプレゼンは
基本的には2分ぐらいがちょうどいい。
●ブログはハンバーガー形式で。
ハンバーガーはパンとハンバーグとパンで構成されているので、
①本を読む目的など(パン)
②本の中身:ポイントやエッセンス(ハンバーグ)
③感想など(パン)
●出版も目指す。
①ブログを書くことでコンテンツ力を磨く。
②人のつながりを大切にする。
(常に自分は見られているという意識で)
≪![]() 感想
感想![]() ≫
≫
僕の中では、付箋箇所はほとんどがPART1でした。
この本のキモがPART1に集約されているのかとも思いました。
この著者は時間がもったいないから10分で本を読むことを
推奨しています。
僕は10分間で本を読んでしまうのは
逆に「もったいない」という感情になってしまいます。
何時間もかけて、身につかない本もありますが・・・
ただ、未読(積ん読)にして本棚に
眠っているだけの本なら、10分でも目を通して
何かを得るほうが絶対いいです!
そして、「お!」と思った部分はハンバーガーの部分で、
実は僕も9月の紹介からハンバーガー的な構成に
ブログを変えました。気分的なものもあるのですが、
よりわかりやすくするために変えたところに
ハンバーガーのことが書かれていて、
引き寄せというかシンクロニシティーを感じました。
(シンクロニシティーとは「意味のある偶然の一致」)
新しい読書方法や読書の時間短縮を目指している方は
ぜひ、ご一読を!
最後までお読み下さり、ありとうございます![]()
一言でもコメント(承認制)頂けると
次への励みになります<(_ _)>
 (諦めたらそこで試合終了だよ)
(諦めたらそこで試合終了だよ)
皆さまの1日1回のクリックがランキングを押し上げてくれます。
いつもありがとうございます<(_ _)>
![]() にほんブログ村
にほんブログ村
![]() ビジネス書 ブログランキングへ
ビジネス書 ブログランキングへ