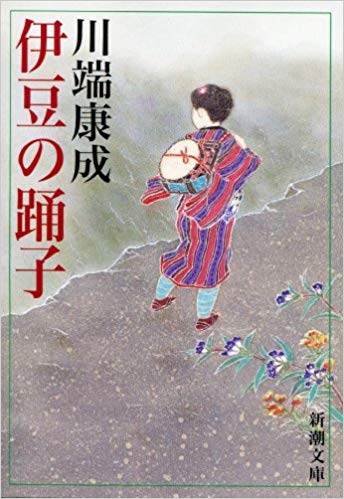2020.2.14に行った夏目漱石『三四郎』読書会のもようです。
私も書きました。
「形式の解体と生命力」
丸山真男は、全共闘の学生に向かって「文化とは形式です」と説教したという。(丸山真男回顧談 下)小林秀雄も安岡章太郎との対談で封建主義のもつ形式というのは、文化を作り上げるからすごいんだ、と力説していた。(安岡章太郎 『文士の友情』)
漱石の作品は形式と生命の対立を描いている。『三四郎』でいえば、美禰子は自由恋愛に惹かれている。野々宮とも、三四郎とも、広田先生とも、原口とも恋愛したい欲求はあっただろう。しかし、形式的なお見合いで、自分を処した。彼女の恋愛の中身は、多くの人に気を持たせた罪作りなモーションだけであった。
スタンダールの『パルムの僧院』を読んで呆れるのは、そのなかに描かれる強烈なロマンである。ナポレオンに憧れるファブリスの、盲目的な情熱が、ギャクかと思うような滑稽さでほとばしっている。これは、ヨーロッパの絶対王政の文化的形式=宮廷の儀礼に対する、生理的なレベルでの破壊欲求である。
封建制は、概念の体系からできている。この概念の体系が「形式」である。ルース・ベネディクトの『菊と刀』によれば、日本の封建的社会秩序は、天皇への忠と親への孝行の概念からなる階層秩序に基づいているという。『それから』の代助は、形式的な佐川の娘との見合いを拒否することで、『親への孝行』にもとづく概念の体系を否定してしまった。自由恋愛として三千代を選んで、実家から勘当された。要するに代助の生命が、親孝行の形式を突き抜けたのだ。体制批判が自由恋愛として表現されている。
形式が目的になっているのが露悪だ、と広田先生はいうが、ベネディクトによれば、忠も考も形式なので、心がこもってなくてもいいのという。家制度のなかに家族愛がなくてもいいである。家制度を、信じていなくても「かのように」形式を踏まえるというところからが、封建制が始まる。
個人を縛り付ける概念の体系が、封建制を成立させているが、個人の生命が、概念の体系を突き破っていけば、概念の体系としての形式は解体していく。みんなが自由恋愛をしはじめれば、それは形式の崩壊であり、つまりは革命のはじまりである。太宰は『斜陽』のなかで、そういうことを描いている。
ファズリスは、自由恋愛の末、旅役者を刺殺し、収容所に打ち込まれる。そこでも収容所所長の娘、クレリアと恋愛関係に陥り、彼女の協力で脱獄する。小さな専制君主国において革命的行動である。こういう行動は、日本文学にはない。100年後の日本にもない。なぜか? それは、日本人が日本文化の形式に無自覚だからだからというのが一つ。もうひとつは、明治維新以降の日本社会においてに、個人の生命力が形式を解体するまでに、未だに高まっていないからだと思う。
(おわり)
読書会の模様です。
『信州読書会』 メルマガ登録はこちらから http://bookclub.tokyo/?page_id=714
今後のツイキャス読書会の予定です。 http://bookclub.tokyo/?page_id=2343