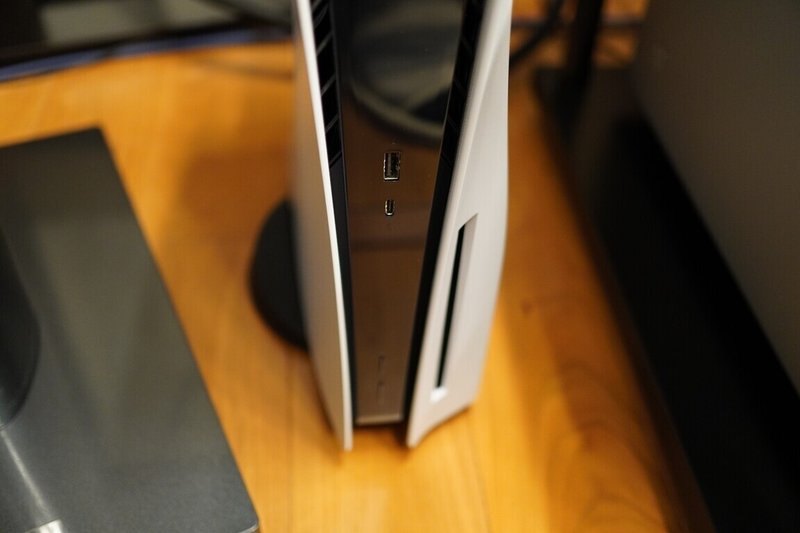こんにちは、Studio 0.xの橋爪徹です。
私は、オーディオライターの活動をしながら、音響エンジニアとして活動しています。音に関するお仕事で飯を食っております。(自己紹介と仕事歴紹介はこちら)
グレード違いで音はどのくらい変わる?
ホームシアターや2.1chシステムには欠かせない存在のサブウーファー。マルチチャンネルでは0.1chと定義され、低域再生のみを受け持つアクティブスピーカーです。
このサブウーファー、意外と軽視されがちでは無いでしょうか。フロントスピーカーが大事なのはその通りですし、AVアンプにだって予算の多くを割きたい気持ちは理解できます。結果、「とりあえず鳴ってればいいか」とサブウーファーのグレードには無頓着な方もいるのではないかと思っています。かくいう私もそうでした。
サブウーファーは、当然メーカーごとにグレードの違いがあります。エントリー機種と上位機種、いったいどのくらい音が違うのでしょうか。スペックを見れば、アンプの出力や最低域の周波数がより低いところまで出ているのは分かります。見た目の特徴は同じでもサイズが大きくなり価格が上がっているケースもあって、果たして音がどれほど違うのか、設置スペースを取るだけの価値はあるのか。気になる方もいるのではないでしょうか。この記事では、DALIのサブウーファーを例にして、サブウーファーのグレード違いによる音質差をレポートしたいと思います。
筆者が自宅スタジオを作ったとき、ホームシアターとしても活用出来るようにしました。しかし、防音室を作った時点で予算の大半を使い果たしてしまい、サブウーファーは2万円台の安価な機種を買い求めました。ずっとそれを使っていたのですが、ご縁あってお仕事でDALIのサブウーファーを試す機会に恵まれ、今では仕事でレビューした機種を自宅に導入するに至っています。詳細は、以下のレビュー記事をお読みいただけると嬉しいです。
話をサブウーファーのグレードに戻しますと、今回ご縁あって自分が導入したSUBE-9Nの上位機種であるSUBE-12Nを試聴出来る機会をいただきました。12Nは設置スペースの都合で元々選択肢にはなかったものの、いちオーディオライターとしては気になっていました。見た目はユニットの口径と足回りのベース以外ほぼ一緒。機能面もアンプの出力や性能は同じ、ウーファーユニットの技術面も同じ、音圧レベルや再生周波数特性がちょっと違うくらいです。あまり違いの無い9Nと12N。はたして、どれだけの音質的違いを見せてくれるか、期待半分・不安半分という感じでした。
試聴は、DALIの国内正規輸入代理店であるD&Mの本社にて実施しました。システム構成は以下の通りです。

フロント: OPTICON6mk2
センター: OPTICON VOKAL MK2
サラウンド: OBERON5
サブウーファー: SUBE-9N/SUBE-12N
AVアンプ:DENON AVC-X8500H
SUBE-9N
ウーファーユニット:9インチ(23cm) アルミコーン
再生周波数帯域(+/- 3 dB):37~200Hz
最大SPL:111dB
アンプ出力:170W(クラスDアンプ)
SUBE-12N
ウーファーユニット:12インチ(30cm) アルミコーン
再生周波数帯域(+/- 3 dB):28~190Hz
最大SPL:112dB
アンプ出力:170W(クラスDアンプ)
昨年7月に発売されたOPTICONのMK2もご用意いただきました。
上記の5.1chシステムで9Nと12Nを聴き比べたところ、まあ、ビックリ! 12Nは明らかに上位機種たり得る魅力的な重低音を楽しむことが出来ました。
※AVアンプ側の音場補正は無効にして、ピュアダイレクトモードで視聴しています。
映画やライブの感動がより上質かつ本格的に!

洋画からはローランド・エメリッヒ監督の『ミッドウェイ』
パニック映画の巨匠が手掛ける戦争モノですが、20年以上に及ぶ膨大なリサーチに基づく戦闘描写は圧巻です。当時のリアルエピーソードが随所に盛り込まれつつ、画面の派手さを追求することも忘れない監督の手腕に好感を覚えました。海外の戦争映画ですから、派手に低音は入っています。真珠湾攻撃開始からレイトン少佐が建物に入るまでを視聴しました。
9Nは、本体が共振してしまっているのが分かります。床の絨毯に直置きなので足回りの振動対策を行えばある程度緩和できるでしょうが、筐体が重低音にビビってしまっているのは聞いていて否定しようがありません。視聴前に、サブウーファー双方の聴感上の音量感がほぼ同じになるように何度もケーブルを繋ぎ替えてボリュームを調整しました。12Nは、足場(ベース)がアルミニウム製でしっかりしています。床へ伝わる振動を抑えられることはもちろん、床の振動がサブウーファーに逆流してくるのを緩和することも期待できるでしょう。筐体の剛性も9Nより高い模様で、音に濁りが少ないのも感心しました。銃撃や砲撃、爆発といった瞬間的なSEもシャープに聴かせてくれます。聴感上の音量を合わせる過程で、9Nも12Nもわざとらしい重低音にならない=さりげない位のボリュームに調整したのですが、9Nに比べると12Nの音の安定感は抜群でした。最低域の伸びもわずか数Hzの違い以上に効果的で、12Nは空気感の再現性がまるで違います。映画館で感じるまるでその場にいるようなトリップ具合は、画面の大きさだけじゃない、重低音もその役割を担っているのだと再認識しました。深く沈み込む密度のある低音は、まさに映画館のそれです。

アニメーションからは、ガールズ&パンツァー最終章 第3話より、中盤の各校の対戦模様を視聴します。第3話は、知波単学園が大きな成長を遂げるも善戦の末、大洗に敗北。続いて劇場版から登場した継続高校との3回戦へとコマを進めます。ジャングルの野戦から雪原へと戦闘フィールドが大きく変化し、音響的にも見所満載の作品です。
率直に言って、9Nでは戦車の砲撃や走行音、衝突などの音が薄っぺらく感じます。12Nは、レベルが大きく瞬発力が求められる戦車戦にあっても、安定感があり映画の世界に没入できました。ローエンドはスペック以上に深く感じられ、厚みがあってリッチです。9Nは、砲撃音がガリガリというちょっと歪みっぽい音に聴こえてしまいます。大音量で鳴ったときの歪み感の少なさを加味すると、リラックスして楽しめるのは圧倒的に12Nでした。9Nは、ちょっと聴いていて疲れます。

最後のソースは、ライブコンサートのBlu-ray。PlayStationで発売されたRPG『クロノクロス』の20周年を記念したバンドライブの追加公演千秋楽を収録したBlu-rayです。ゲーム音楽界の巨匠、光田康典本人がプロデュースしたファン感涙のメモリアルライブ。今でも感想がSNSでつぶやかれ、1周年や2周年でファンがハッシュタグを付けて祝ったりするほど熱狂的に愛されているライブです。私も千秋楽の現場に一般客として足を運び、後にハイレゾ音源化に合わせて光田氏にインタビューをさせていただきました。
本作の音声は、2chのハイレゾと、ドルビーデジタルの5.1chが収録されています。ドルビーデジタルとは懐かしいフォーマットです。いわゆるDVDと同じ、非可逆圧縮のマルチチャンネルサラウンド。おそらくメインの音声がPCM 96kHz/24bitで収録されているため、映像ビットレートを圧迫しないようサブ音声の5.1chはドルビーデジタルにしたのでしょう。
ドルビーデジタル5.1chは、リアスピーカーに観客席の声援や反響が割り当てられ、LFEチャンネルには低音楽器の重低音域はもちろん、ホールの反響に含まれる重低音もミックスされていると思われます。驚いたのは、12Nで5.1chを聴くとホールの中にいる生の空気感を味わえたこと。音楽としての情報は9Nでもまったく問題は無いのです。映画に比べても、9Nと12Nの落差は減りました。しかし、ライブコンサートホールのあの身体全体で感じられるような低音感は12Nでしか味わえません。まさにそのローエンドの深さこそがコンサートホールの空気感に繋がっていたのです。正直、LFEにこんなに低い周波数まで収録されていたのかと驚かされました。ともすれば、重くて息苦しい音場になりがちですが、そこは光田康典プロデュース。ミックスバランスに抜かり無しです。そんなコンサートの臨場感に欠かせない重低音は、12Nでこそ存分に体感できますし、クリアで歪み感の少ない出音のクオリティも相まってドルビーデジタルであることを忘れさせる贅沢な時間を堪能させてもらいました。
3枚のBlu-rayを視聴して分かったのは、サブウーファーのグレードの違いは、予想以上に大きく満足感に影響するということでした。見た目がほとんど同じで、何か特別な機能が上位機種に搭載されている訳ではありませんが、段違いに臨場感はアップしましたし、リラックスして視聴出来る上品な重低音は確かめられたと思います。ウーファーの口径の違いは言うまでもなく、筐体の剛性やベース部の強化により振動の悪影響を抑えた結果、良好な結果を得られたのだと推測できます。
おわりに ~使いこなしのTIPS~
今回の記事を執筆するにあたり、本国デンマークのWEBサイトも参照しました。機能説明はほぼ同じことが書いてあり、アンプも同じ出力&機能、ウーファーユニットも口径以外一緒、明確に違うのはアルミニウムベースとゴム脚だけで、正直呆然としました。ほとんど同じなのに音にこれほど差異が現れるというのは、如何に重低音再生において振動対策(制御)が重要であるかの証だと思います。
置く場所があるなら、迷わずSUBE-12Nを選ぶべし!
これが試聴しての結論です。12Nならローエンドの深みや歪みの少なさを体感できると思いますし、足場のケアをやってあげればさらに音は化けると思います。

アコースティックリバイブのクオーツアンダーボード「RST-38H」(写真は9N)
電源ケーブルはACインレット対応なので、ぜひ交換して欲しいです。私は、同梱品からSAECの余っていた電源ケーブルに交換しました。またRCAケーブルも、長めの製品はなかなか見つかりませんが、業務用のMOGAMI 2534をベースにオーディオケーブル市場で特注しました。注文時に両端をRCAにします。個人的には、高価なサブウーファー専用ケーブルを買うよりは、癖の少ない音色で信頼性も高いMOGAMIをお勧めしたいです。
2022年2月 橋爪徹
試聴協力:株式会社ディーアンドエムホールディングス