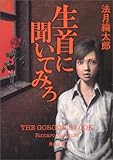2007年10月発行の角川文庫。「このミス」1位とか本格ミステリ大賞受賞作とかのポップをつけて、行きつけの書店で大量に平積みされていた。自分は謎解きを主眼に置いた小説を必ずしも好まないのだが、せっかくの書店のイチ押しでもあるし、この機会に未読の作家に接するのも一興かと思い、手にした次第。
最初に驚いたのは、著者と同名の作家が探偵役で登場することである。この場合、普通ならば、「私」という書き方で進行するべきではないかと思うが、あえて法月綸太郎という固有名詞が作中で動き回るのだ。著者はすでにこの手法で幾多の作品を発表していて、ファンにはお馴染の探偵なのかも知れないけれど、初めて読む自分としては、大いに違和感を感じ、著者の意図を疑問に思った。ミステリに疎いので、こういうスタイルもこの分野では一般的なのだと言われれば、それまでであるが。
彫刻家の川島伊作が病死し、彼が直前に完成させた愛娘の江知佳をモデルにした石膏像の首が、何者かに切断され持ち出された。首の切断は殺人予告とも思われ、江知佳の身を案じた叔父の川島敦志は、旧知の法月綸太郎に捜査を依頼する。綸太郎は伊作のアトリエなどを調査し、外部からの侵入ではなさそうだと見当をつけるが、その直後、江知佳の行方がわからなくなってしまう。
川島伊作の江知佳像は、名古屋市美術館で開催される予定の「川島伊作展」の目玉になるはずの作品であった。その企画を進める美術評論家の宇佐美彰甚が名古屋市美術館へ打ち合せに訪れたとき、宅配便で段ボール箱が届き、そこには江知佳の生首が入っていた。ついに殺人事件の発生となったのだ。
ここからは当然に警察の出番であるが、綸太郎の父親は警視庁の警視であり、綸太郎も警察と合同で捜査に携わるような形になる。このあたりも、すでにファンには馴染みの展開なのかも知れないけれど、初読の自分としては腑に落ちない展開だ。いくら親子でも、こんなことがあり得るのだろうか?
生前の江知佳には、プロカメラマンの堂本峻がストーカーまがいに纏わり付いていたことがわかっており、宅配便の発送も堂本名義でなされていて、指紋も検出されたことから、警察は彼を有力容疑者として懸命に行方を追う。だが、ミステリの常道として、堂本が真犯人ではあり得ないことは明白である。
事件の鍵は、切断して持ち出された石膏像の首にあったのだ。そこには、伊作が死の直前に残したメッセージが籠められていた。それは16年前の、伊作と江知佳の母である律子の離婚、律子の妹の結子の自殺、結子の夫であった各務順一と律子の再婚という、一連のできごとにまで遡るものであった。
ミステリの結末までをこの場に書くことは野暮な気がするので、ストーリーはここまでとしよう。確かによくできたミステリであり、様々な伏線が張り巡らされ、前回出てきたシーンが後に違った意味合いを持ってくることも多々あって、一種の快感を味わうこともできる。ミステリ好きには大満足の一冊であろうと思う。
しかし、広く小説全般を見渡してこの作品の価値を捉えようとすると、やはりこれはミステリのためのミステリという感じで、そのための無理も散見されるし、評価を落とさざるを得ないような気がする。よくできたミステリではあっても、よくできた文学作品にはなり得ていないのではないか? 自分が必ずしもミステリを好まないのも、こうした事情によるわけであるのだが。
2008年11月1日 読了