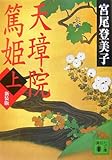今年3月に新装版となって発行された講談社文庫。当初の文庫化は1984年9月であったようだ。
来年のNHK大河ドラマの原作であるらしいが、テレビドラマを見る習慣はないので、そのことには関心がない。ただ、先日読んだ有吉佐和子『和宮様御留 』に幕府大奥の総帥として天璋院の名が見えていて、興味を引かれたというわけである。有吉作品は和宮の江戸入りまでを描いており、しかも二度にわたる身代わりが重要なモチーフとなっていて、この作品との直接の関係は希薄なのだけれど。
この上巻では、薩摩島津家の分家である今和泉家に生まれた篤姫が、藩主斉彬に見出され、本家の養女となって、将軍御台所となるべく教育を受け、江戸へ出て、幾多の障害を乗り越えて将軍家へ入興するまでを描いている。薩摩は雄藩であるが、将軍家への輿入れにはさまざまな思惑が入り乱れ、斉彬の思い通りには運ばず、篤姫は不安定な状態で4年も待たねばならなかった。しかも、病弱な将軍・家定であるため、後嗣の問題が常にあり、斉彬は水戸の慶喜を次期将軍にと画策しており、篤姫にもそのための一助となるように密命を与えるのである。
幕末で、既に黒船は来航しており、各国の通商要求に幕閣は苦慮し、巷には攘夷の風が吹きすさぶ時代であるのに、女たちを取巻く環境にはそういう緊迫感がなく、不思議に思うほどである。著者はまた女性らしい細やかさで、篤姫やその取巻きを描いてゆく。薩摩から苦楽をともにする幾島や、大奥を仕切る滝山など、それぞれの立場で真剣なのだ。幕末を題材とした小説は数多いけれど、ここまで女性の視点で幕末を描き切った作品は稀有ではないだろうか。
それでも、篤姫は冷静に周囲を見て判断する能力を備えていて、大奥で次第に存在感を増してゆく。また、徳川家に嫁いだからには、斉彬の密命を忘れることはできないけれど、徳川のために良かれと思うことを第一にすべきだと思うようにもなってゆく。家定とはついに清いままの夫婦であり、継嗣を宿すことは諦めねばならないが、それでも夫を愛し、妻としてできることをしたいと思うのである。
この上巻では、井伊直弼が老中に就任し、将軍の後継には紀州の徳川慶福が決定するまでが描かれている。下巻ではいよいよ和宮も登場するはずで、とても楽しみだ。
2007年8月24日 読了