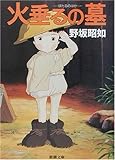ジブリアニメ『火垂るの墓』が公開されたのは1988年。
私は小学校低学年で、
母親が「観にいこうか~?」と言うのを必死に断った記憶がある。
当時、書店でみた宣伝ポスターの、清太が節ちゃんを負ぶった姿と、
そして添えられたキャッチコピー
「4歳と14歳で、生きようと思った」
だけでもう、怖くて、拒否反応が。
同時上映だった『となりのトトロ』はすごく観たかったけど・・・。
結局、全部しっかりと見たのはそれから5年ほど経ってから。
中学の授業で、視聴覚室で鑑賞させられまして(T▽T;)
・・・小学生の頃観なくて良かった、と思った。
主人公が最後まで報われない、救いのないラスト。
これは、きつい。
悪ぶりたいお年頃の男子生徒を含めて、
その場にいた8割以上の生徒が、目を真っ赤にしていた。
私は5年経って結構図太くなっていたので、なんとか受け止められたけど・・・、
でもやっぱり、夜眠れなくなった。
それにしても。
映画館で、あの楽しい『トトロ』のあとに『火垂るの墓』観た人たち、
感情が追いつかなかっただろうなぁ・・。
まだ『火垂るの墓』→『トトロ』の方が良いかも?
その後、この話が、原作者・野坂昭如の実体験をもとにした作品と知って、またショック。
でも、テレビ番組で見かけた野坂昭如って。
酒好き・女好きを標榜する「うさんくさいおじさん」でしかなくて。
なんというか・・・清太とは重ならないな、と思っていた。
(現在は闘病生活を送っているため、テレビ出演はしていないです。)
さて、今回長年の宿題を片付けるつもりで、図書館で借りました。
野坂昭如『火垂るの墓/アメリカひじき』。
表題作2作を含む、6作が収録された短編集。
読み始める前に、Wikipediaで予備知識を補強。
曰く・・・、
野坂氏は、清太のように「優しい、妹想いの兄」ではなかったらしい。
自分が生きていくのも精一杯の中で、
面倒をみなければならない妹は疎ましいだけの存在であり、
泣き止ませるために頭を叩いたり、食料はひとりじめにし、
・・・そして妹は餓死。
『火垂るの墓』は、そんな著者の、贖罪の物語なのだそうです。
感想。
ジブリの『火垂るの墓』、おそろしく原作に忠実。
エピソードの足し算・引き算がほとんどない。
でも、雰囲気がまるで違う。
どちらかと言えば、ジブリ版は、
兄妹の仕草や表情の変化を繊細に描いていて、感情移入を誘うような感じ・・・。
「画」としての美しさもあいまって、物悲しいけど、繊細で叙情的。
一方、原作。
しばしば「饒舌」と評されるという、野坂氏の文体。
句読点が少なく、故に改行が少ない。
頁を開いたとき、まず感じるのはその密度の濃さ。
読んでみると、時折助詞を省き、七五調を思わせる、
口語体であるのに、文語体の作品を読んでいるような・・・。
主人公の心情の吐露は最低限で、
事実を淡淡と連ねるような、昔の人の日記を読んでいるような。
現実を突きつけられているような切迫感。
読んで損はない。
『火垂るの墓』も、他の収録作品も、間違いなく傑作。
(うん、これは「さすが直木賞」かも。)
でも、最近の新潮文庫版がジブリの「節ちゃん」表紙だからといって、
小学生にはオススメできないです。
ちょっととっつきにくい、難しい文章だから、というよりも、
映画よりも、更に受け止め難い作品だと思うので。
主人公が可哀想だとか、周りの大人が非情過ぎるとか、
そういう同情や非難も吹き飛んでしまう、
「戦争」という異常な時代をズシン、と感じさせられます。
評価:☆☆☆☆
戦争を経験した中年男性のがアメリカ人に抱く複雑な感情。
歪んだ(これが当時は普通だったのか?)日米交流。
おそろしく不味かったアメリカからの特配品「アメリカひじき」の正体とは?― 『アメリカひじき』
12歳まで自分を育ててくれた養母。訃報を聞いて駆けつけると、
あまりにも貧しい暮らしぶり。主人公は、悔恨と共に母との日々を回想する・・・。― 『焼土層』
女は何故、自分の娘を殺したのか?
娘の存在が、その泣き声が呼び起こしてしまった彼女の「悪夢の日々」とは?― 『死児を育てる』
枚方の少年院出張所へ放り込まれた少年。
彼が盗みに手を染めたのは・・・「餓鬼」にとりつかれていたから。― 『ラ・クンパルシータ』
枚方の少年院出張所から、思いもよらず裕福な親類へと預けられた少年。
彼は幸福であるのに、どこか「落とし穴」があることを予感していた。― 『プアボーイ』
『火垂るの墓』以外の収録作は以上。
(私が読んだのは絶版のハードカバー(文藝春秋社)だけど、
画像の新潮文庫版も収録作はたぶん同じだと思う・・・。)
どれも野坂氏の体験談が反映されていると思われる。
特に、『死児を育てる』は、裏『火垂るの墓』といっていいかも。
これが氏の実体験だとしたら、あまりにもやりきれない。