第287話/戦艦内
「アメリカに勝った」という範馬勇一郎。勇次郎の実の父親だという。
猛烈な爆撃をかわし、上陸してくるアメリカの兵隊をことごとく投げ殺す。くりかえすうち、指揮官は原子力爆弾の使用という非現実的な方法まで浮かべる。
そしてその指揮官は、ある夜、旗艦となるアイオワの甲板に突き刺さって絶命していた。目撃者はひとり、背中に「ONI」を背負った男が悠々と立ち去っていったというのだ。
甲板には大勢の兵隊が集まっていて、すでに目撃者の証言によって「ONI」という表現が伝わっている。
しかし勇一郎は去ってはいなかった。そう見せかけて、たぶんふなべりの影にぶらさがるなりして隠れ、すべての兵隊が集まるのを待っていたのだ。勇一郎の動機がいったいどこにあるのか、確実なことはなにもいえないが、指揮官を殺すだけで満足しなかったところを見ると、純粋に闘争を楽しんでいるだけなのかもしれない。まだ戦争の影の残る時代であり、法制も不安定だ。まあ、こうすることではじめて、国粋主義の日本人としてアメリカに勝利したことになると判断した可能性もあるが、まあ、直観だが、そういうややこしい主義主張はないだろうとはおもう。というよりは、むしろこれは戦略ではないかとおもわれる。ふつう、ハリウッド映画でよく見る光景だが、最上級の指揮官が死亡すれば、そのすぐしたの人間が指揮をとることになるとおもうが、指揮官(名前なんだっけな・・・)はそうした指示のようなものはいっさい出さずに死んだわけだし、なにより垂直に厚い甲板に突き刺さって死ぬという姿があまりにも衝撃的で、軍隊の深層レベルでの規律は完全に乱れ、総体としてみると、2000人いるとはいっても戦場の緊張状態にあるそれとはぜんぜんちがう、不完全な戦力に弱まっているとみていいだろう。しかし、そうした戦略を用いているところを見ると、勇一郎の目的は闘争そのものではなく「勝利すること」だったことになるわけだが。
ともかく、集まった2000人の兵隊の前に肉のかたまりのような巨大な男があらわれた。こんなに縦と横の長さが近い体型はバキ世界でもあまりない。オリバよりむしろマリアのほうがバランス的には近いかもしれない。なんというかもう、四角い。
このときの様子を語るのはジョン・ヘイズ86歳、戦艦の乗員だ。アイオワは外からの攻撃に対しては当時でもA級、一流品だった。しかし視点をかえると、内部からの攻撃が想定されてつくられていないということになる。もちろん、外部が強いからといって内部が弱いとはかぎらない。鋼鉄の筋肉を持つビルダーがふつうのひとよりインフルエンザを発症しやすいということはない。しかし現場は海のうえであり、そのうえに鉄の物体が浮かぶといういわば自然のはたらきにはないふるまいを実現するものでもある。存在していることそれじたいに、一種の負荷がかかっているのである。戦艦は、そこにあることを持続するために、強固でなければならず、その負荷を内部に持ち込むことを通常よりおそれるものなのかもしれない。
ヘイズは、侵入さえ成功したなら、戦車一台ぶんほどの戦力があればことは足りるというふうにいう。侵入したところで、なかにいる兵隊と条件はおなじなのだから、そこには2000人分の戦力が必要ではないかとたんじゅんにおもうが、はなしはもっと複雑なのだろう。みたところ兵隊は装備をしていないし、リラックスモードだ。戦車というのは数値のことではなく一種の比喩、奇襲でもされたらあんがいもろいのかもしれない。
しかし「ONI」の戦力は戦車なんかではきかない。光成によれば彼はそこで不思議な技をつかったのだという。ヘイズも、あれを見て以来、パラダイムシフトしてしまい、すばらしいボクシングもただのスポーツにしか見えなくなってしまった。つまり、彼の価値観を根底から変えてしまうほどの技だったのだ。
ヘイズだけではない、その他の2000人を超える乗員のすべてが、恐怖からか、船を捨てて海に逃げ出してしまったというのだ。
彼らはその技を、「ドレス」と呼んだ。
勇次郎が周辺を注意深く見渡している。勇一郎の幻影は消え去ったらしい。
跪いたままのバキをにらみつけ、勇次郎はいう。
「懐かしい面を見て
思い出しちまった
親父の得意技術(わざ)だ」
つづく。
勇次郎が「ドレス」をつかうつもりのようである。
「ドレス」とはどのような技なのか?
なんらかの格闘技術だとすると、おそるべき方法、あるいはおそるべき威力でひとを破壊し、あんまりそれがひどいありさまなので、乗員は逃げ出してしまったことになる。
2000人が集まるのをわざわざ待っていたくらいだから、これをどうにかすることが勇一郎の目的だったはずである。
仮に2000人すべてを殺傷することが目的だったとすると、この「ドレス」という技は不完全である。ほとんどが逃げてしまっているのだから。
となると、そのなんだかわからない「ドレス」は、相手を戦慄させ、戦意を喪失させて、原理的に勝利を獲得するための技術であることになる。勇一郎なら「ドレス」を用いずとも相当数イケるだろうし。それをせずに「ドレス」をするからには、「2000人が逃げ出す」というこの結果が、勇一郎の求めた光景なのであり、「ドレス」のもたらしたものなのである。
それをして全乗員が海に飛び込んだあとの勇一郎には、見たところ変化はない。格闘技術であるにせよ、手近の兵隊をつかった試し割りのようなものであるにせよ、そこには一種の訴求性のようなものがなければならない。彼らの価値観をゆさぶり、全員でかかってもこんなやつにはかなわないと本能的におもわせ、海にとびこませる宣伝力がなければならない。
勇一郎は直前、ひとりの兵隊の顔面をわしづかみにしている。あんまりてきとうな予想をしてもしかたないが、ひとつの仮説として、「関節技によって見たことのないかたちにねじまがる人体」ということはいえるかもしれない。たとえば、それがまるで、ひとを着ているように見える、とか。
しかしそのような力技で2000人もの人間が海に飛び込むとは考えにくいし、それにそこまで極端な関節技をつかえば相手から出血して勇一郎の外見にあのように変化がないということはなさそうにおもえる。
とすると、ピクルが骨格を変化させたような筋肉操作だろうか。くりかえすように、勇一郎の目的は「ドレス」で2000人を殺傷するところにはなかった。だとしたらそれがパフォーマンス的だとしても問題はないだろう。
仮に見たことがないものであっても、わたしたちは想像可能でさえあれば、ある程度はみずからのものさしをあてがうことで、相対的に解釈することができる。価値観をゆさぶるということは、ものさしが足りない、どこにどうあてればよいのかわからない、そもそもこのものさしで正しいのかわからない、そういう状況だろう。ただの筋肉操作でそこまでの出来事が起こりうるのかというと疑問だが・・・。
あるいは、ふとしたおもいつきだが、勇一郎ほどの怪力なら、投げ倒した数人をからだの表面に防具として装着し、なおかつ、いつもとかわらぬ速度で移動するということも可能かもしれない。どのように人体をくっつけるのかという問題は残るけど。
まあ、「ドレス」の正体は来週のお楽しみということでいいが、問題はそれを勇次郎がつかおうとしているということである。
くりかえすように、現時点で判断できる「ドレス」のもたらしうる結果は、たくさんのにんげんがびびって逃げ出してしまうという状況だ。「ドレス」は、おそらくパフォーマンスなのだ。
勇一郎は「勝てる」といったが、バキはもう負ける気満々だ。いわば、いまは戦闘が停止し、保留されている状態である。
勇次郎はもちろんまだ続けたいだろう。
そうすると、ここで「ドレス」の訴求性が有効に働くのではないかとおもわれる。
勇次郎が「ドレス」をつかえば、たぶん、まず最初に、多くの素人観衆が逃げ出してしまうだろう。
勇一郎対兵隊のときとちがい、勇次郎はべつに観衆とたたかっているわけではないわけだが、闘争が「語られるもの」となったいま、まっすぐに勇次郎が観衆にむけて暴力を放ち、皆殺しにしたとしても、構造的に「観衆」がいなくなることはない。
しかしもし「ドレス」がベクトル(メッセージ性)をもたないパフォーマンスであり、なおかつ、それを見ただけで恐怖を覚え、逃げ出してしまうようなものであるなら、観衆が「自発的に退去するわたし」を承認してしまう可能性もある。それでもおそらく構造に変化はないとおもうが、少なくとも語りの声は聞こえなくなり、バキにとってはよりナチュラルな状態になるのではないだろうか。
ややこしくなってきたので当ブログの仮説を整理してみます。
親子喧嘩は観衆を導入され、「語られるもの」となったことで、ひとつ次元の繰り下げられたものとなり、バキにとって父は超越可能なものとなった。
仮に勇次郎がその場にいるものを一人残らず消し去ったとしても、「その場にいるものを一人残らず消し去った勇次郎」を語る非人称の語り口だけは残る。まったくの素人(なにものでもない、ただの目線)が観衆になることで、物語はそういう構造になった。
バキの負けの悟り、「すべてを出し切った」という実感は、彼を「じぶんもまた父に規定されるその他大勢にすぎない」という感覚におとしいれた。父を「大国に等しい」といういまさらなことばで形容しはじめたところにそれはあらわれているとおもう。
つまり、この意味で、バキを敗北に、「弱者」側に引き込んでいるのは、父ではなく、「弱者」というサイドそのものなのかもしれない。語りの声は、父を超越可能にしたが、同時にバキを「悟り」に引き込んでもいるのである。
この世に彼らふたりしか存在しなければ、バキは少なくともあのような形容のしかた、あのような感想で、敗北を悟ってはいない。
観衆の導入は勇次郎を超越可能なものとした。
次に必要なことは、たぶん、ふたりきりになることなのである。
とはいえ、この観衆たちは鬼の顔が浮かんだ光を見ても大丈夫なくらい神経太いので、あるいは「ドレス」をつかうことでバキの目を覚ます、という具合になるかもしれない。
- 範馬刃牙 33 (少年チャンピオン・コミックス)/板垣 恵介

- ¥440
- Amazon.co.jp
- 範馬刃牙 32 (少年チャンピオン・コミックス)/板垣 恵介

- ¥440
- Amazon.co.jp
- 餓狼伝(18) (少年チャンピオン・コミックス)/夢枕 獏

- ¥440
- Amazon.co.jp
- 餓狼伝(17) (少年チャンピオン・コミックス)/夢枕 獏

- ¥440
- Amazon.co.jp
- 木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか/増田 俊也
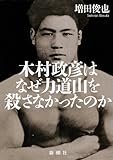
- ¥2,730
- Amazon.co.jp