(5) 食品に生えるカビとその毒性について
先に引用したように、山崎パン自身の実験で、アオカビの胞子を接種した場合に「ヤマザキ食パン」はカビが生えるまでの時間が72時間と、他社品・自社品他製品が52時間~68時間に比べて少し遅い程度の差はあります。
この差は、先に書いたように、食品衛生法でパンの中に検出限界(0.5ppb)以上検出されてはならないと決められている臭素酸カリウムによるものであることは、あり得ません。そもそもパンの中には存在しないないのですから。(これは、パンの製造に臭素酸カリウムを使ってもよい・使うべきでないという議論とは関係のない話です。)
おそらくこの差は、水分やpH、あるいはアルコール分や有機酸などの含有量の違いが原因ではないかと推定されます。(←って、可能性のある差異のほとんどですが。
何が要因かを特定するためには、この場合、ひとつの因子だけを変えた実験をすることは不可能なので、さまざまな条件が異なる実験でデータを取って多変量解析でもするしかないでしょう。そんな実験にあまり意味があるとも思えませんが。)
さて、では、パンにカビが生えるのを防ぐ食品添加物として何があるのか、山崎パンのサイトには以下のように書かれています。
Q6 カビの発生を抑える食品添加物はありますか?
食品の腐敗や変敗の原因となる微生物の増殖を抑制し、食品の保存性を高めるために使用される添加物としては、保存料と日持向上剤があります。食パンのカビ発生を抑える保存料としては、プロピオン酸カルシウム等がありますが、弊社では風味等への影響もあり保存料は使用しておりません。日持向上剤は保存料ほど微生物の増殖を抑制する効果は大きくありませんが、食品の品質を保持する効果があります。
プロピオン酸カルシウムについて調べてみると、このような記述を見つけました。
「食品ネット分析室」というサイトで、食品添加物に反対の立場のサイトのようです。
http://trinity.blog.bai.ne.jp/?eid=45627
パンの保存料としてプロピオン酸カルシウムが使われていました。最近は保存料併記を嫌いほとんど使用されなくなっています。ところが、単純に保存料を抜くだけでは、カビのクレームが発生してしまいます。そこでおかしな添加物が発売されています。パンはパン酵母で発酵させた後に焼き上げる食品ですが、パン酵母の添加とともにプロピオン酸を作る細菌を添加するのです。すると発酵中にプロピオン酸が生産されて保存効果が出ると行った仕組みです。
プロピオン酸を添加していませんので表示義務はありません。ところが食品衛生月間の夏や、お正月前の保健所の検査で測定されると表示されていないプロピオン酸が検出されて食品衛生法違反となってしまいます。
大手の発酵メーカーの製品で、かつてはパンの大手さんも使用した事がありますが、現在では中小のパン屋さんで残っている程度です。被害を被るのは仕掛けた発酵メーカーではなくそのお客さんであるパン屋さんが食品衛生法違反となってしまいます。ご注意ください!
Wikipediaでは、プロピオン酸カルシウムについて日本語のページはありませんでしたが、英語のページはありました。その毒性についてはこのように書かれています。
According to the Pesticide Action Network North America, calcium propionate is slightly toxic. This rating is not uncommon for food products; vitamin C is also rated by the same standards as being slightly toxic.
「わずかに毒性である」と。これはビタミンCと同じレベルの毒性です。山崎パンは、プロピオン酸カルシウムを、その健康影響の問題からではなく、風味の問題から添加していないと。「カビが生えない」と難癖をつけられるこらいですから、防カビ剤を添加する必然性などないでしょう(笑)。
このような食品添加物の使用の是非については、後日書きたいと思います。
話を戻すと、ヤマザキパンはカビを抑える食品添加物を使用しているわけではなく、製造工程でカビの胞子が入らないように衛生管理しているのでカビが生えにくいのであって、開封後にカビの胞子が付着して(付着させて)30℃で置いておくと3日でカビが生えてくるようです。
他の大手パン会社のパンでも同様だと考えられます。
小さなパン屋や自家製パンの場合だと、開封前でももともとカビの胞子が付着している可能性が高く、30℃で置いておけば、同じように3日くらいでカビが生えてくると考えられます。(個人的感覚的では、3日はちょっと早いような気がしますが。30℃だからでしょうか。)
さて、いよいよ今日の本題ですが、このようにカビが生えたパンを食べてもいいのかどうか、です。
長村氏が指摘したカビの毒はマイコトキシンというものでした。これは「カビによって生成される毒の総称」です。カビの種類によって生成される物質は異なり、それぞれ毒性も異なります。
マイコトキシンの中でも最も代表的なものが、アフラトキシンという物質で、急性毒性もあるし、強い発がん性もあります(クラス1)。輸入ピーナッツに含まれているのが見つかって騒ぎになったこともありますし、2008年に問題になった三笠フーズなどによる「事故米不正転売事件」で、事故米(ベトナム産・中国産)に検出されていたのがアフラトキシンでした。
東京都健康安全センターによると、
http://www.tokyo-eiken.go.jp/issue/health/webversion/web052.html
アフラトキシンはアスペルギルスフラバス(Aspergillus flavus)などのカビが作る毒素で、高温多湿の条件で作られます。アフラトキシンが作られる最適条件は、温度30℃前後、湿度95%以上であるため、汚染は主に高温多湿の熱帯もしくは亜熱帯地域で起こり、日本国内で食品にアフラトキシン汚染が起きる可能性は低いものと考えられています。
日本国内でパンにアフラトキシンを産生するカビが生える可能性は低いようです。(全く可能性がない訳ではないようなので、一応、念のため。)
ただ、カビの産生する毒にはこれほど危険なものもあることは理解すべきと思います。カビ毒だけでなく、日本人なら誰でも知っているフグやキノコの毒も天然の物質であることからもわかるように、「天然=安全」「人工=危険」という単純化した図式は明らかに間違っています。
「天然の物質にも人工の物質にも、比較的安全なものと比較的少量でも健康に悪影響のあるものとがある」という、美しくも面白くもない説明が科学的に正しい事実です。「比較的安全」と書いたのは、食塩でもビタミンCでも、過剰に摂りすぎると健康に悪影響があるからです。なお、これ以降は話を簡単にするため、「比較的少量で健康に悪影響がある物質」を単純に「毒物」と呼ぶことにします。
さて、最も知りたいことは、日本でパン(や餅など)に生えるカビは毒物を出すのか、ということですね。主にWilipediaを中心に調べました。
日本にパンに生えるカビは、主にアオカビかコウジカビだと。俗にいうクロカビは見た目に黒いカビをそう呼ぶだけで、食品に生えるのはおもにクロコウジカビであり、コウジカビの一種のようです。
それぞれを調べてみました。
アオカビ:
アオカビ(Penicillium)はアオカビ属(ペニシリウム属)に属するカビの総称。胞子の色が肉眼で青みを帯びた水色であることからその名がある。ただし、白や緑がかった色のものも見られ、必ずしもすべてのアオカビ属のカビが青いわけではない。
チーズの製造に使われる。抗生物質のペニシリンが発見された。
アオカビの大部分はカビ毒(マイコトキシン)を産生しないため、これらが直接に重篤な食中毒の原因になることはほとんどない。
コウジカビ:
コウジカビ(麹黴)は麹菌(きくきん)ともいい、アスペルギルス (Aspergillus) 属に分類される。
その一部は、味噌や醤油、日本酒の製造に用いられる。
発酵食品の製造に利用される一方で、コウジカビの仲間にはヒトに感染して病気を起こすものや、食品に生えたときにマイコトキシン(カビ毒)を産生するものがあり、医学上も重要視されているカビである。
とのことで、アオカビであれば食べても毒にならない可能性が高いけれど、コウジカビだと危険かもしれないとの結果ですね。
毒を出すカビかそうでないかの判断は専門家でも難しいようで、素人では不可能ですし、アオカビだと思っても同時に他の有害なカビの増殖も進んでいると考えるべきなので、結局、カビが生えたパンはやっぱり食べない方がいいでしょう。
餅に生えるのは主にアオカビなので、削って食べることは間違いとは言えないようですが(私のうちでもやっていました)、同じ理由で健康リスクを考えるなら食べないに越したことはないでしょう。
長村氏は示唆に富んだ逸話を紹介されています。
http://www.ffcci.jp/information/img/kaiho_4-1-3.pdf
私は約30年前にドイツに留学していたが、その時に何度も家に行き来し、家族ぐるみで交際していた友人がやっていた残ったパンの処理の仕方を思い出した。彼の家では毎朝近所のパン屋さんでパンを買ってくる。ところが、時々そのパンは食べきれずに残る。その残ったパンは翌日になると犬かまたは庭の小鳥のえさになる。ドイツ人=けちな人種、という方程式で彼らの行動を理解していた私のドイツ人感にしてはかなり奇異に思えたので、「まだ食べられるパンをもったいないではないですか」と彼に尋ねた。
彼は「近所のパン屋で作られるパンは数日もすればカビだらけになる。従って2日目にはすでに相当数の胞子がカビのコロニーを作り始めている。ここにはかなりのマイコトキシンの生産が始まっている。人類はこうした微量のマイコトキシンを食べ続けることの毒性のデータを持っていない。しかし、私はおそらくこれは健康に害があると考えている。特に、発がんを考えたら絶対に避けるべきである。だから、食べない」と即座に答えてくれた。多くのドイツ人は日本人と同じようにカビが生える直前まで食べているから、この行動はドイツ人としては少数派に属する。彼の専門研究領域は、インスリン依存性の糖尿病発症に関する分野であるのでカビ毒などとはほとんど無関係な研究者である。私は、彼の研究者らしい考え方とその実行力に少なからぬ感銘を覚えた。
(この後で、この研究者がコーヒーにチクロを入れていたと賞賛しています。この辺が、中立ではないので注意しなければならないと思う要因ですが。)
それはさておき、次の考察はなるほどと思われます。
我々世代は戦後、食糧が少ない時代に育ったので少しくらいカビの生えたパンやお餅などは平気で食べてきた。そして、自分たちは生き残っているからカビ毒はたいしたことないと思っているかもしれないが、本当にそうかという疑問が出てきた。若くしてこの世を去って行った同世代の人たちに、このカビによる犠牲者は本当にいなかったのだろうか、微量のマイコトキシンの長期摂取の問題に関しては、本格的な研究データが少ないだけに考えさせられる大きな問題である。
人間は昔からカビの生えかけた・生えたものを食べてきて生き残っているのだから、少々のカビ毒を食べても大丈夫なはず、という考えは根拠のない間違いで、一部のカビ毒に発がん性があることは明らかな事実です。
ガンになって死んでいった先祖代々多数の人たちがガンを発症した原因のひとつが、カビが生えたものを長期にわたって食べたことである可能性は否定できない・けっこうあるのではないかと、私は考えます。
カビが生えても食べないと飢えてしまうという状況ならいざしらず、現在の日本では、健康を考えて、カビの生えたものは食べずに捨てる方がよいと言えます。
それはさすがにもったいないので、小さなパン屋で買ったパンや自分で作ったパンはできるだけ早く、大手のパン会社のパンでも開封後は早く食べきってしまうこと、もし保存するなら、冷凍するなどしてカビが生えないように保存することが大切でしょう。
今日はこんなところで。
食品添加物についての考察(結論?)は、明日書くことにします。
脱線その1:
カビの学名って、マンガ「もやしもん」で出てきましたねぇ。
下の左がペニシリウム・クリソゲヌム(アオカビ)、右がアスペルギリス・オリゼー(コウジカビ)。
名前覚えられないけど。

「もやしもん」は、菌が見える(!)という特殊能力を持つ主人公で農業大学が舞台のマンガです。
第12回手塚治虫文化賞マンガ大賞、第32回講談社漫画賞一般部門受賞。
コミックスは一式揃えていたけど、最新版(10巻、2011年3月発売)はまだ買っていないようなので、買わないと。
もやしもん(10) (イブニングKC)/石川 雅之
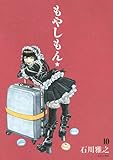
¥570
Amazon.co.jp
「もやしもん」のアニメは見てないのですが、深夜の実写ドラマは見てました。原作に忠実だったような。笑い飯の西田氏は、多分、原作でのモデルなんでしょうね。似すぎです。
ドラマ出演の女性たちが可愛かった。加藤夏希は(その前からも)その後も活躍してるけど、他の女性たち、ちすん・はねゆり・岡本あずさってみんな、その後どうしてるんだろう?
脱線その2:
コウジカビの「アスペルギルス」という学名は、分生子がカトリックにおいて聖水を振りかける道具であるアスペルギルム(Aspergillum)に似ていることから命名された。
「アスペルガー症候群」は、オーストリア・ウィーン生まれの小児科医であるハンス・アスペルガー(Hans Asperger)が名づけたもの。
ということで、たまたま私のブログで相次いで登場したとてもよく似た言葉ですが、全く関係がないことがわかりました。