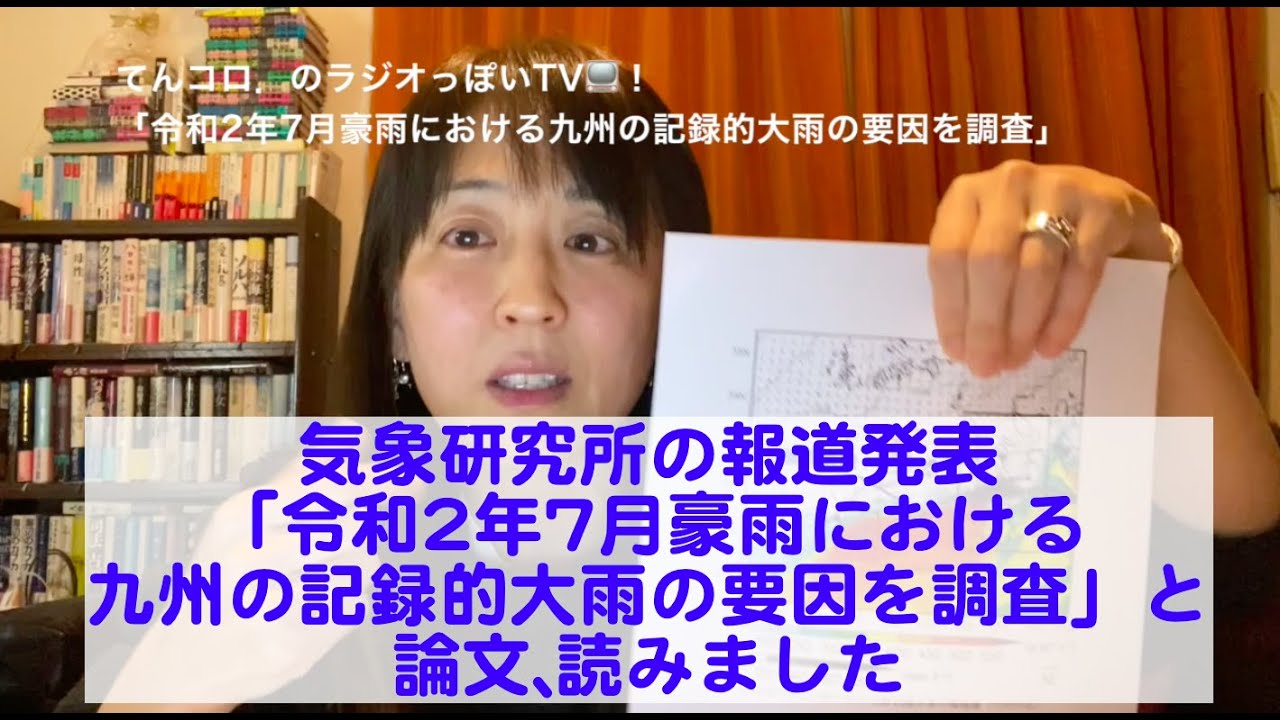気象研究所報道発表資料より↑
12月24日,気象庁気象研究所からの報道発表資料
「令和2年7月豪雨における九州の記録的大雨の要因を調査」
そして,記録的な大雨の要因についての
論文も読みました
https://doi.org/10.2151/sola.2021-002
ポイントは,
特に梅雨前線上の小低気圧があった(発達した)こと,
上空の寒気流入があったこと.
梅雨前線上の小低気圧って,
解析されるされないは別として,
珍しいものではないと思うのですが
今回の事例では,すごく重要な役割を担ってしまった
とのこと.
低気圧が発達して,低気圧の南側で水平風速が強まり,
多量の水蒸気の運び手として働いてしまう,
それが,太平洋高気圧の縁辺流と収束して
大気下層に多量の水蒸気がある収束線上に
線状降水帯が形成されてしまったようです.
さらに私が驚いたのは,上空250hPaの寒気の動向.
トラフ後面に入る上空寒気のせいで,
積乱雲がより高い高度まで発達できてしまう
環境になっていたようです.
普通の梅雨期は,
上空寒気なんてなくても,
下層に多量の水蒸気が流入するだけで
だいぶ不安定なのに,
上空に寒気が入ることで
非常に不安定になってしまったんですね.
でも,ここで注意しなければならないのは,
「上空に寒気が入った」だけでなく,
下層から中層にかけては気温が高いということです.
これにより,大気の下層から中層にかけて
大量の水蒸気が存在する状況になっていました.
報道発表資料,論文を読んで
線状降水帯を精度よく予測するためには,
メソ低気圧の監視・予測が有効そうだということも
分かりましたが
それでも完全に予測するのは難しそうです.
では,私たちが今すぐできることはどんなことだろう.
ここに示された危険要素のうちのいくつかは
普段見ている天気図などでも,把握できることです.
例えば,大気の鉛直方向の温度分布は
状態曲線や高層天気図を見れば
ある程度確認できますよね,
そこで危険を見逃さない,危なさを察知すること
それが大事だと思います.
<令和2年7月豪雨における九州の記録的大雨の要因を調査」と論文読みました.(てんコロ.のラジオっぽいTV!)>