 ブログネタ:何してるときが一番幸せ?
参加中
ブログネタ:何してるときが一番幸せ?
参加中[ 何しているときが一番幸せ? ]
そりゃぁ友達と馬鹿なことをしあって、バカみたいに笑い、バカみたいに遊び、バカみたいに寝る…のは違うか。どんなに遅く寝ても、皆がいると朝きっちり目が覚めちゃうんだよなぁ。まだ遊び足りないということでしょうかね。
でもそんなバカな時間はそうそう作れるものじゃありません。
身近に、かつ一人でできるという点ではやはり本を読んでいるときは幸せですかね。
さて、以前蒲公英草紙
を読み、常野一族の魅力にやられた僕は、続けざまに光の帝国を読みました。
光の帝国-常野物語 著:恩田陸
- 光の帝国―常野物語 (集英社文庫)/恩田 陸
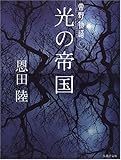
- ¥520
- Amazon.co.jp
あらすじ
膨大な情報(書物や談話など)を暗記するちから「しまう」
遠くの出来事を知る力「遠耳」
将来を見通す力「遠目」
などなど、常野一族にはそれぞれ不思議な能力があった。しかし、気性は皆穏やかで、誰とでも親しくなり、人当たりも良い。しかし、そのなりを潜め、静かに、普通の生活をしている。
彼らの役目を全うするために。。。
彼らは何のために存在し、何のために生きるのか。
不思議な能力を持つ人々の運命を探る連作短編集。
これは短編集ですが、どれひとつ欠いてもいけない。短編集のかたちをとっているのは、常野の「ちから」が様々であり、それぞれの生活を引き抜いたからではないでしょうか。
しかし、常野は皆別々の場所へ広がっているけれど、ひとつの収束へと向かおうとしている。よって各短編作品がそれぞれつながりを持ち、あっちでツル先生、こっちでツル先生、あっちで遠目、こっちで遠目…とそれぞれが重要な位置を占めています。
常野は様々なちからがあります。どれも有効的で、手に入るものなら欲しいと思えるようなものばかりです。
しかし、常野には常野の苦悩がある。やはり得意なちからというのは、それなりの代価が必要なのです。
近い将来が見えるからこその苦悩、しまえるからこその疲労。
一方で、近い将来が見えるからこその喜び、しまえるからこその奇跡、そういったものももちろんあるようです。
でも僕は、苦悩の方が強く脳内に刻み込まれてしまいました。
怖い、怖い、怖い。
僕が常野の人間だったら、今の世で生きていけるかどうか…
この作品の面白いところは、それぞれのちからの使い方はもちろんのこと、常野という存在の不明確さがしっかりあることでしょうか。今回は、蒲公英草紙よりもぐっと常野一族に迫った作品ですが、それでもいくつもの謎が残る。もしかしたら彼らのような人間が、逸話、寓話、昔話なんかを残すのかもしれませんね。
僕はミステリー小説を読んだことがないので、どんなものなのか知りませんが、この作品はミステリー要素も多少含んでいるのでしょうか。いや、ミステリーというかホラーかな?それでも救いの手が差し伸べられているからなんとか読み終わってもスッキリします。ん~?でも能力が能力だけにホラーとは言いがたいかな?かといって怪談という感じでもないし…。
そう!世にも奇妙な物語のような、そんな感じですかね。世にも~よりすっきり読める点では光の帝国の方がしっくりきて好きですが。
ふぅ…
この作品のなかで、常野の秘密を完全な形で残した作品がありました。オセロ・ゲームという作品です。どうやらエンド・ゲームという作品の中でも彼らのちから、秘密として残された力が描かれているようです。
が、まだ文庫本発行にまで至っていないので、彼らの秘密を知るまでにもう少し時間がかかりそうです。
…なんだかすっかりこのシリーズにはまってる…