一度挫折しましたが、無事読了
虞美人草
夏目漱石 著
新潮文庫
- 虞美人草 (新潮文庫)/新潮社
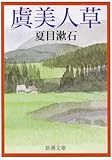
- ¥594
- Amazon.co.jp
男女六人の、絡み合った運命が描かれています。
径何十尺の円を描いて、周囲に鉄の格子を嵌めた箱を幾何となくさげる。運命の玩弄児はわれ先にとこの箱へ侵入る。円は廻り出す。この箱に居るものが青空へ近く昇る時、あの箱に居るものは、凡てを吸い尽す大地へそろりそろりと落ちて行く。観覧者を発明したものは皮肉な哲学者である。
(285ページ)
ときどき少し鼻につくほどの、全篇に散りばめられた、美しい表現の数々。
時ならぬ春の稲妻は、女を出でて男の胸をするりと透した。色は紫である。
(34ページ)
酔いしれたり、くじけそうになったりもしつつも。
人間描写が、実に面白くて!
女同士の、水面下の静かな駆け引きとか、どちらの女性を選ぶかで鬱々とする、詩人の小野さんとか。
正反対の性質のように思えた、甲野さんと宗近くんの、魂の深いところで通じ合っているような、男の友情、絆とか。
宗近君は巻烟草を燻らし始めた。吹く烟のなかから、
「これからだ」と独語の様に云う。
「これからだ。僕もこれからだ」と甲野さんも独語の様に答えた。
(394ページ)
裕福な家の育ちで、学問もあって、傍から見ると好きなようにゆるゆると生きているように見えた二人が、いつの間にか、各々のこれからに向かって一歩踏み出している。
主要な登場人物たちの殆どが、これからに進んでいく。
能動的に、もしくは受動的に。
その一方で、これからの先が無い人もいて。
もちろん、悲劇のヒロインやヒーローが居てくれるからこそ、悲劇というドラマが成立するのですよね。
そして甲野さんも記しているように、悲劇を体験するからこそ、他人の死という事実を経験するからこそ、私たちは生のありがたみを実感する。
襟を正し、生きなければと思う。
理屈では、そうなんですけどね。
シェイクスピアの悲劇を読むときには、これは悲劇なんだこういうもんだ、と割り切って読むから、いいのですけれど。
そしてそういえば、物語の序盤から、登場人物たちがシェイクスピアを読んでいるのでした。
自分のことを一番に愛しているように見える、藤尾も。
(でも、それだけじゃないと思う。漱石はそう思っているのかもしれないけど、私は)
自分と、自分の延長線上の娘のみを愛していて、自らの保身ばかりに注力する、藤尾の母も。
煮え切らない態度で、周りの人を闇雲に傷つけていく、小野さんも。
人間の理想通りに生きられない人たち、打算で行動してしまう人たち、でも彼らの姿もまた、人間が生きているという形でもあるから、もちろん理想は正義であるだろうけど、志すべきは徳であるだろうけど、そのあるべき線路からはみ出してしまった人たちに、現代の私は共感したりもしてしまいました。
価値観の違う他人たちが、価値観の勢いよく流れ変化していく時代の中で、どう歩んでいくのか。
どう認め合い、折り合うのか。どう認め合えないのか。
考えさせてくれました。
この作品では、人がどう生きるべきかより、どう社会があるべきか(そのためには人がどうあるべきか)に、比重が置かれているのかな。
外には白磁の香炉がある。線香の袋が蒼ざめた赤い色を机の角に出している。灰の中に立てた五六本は、一点の紅から烟となって消えて行く。香は仏に似ている。色は流るる藍である。根本から濃く立ち騰るうちに右に揺き左へ揺く。揺く度に幅が広くなる。幅が広くなるうちに色が薄くなる。薄くなる帯のなかに濃い筋がゆるやかに流れて、仕舞には広い幅も、帯も、濃い筋も行方知れずになる。時に燃え尽した灰がぱたりと、棒のまま倒れる。
(447ページ)
香りは仏に似ている。色は流るる藍である。
そうして燃え尽した灰がぱたりと、倒れる。
この数行に渡る線香の描写に、泣いてしまいそうになりました。
☆
女性たちが皆、生き生きと魅力的に描かれています。
藤尾も、小夜子も、糸子も。
いちばん感情移入してしまったのは、小夜子でした。
会えなかった五年の間に、見違えるように変わった小野さん。
それに比べ、何も変わらない自分。ひとり置いて行かれそうに、感じる気持ち。
せつない。。。
糸子は、朗らかな外見の内に隠した芯の強さがすごいです。
実は誰よりもたくましいし、よく人を見ている。
藤尾も、あまりに強烈すぎて、好きというわけではないけれど、嫌いにはなれないです。
「ホホホホ」というかん高い笑い声が、いつまでも耳に残っています。。。
『三四郎』、『それから』、『門』、と読んだ後に、古いこの作品に戻ったので、おや、と思うところはありました。
これと『それから』までの間に、漱石に何があったのでしょう。。。
はざまの時代に、かねてより読みたかった『抗夫』が位置するようなので、『抗夫』への興味が増しました