今回読んだ本は、新田次郎さんの「武田勝頼」です。読もうと思ったきっかけは、今年のNHK大河ドラマの「真田丸」です。こちらは真田昌幸をはじめとする真田一族が戦国時代の苦難を乗り越えて行く姿を描くドラマですが、それが武田家の滅亡から始まります。甲斐の武田家と言えば、武田信玄が一代で築いた戦国最強とも呼ばれる軍団で、にもかかわらず信玄が病死後は勝頼の代で呆気なく滅んでしまいました。信玄や風林火山の旗印などはよく知っていたのですが、勝頼のこととなると、考えてみるとあまり知りません。特になぜあれほどまでに易々と滅ぼされてしまったのか。調べてみると、新田さんが「武田信玄」に続いて「武田勝頼」も小説として書いていましたので、それでは読んでみようと思った次第です。
今回は、「陽」の「花嫁売込合戦の次第」から「捨てられた長篠城」までです。
- 新装版 武田勝頼(一)陽の巻 (講談社文庫)/講談社
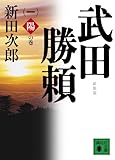
- ¥823
- Amazon.co.jp
「花嫁売込合戦の次第」
花嫁売込合戦とは、奥平貞昌への花嫁を武田方、徳川方、双方から差し出し、山家三方衆の一つ、奥平家を味方につけようと画策したことを指しています。
勝頼は、穴山信君を主軸とした家臣団に対して反発し、病気と称して引きこもり、評議の座に出なくなりました。或る日、暇に任せて躑躅が崎の館を歩き回っていた勝頼は、人質館の裏手で少女を見掛けます。少女は山家三方衆から差し出された人質のお阿和で、奥平貞昌と結婚することになっていました。長坂長閑(釣閑)斎は跡部勝資と策を弄し、作手城に乗り込むと貞昌の父である奥平貞能と交渉を開始します。「貞昌には武田信豊の次女を輿入れすることとし、奥平家からはお阿和を勝頼の内室として輿入れすることにしたい」と半ば命令的に切り出します。
貞昌は父の貞能の言うことを聞かず、困った貞能は隠居している祖父の貞勝に相談します。貞勝は「武田の使者には承知したと答え、祝言は新館が出来上がる秋か冬頃にしたいと言えばよい。待てば情勢は変わるだろう」と言って笑うのでした。
その後、貞能は徳川家康からの密書を得ます。それには、家康の女(むすめ)を貞昌の正室にし、山家三方衆全ての領地をくれると書いてありました。貞能は家康に従くことを約束します。
「饗(もてなし)風呂」
饗風呂とは、作手城の城主である奥平貞能が、目付け役の小笠原新弥らの武田勢から逃れ、徳川方へ寝返ろうとした際に、武田勢を欺くために城内の豪華な風呂に入れてもてなしたことを指しています。
信玄の死はもはや周知の事実となり、三河、遠江方面では徳川家康の巻き返しが活発化していました。家康の率いる三千の軍が長篠城へ向かったため、武田軍は三河方面に武田信豊ら五千、遠江方面に武田信廉ら五千が向かいます。長篠城から四里ほどのところにある作手城は奥平貞能、貞昌父子が守っていましたが、徳川軍の進撃を阻止する様子はありませんでした。武田軍が出動すると、家康は浜松に退きます。武田信豊は黒瀬(玖老勢-愛知県新庄市)に陣を構えると、貞能を黒瀬の陣屋に呼び出し、作手城への帰り道で殺そうとしましたが、見抜かれてしまい、失敗します。次に信豊は、作手城の目付け役でもある初鹿野伝右衛門に命令して、奥平貞能等の家族を人質として差し出させようとしましたが、長持や道具の移動をわざと手間を掛けながらゆっくりと行ない、簡単には人質になろうとしません。小笠原新弥と草間備前は様子を見に行くとともに準備を急がせようとするのですが、貞能は二人を風呂に誘い、出た後には酒肴を出して盛んにお世辞を述べ立てます。
小笠原新弥と草間備前は貞能の舌先三寸に言いくるめられて、こやつ臭いぞ臭いぞと思いながらも、つい酒をのみ肴を口にして時間を過ごしてしまいます。その間に、奥平の一族とその家来たちは脱出の準備を急いでいたのでした。
「捨てられた長篠城」
奥平貞能、貞昌父子はまんまと作手城からの城抜けを成功させます。明らかに武田軍は負けたのでした。負けて奥平一族を取られてしまい、それは三河における武田勢力が著しく後退したことを示します。信玄が生きていたら奥平一族が離反しようなどという気も起さないし、家康も山家三方衆の抱え込み工作もしなかっただろうし、信玄が死んだということはこれほどにも士気に影響するのかと愕然とするのでした。
次に徳川軍は武田勢が残る長篠城を包囲し、連日連夜攻め立てますが城兵二千はよく戦い守り通します。徳川軍は一旦攻撃を止めて引揚げて行きますが、ほっとした城兵が油断した隙に、城内の徳川方に心を寄せている兵が火を放って、長篠城は焼け落ちてしまいます。
甲斐の古府中から走り馬が来ます。一頭は勝頼からの使者で「焼けてしまった長篠城は放棄せよ」と言い、もう一頭の穴山信君からの使者は「長篠城は信玄公が三河を押さえる要の城と申されていた。直ぐ築城にかかり、長篠城を敵に渡してはならぬ」と伝えます。武田信豊は勝頼の命令を守りました。家康は長篠城と共に運を拾い、勝頼は長篠城を捨てた瞬間に運にも見放されていたのでした。
この後、武田家滅亡の直接の原因となる長篠の戦いは、この三河の北部に位置する長篠城を廻っての合戦でした。長篠城は、信玄が亡くなった直後から武田家の運命を握っていた訳で、武田家にとっては因縁の城と言えそうです。
- 武田信玄と勝頼―文書にみる戦国大名の実像 (岩波新書)/岩波書店

- ¥799
- Amazon.co.jp

