今回読んだ本は、新田次郎さんの「武田勝頼」です。読もうと思ったきっかけは、今年のNHK大河ドラマの「真田丸」です。こちらは真田昌幸をはじめとする真田一族が戦国時代の苦難を乗り越えて行く姿を描くドラマですが、それが武田家の滅亡から始まります。甲斐の武田家と言えば、武田信玄が一代で築いた戦国最強とも呼ばれる軍団で、にもかかわらず信玄が病死後は勝頼の代で呆気なく滅んでしまいました。信玄や風林火山の旗印などはよく知っていたのですが、勝頼のこととなると、考えてみるとあまり知りません。特になぜあれほどまでに易々と滅ぼされてしまったのか。調べてみると、新田さんが「武田信玄」に続いて「武田勝頼」も小説として書いていましたので、それでは読んでみようと思った次第です。
小説は「陽」、「水」、「空」の三部作となっており、頁数では500頁 X 3冊 にもなる大作ですので、何回かに分けて感想を書いてみようと思います。
今回は、「陽」の「生い立ち」から「暗雲低迷」までです。
- 新装版 武田勝頼(一)陽の巻 (講談社文庫)/講談社
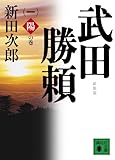
- ¥823
- Amazon.co.jp
「生い立ち」
- 武田勝頼は甲斐の古府中(甲府市)の躑躅ケ崎の館において出生します。母は諏訪頼重の女の湖衣姫で、信玄の側室でした。勝頼は数えて四男に当たるため、四郎と名付けられました。勝頼の初陣は十七歳で、上州箕輪城の攻撃に参加し、敵の大将藤井豊後守と組み討ちをしてその首を上げました。信玄は聊爾者(軽はずみな奴)と戒めますが、勝頼はその後の戦にも先頭に立って戦い、武田家中に次第に名を高めて行きました。
信玄には嫡男の義信がいましたが、たびたび意見が衝突し、信玄は義信を幽閉します。義信は病死し、勝頼は思いがけず、信玄の後継者となります。信玄は勝頼を帷幕の将として作戦や実戦に従事させ、徐々に総大将としての器に仕上げようとしましたが、これは武田信玄一生一代の誤りでした。勝頼は信玄の後継者の位置に座り、実質的に武田の統領としての実権を握るまでには至っていませんでした。
死期を知った信玄は、勝頼と山県昌景にこもごもと「余が死んでも三年間は死を秘めておき、その間に勝頼は武田の統領としての地位を確立せよ」と遺言します。しかし、結果としては武田の諸将が信玄の死を隠したことがかえって諸国の不信を招き、武田内部に信玄の死によって内紛でも起きたのではないかという疑心までも起させたのでした。
勝頼の目には暗雲、模糊として漂っていました。
「陰々滅々」
三河の徳川家康は信玄が死んだのは確実だという情報を得て、山家三方衆を武田の手から取り戻すことを始めます。山家三方衆とは、三河の北部山岳地帯に定着している北設楽田峯の菅沼氏、南設楽長篠の菅沼氏、作手の奥平氏の三氏のことです。最初は今川、その後に徳川、今では武田の将秋山信友などの攻撃により武田の勢力下に置かれていました。家康は作手城の奥平貞能、貞昌父子に調略の手を延ばします。
長篠城を守備していたのは、城主菅沼正貞と目付け役として入っていた武田勢の室賀信俊らでした。室賀信俊は作手城の奥平父子の動きに不審の点があることを勝頼に知らせます。しかし、勝頼はそのままにして置きます。父信玄が死んだ後は命令系統が乱れ、勝頼が命令してもすぐに実行できる状態ではなかったのでした。それは信玄の死去した直後に起こりました。内藤昌豊が信玄の後を追って自害しようとしたのです。
内藤家は信玄の父信虎の家老でしたが、信虎の非道を諫言したことで武田家から離れますが、信玄の代に再び戻って来て、重く用いられていました。しかし、武田家と最も血縁関係の深い家柄でもある穴山信君は内藤昌豊とそりが合わず、疑い続けていました。三方ケ原の合戦で、内藤隊が予定どおりの動きをせず、そのために家康を取り逃がしてしまったと考えていたからです。内藤昌豊は我慢ならず、信玄の病気が快方に向いたら身の潔白を述べるつもりでしたが、その信玄が死んでしまったため、腹を切って身の証を立てようとしたのでした。
勝頼は内藤昌豊に誓書をしたため、血判することで昌豊に切腹を思い止まらせますが、勝頼の地位は甚だ不安定であり、こうしなければ有力武将の離反を誘うような状態だったのです。
「暗雲低迷」
暗雲低迷とは、信玄の死後二ヵ月が経った甲斐の国で、武将間の内紛が起きそうな気配となったことを指しています。
遠江方面では、家康の攪乱作戦が続いていました。山家三方衆に対する家康の調略が疑う余地のない事実であり、長篠城の副将室賀信俊から古府中の勝頼に書状が届きます。内藤昌豊や跡部勝資は軍勢を早急に送るよう発言しますが、穴山信君は信玄の「三年間喪を伏せよ」という言葉を盾に、家康の挑戦を知らんふりにして見ていようと言い、勝頼はそうせざるを得ませんでした。
信玄の存命中、武将の中心となるものは山県昌景や馬場信春でしたが、信玄が死ぬと同時に信君が軍議の席上で主役を務めるようになっていました。勝頼は武田の統領、信君は義兄であり従兄であって主従関係ははっきりしていますが、信君は勝頼をお館様とは呼ばず、四郎殿という呼名を使い続けていました。信君は四十五歳、勝頼は二十七歳、親子ほども年齢が違っており、四郎殿と言われても勝頼はどうすることもできません。
その時、信君に「先代様の後目を相続される勝頼様に対して、四郎殿とは聞き捨てならぬ」と下座から発言したものがいました。長坂釣閑斎でした。長坂釣閑斎は跡部勝資の推挙によって側近に加わっていました。釣閑斎は「拾い馬の釣閑」と呼ばれていました。川中島の戦いで、上杉謙信の乗馬を捕えたのですが、恩賞の沙汰があった時、「馬は拾い物であり、馬を曳いていた敵を討ち取った手柄だけで結構」と答えたのでした。当時、信玄はこの話を聞いて「口才にたけた者・・・」と傍にいた山県昌景に呟いたのでした。そのような釣閑斎が勝頼に召し出されて側近に加えられたことを昌景は不安に感じていました。
山県昌景が釣閑斎をたしなめた後、さらに跡部勝資が釣閑斎を叱ってその場を繕いますが、穴山信君は憤然としてその席を去ったのでした。
多くの宿将たちが心配していたことが起こります。長坂釣閑斎の家臣が、穴山信君が登城するところを見計らって切り込んだのでした。信君の側近が防ぎますが、山県昌景と馬場信春はこの事件の後、収拾策に乗り出します。如何に隠しても信玄の死はもはや公知の事実となっています。取り敢えずは勝頼の跡目相続の儀式を行なわねばならぬというのが宿将昌景と信春の切なる願いでしたが、穴山信君は聞かず、また信玄を神格化して考えている武将の中には信君を支持する者が多く、容易に昌景等の誘いには応じませんでした。
稀有の才能を持った先代が一代で築いた巨大組織が、突然瓦解して行ってしまう典型的なパターンです。これまでは組織を支えていた有能な幹部たちが、今度は逆に組織を破壊する力に変わってしまっています。このままではいくら勝頼が優秀な跡取りであっても、信玄の築いた武田家は滅んでしまいます。どうする勝頼...
- 武田家滅亡 (角川文庫)/角川書店(角川グループパブリッシング)

- ¥994
- Amazon.co.jp

