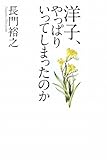おはようございます。
岡本大輔です。
以前紹介した書籍、
の続編で、
南田洋子さんが亡くなってから
書かれた書籍を紹介します。
本書の内容を介護職が
捉えるのならば・・・
”男性介護者の想い”の一つを
知ることができる書籍です。
この想いを知って
今日からの介護に・・・
お客様だけでなく、その家族へのケアを
考えてほしいと思います。
本書の出会いは
帯広図書館です。
前回の書籍を読んでから
「長門裕之」で検索したところ、
本書が出てきました(貸し出し中でした)。
抜粋です。
↓↓↓
第一声の”ばかやろー”
萩本欽一さんの言葉・・・
”ばかやろう”は大好きだよ、
愛しているよ、なんで一人にするんだよ、
もっと尽くしたかったよに聞こえた。
こちらの抜粋は南田さんが亡くなって
長門さんが仕事が終わって
初対面のところです。
第一声が「ばかやろー!」だった
ということ。
そして、隣にいた萩本欽一さんが
その”ばかやろー”を葬儀のときに
意訳していたのです。
この部分を読んで僕は
早速涙が出てきました。
あとの抜粋にも続きますが、
「なんで一人にするんだよ」
「もっと尽くしたかったよ」
が長門さんの
本音だったのだろうと思います。
介護の真相・・・
介護疲れで自分が先に逝く、
妻を看取るのが怖かった、
受け入れたくなかった。
前回の書籍では
「妻の介護は自分の役目」と
話していました。
その真相は
妻を看取るのが怖い
妻の死を受け入れたくない
・・・男性の弱さを
垣間見たところでした。
この部分に対して、
長門さんに悪印象はありません。
堂々と書籍で本音を
話してくれて
「ありがとうございます。」と
伝えたいです。
妻との別れは
長年連れ添った妻を
失っただけでなく
妻でありながら
もう一度恋した女を失った、
失恋も同時にした。
先ほどの抜粋にプラスして
妻を介護していたのでなく、
恋人を介護していた。
だから、介護の専門職など
他人に介護されるのを嫌がった
という解釈をしました。
世の男性介護者全員が
そう思っているとまでは
言いませんが、
参考になる部分です。
”妻”の介護でなく
”恋人”の介護であれば
他人に指一本触れさせたくない
という想いが出るのは
当然なのかなと
僕も感じました。
生きることに未練があるか問われたら、
「当たり前だ。未練があるさ」と
胸を張って言う、
何かにすがって生きること・・・
それは恥ずかしいことではない。
南田さんが亡くなってからの言葉です。
僕自身ににも同じように
問わせてもらいました。
僕も今死ぬとしたら
未練ばかりです。
長門さんの半分も人生を生きていない。
それでも
いつかは年老いて死ぬときが来る。
その日までは
たとえ何かにすがってでも
生きていこう。
(すがらないでがんばることを
前提に)。
演技ができなくても、
伝達ができなくても、
手足が不自由になっても、
誰の命も輝いている。
長門さんは今回の書籍で
伝達ができなくなる=死に近い
という表記をしていましたが、
それでも南田さんが
亡くなってからは
上記のように
できないことが多くなったとしても
誰の命も輝いている
と締めてくれました。
まとめとして、
男性介護者の中には
自分が先に逝きたいと想う人
妻に恋している人
妻の死を受け入れられない人
などのケースがある。
(妻の)介護をしていくことが
自分の生きる支えになることもある。
介護の専門職として
もしケースに当たるときは
「なぜ、一人で抱え込むのか?」
を考えてこのような家族に接したい。
そして、
ケアに当たっては
介護保険を使うばっかりが
正解ではないということ
選択肢を幅広く持つことが
大切だと教えられました。